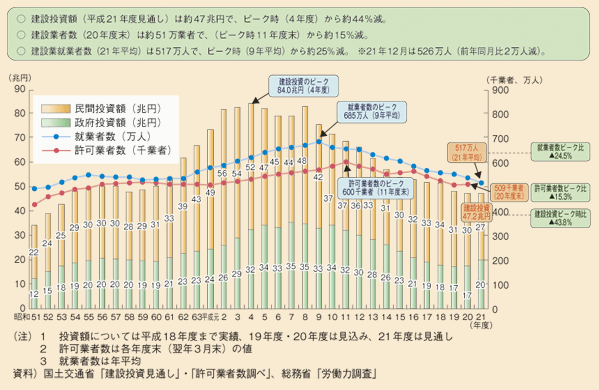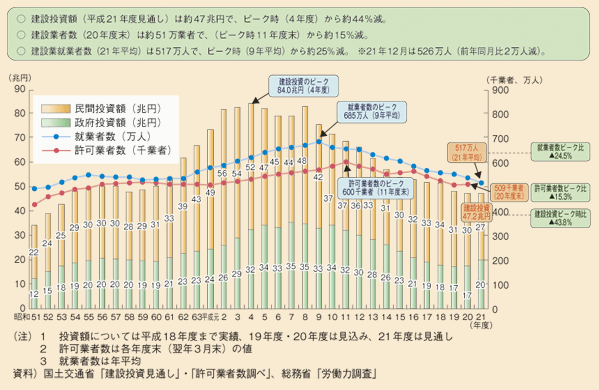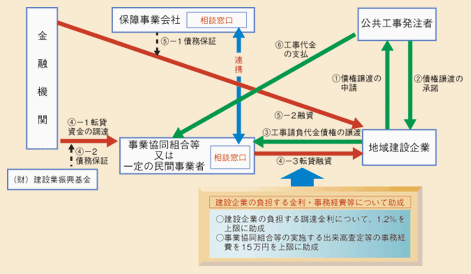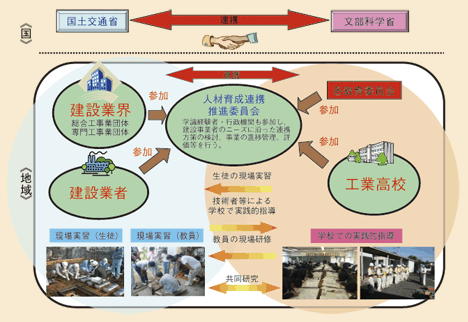8 建設産業の活力回復
(1)建設産業の現状
建設業は、国民生活に不可欠な社会資本の整備・維持管理や災害発生時の対応等、地域の経済社会を支える役割を果たしており、国内総生産・全就業者数の約1割を占める基幹産業の一つである。しかし、民間建設投資の急激な落ち込み、価格競争の激化といった課題に直面し、また、今後は、人口減少、少子高齢化、厳しい財政状況という制約の中で、新規の公共事業を抑制せざるを得ない状況にあり、建設産業を取り巻く環境は、かつてないほど厳しい状況にある。
図表II-5-4-13 建設投資(名目値)、許可業者数及び就業者数の推移
(2)公正な競争基盤の確立
建設投資が急激に減少する中で「技術力・施工力・経営力に優れた企業」が生き残り、成長するための競争を実現するためには、建設業者における法令遵守の徹底を始めとする公正な競争基盤の確立が重要である。このため、従来より下請取引等実態調査や立入検査等を実施しており、建設業における元請・下請間の取引の適正化に取り組んでいる。また、平成21年7月には建設工事の請負契約をめぐるトラブル・苦情等の相談窓口として「建設業取引適正化センター」を設置し、さらなる法令遵守の徹底に向けた取組みを推進している。
(3)資金繰りの円滑化
建設企業の資金繰りの円滑化等を図るため、元請建設企業が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について未完成部分を含め流動化を促進すること等を内容とした地域建設業経営強化融資制度を創設し、平成20年11月から実施している。
本制度は、元請企業が、公共工事請負代金債権を担保に事業協同組合等又は一定の民間事業者から出来高に応じて融資を受けられるとともに、保証事業会社の保証により、工事の出来高を超える部分についても金融機関から融資を受けることが可能となる制度であり、元請建設企業の金利負担等の軽減が図られる。
図表II-5-4-14 地域建設業経営強化融資制度
(4)ものづくり産業を支える「人づくり」の推進
建設産業は、技術者・技能者がその能力をいかに発揮するかによって生産の成否が左右されるものであり、「人」が支える産業である。しかし、建設産業就業者を取り巻く労働環境が厳しい状況となり、就業者の高齢化が進展する中、建設技術・技能の承継を円滑に推進するためには、将来を担う優秀な人材の確保・育成と建設産業就業者に対し、適正な評価が行われる環境整備が不可欠である。
このため、地域の建設業界と工業高校等が連携して行う、建設技術者・技能者による生徒への実践的指導などの取組みや、建設業団体等による建設技能の承継及び建設労働者の確保・育成に資する取組みに対し、支援を行い、その成果の普及に取り組んでいる。
図表II-5-4-15 地域の建設業界と工業高校等が連携した将来の人材の確保・育成に向けた取り組み
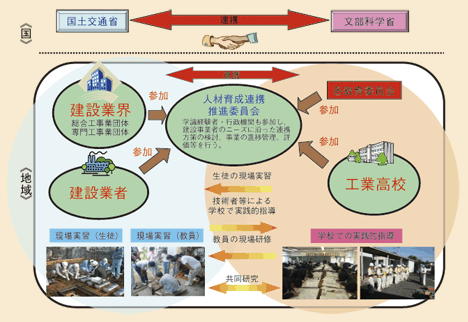
また、施工現場で直接生産活動に従事する技能者のうち、作業管理・調整能力等を有し、基幹的な業務に従事する登録基幹技能者の確保・育成・活用を推進している。登録基幹技能者数は、平成21年9月末現在で15,086人(23職種)となり、総合評価落札方式(試行工事)などで活用を図っている。
(5)建設産業の振興
地域の中小・中堅建設業者の団体が、その保有する人材、機材、ノウハウ等を活用して、農業、林業、観光、環境、福祉等の異業種団体及び自治体との連携により協議会を設立し、建設業の活力の再生、雇用の維持・拡大や、地域の活性化を図ろうとする場合に、連携事業に関する検討や試行的実施に必要な経費を助成する建設業と地域の元気回復助成事業を創設した。これまでに157件を選定し、事業を推進している。また、大学・異業種企業等の持つ技術・事業シーズと建設企業をマッチングし、新たな事業展開を支援する建設業と異分野とのコラボレーション促進支援事業も実施している。
さらに、従来より、中小・中堅建設業者の新分野進出や経営革新、経営基盤強化の取組みを円滑化するため、建設業者が関連するサービスを一元的に提供するワンストップサービスセンターを各都道府県に設置し、関係省庁と連携して支援している。特に、建設企業の成長分野展開については、中小企業診断士などのアドバイザーによる相談回数を増加するなど、相談体制の充実を図っている。
そのほか、中小・中堅建設業者の継続的協業関係の確保により経営力・施工力を強化するため、経常建設共同企業体の適切な活用を促進している。また、中小・中堅建設業者の組織化、事業の共同化を推進しており、事業協同組合等(注1)による共同事業の活性化や事業革新活動を促進している。
また、建設関連業(測量業、建設コンサルタント、地質調査業)は、建設投資が減少している中、業務成果の品質確保等を図るとともに技術力と人材を経営資源とする知的産業として、適正な競争市場への参加と新たな業務領域の拡大に取り組んでいる。国土交通省では、建設関連業の登録制度の適切な運用等を通じて、優良な建設関連業の育成と健全な発展に努めている。
(6)建設機械の現状と建設生産技術の発展
我が国における建設機械の保有台数は、平成19年度で約92万台(注2)と推定されており、建設機械の購入者別の販売台数シェアで見ると、リース・レンタル業者が58%で、建設業者の17%よりも高い。また、建設機械施工技術者の技術力確保のため、「建設業法」に基づく建設機械施工技士の資格制度があり、21年度までに1級・2級合計約17万人が取得している。
建設業における死亡災害のうち、建設機械等によるものは約14%を占め、近年では建設機械の技術進歩により事故原因(注3)も変化している。このため、建設機械施工安全技術指針の改定、建設機械施工安全マニュアルの策定等を行い、建設機械施工の安全対策を推進している。
また、建設業の諸課題(低い生産性、熟練労働者不足、施工品質の確保等)の解決を目的として、ICTを活用した革新的な施工技術である情報化施工の普及促進を図るため、「情報化施工推進戦略」を20年7月に策定し、現在普及の課題となっている施工管理基準等の整備や設計データの標準化を行う等、受発注者間の環境整備に取り組んでいる。
(7)建設工事における紛争処理
建設工事の請負契約に関する紛争を迅速に処理するため、建設工事紛争審査会において紛争処理手続を行っている。申請実績は、中央建設工事紛争審査会では平成21年度に68件(仲裁11件、調停51件、あっせん6件)、都道府県建設工事紛争審査会では20年度に131件(仲裁21件、調停83件、あっせん27件)となっている。
(注1)建設業の事業協同組合:4,766組合、協同組合:38組合、企業組合:144組合
(注2)主な機種:油圧ショベル約682千台、車輪式トラクタショベル約159千台、ブルドーザ約53千台
(注3)建設機械の小型化(狭小現場に対応させた小型バックホウ等)による重心位置の変化や、補助装置(障害物検知装置等)の不適切な使用等による事故等