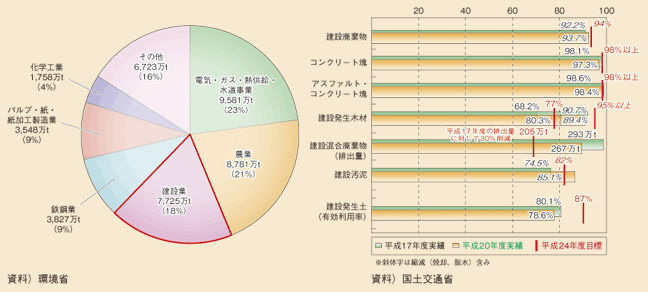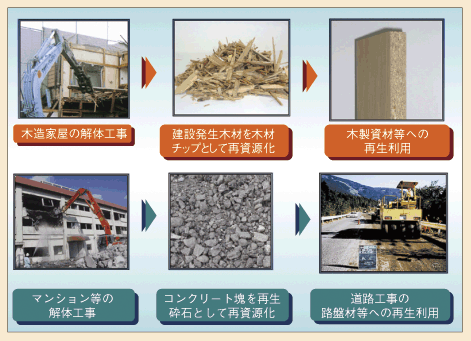第2節 循環型社会の形成促進
1 建設リサイクル等の推進
建設廃棄物は、全産業廃棄物排出量の約2割、最終処分量の約3割、不法投棄量の約8割を占め、その発生抑制、リサイクルの促進は重要な課題である。平成19年度の建設廃棄物の排出量は全国で7,700万トンである。20年度の再資源化等率は93.7%であり、17年度の92.2%と比較して向上しているものの、再資源化等率を高い水準で確保するため、引き続き取組みが必要である。
下水汚泥についても、産業廃棄物排出量の約2割を占め、19年度の排出量は約8,000万トンであり、その減量化、リサイクルの推進に取り組んでいる。
図表II-7-2-1 産業廃棄物の分野別排出量と建設副産物の品目別再資源化率等
(1)建設リサイクルの推進
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」の施行に当たって全国一斉パトロール等による法の適正な実施の確保に努めている。
また、平成20年12月に取りまとめられた「建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討について」を受け、22年2月に建設リサイクル法の省令及び施行規則の一部を改正し、事前届出書の様式変更と建築物に係る解体工事の工程順序の詳細化を行い、建設リサイクルの促進を図ることとしている。建設リサイクルを取り巻く課題として、再資源化率が低い品目があること、発生抑制やリサイクルの「質」の向上への取組みが不十分であること、依然として建設関係の不法投棄が多いこと等が挙げられる。そこで、関係者の意識向上と連携強化や他の環境政策との統合的展開を図り、民間主体の創造的取組みを軸とした建設リサイクル市場の育成を基本的考え方とする「建設リサイクル推進計画2008」を推進している。また、建設副産物の利用、排出、再資源化及び最終処分等の実態の把握をするために、20年に実施した建設副産物実態調査結果を取りまとめた。
図表II-7-2-2 建設リサイクルの取組み事例
(2)下水汚泥の減量化・リサイクルの推進
下水汚泥の緑農地利用やエネルギー利用等を推進(平成19年度リサイクル率77%)し、処理過程で発生するバイオガスのガス発電利用や天然ガス自動車の燃料化、下水汚泥の固形燃料化等によるエネルギー利用や、下水・下水汚泥からのリンの回収・活用を進めている。さらに、下水汚泥の利用をより促進するため、下水汚泥資源化・先端技術誘導プロジェクト(LOTUS Project)により開発された技術の普及を推進している。
(3)住宅・建築分野における廃棄物対策
建築系廃棄物である建設発生木材の再資源化等率は、縮減を含めて約9割程度となっており、1)地方公共団体等のリサイクルに関する取組みへの支援、2)住宅性能表示制度による劣化対策等に係る情報提供等により、住宅・建築物におけるリサイクル対策等を推進している。