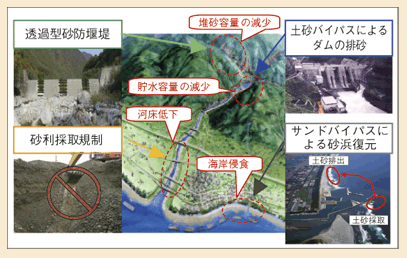2 豊かで美しい河川環境の形成
(1)良好な河川環境の保全・形成
1)多自然川づくり、自然再生の推進
河川整備にあたっては、多自然川づくりを基本とし、治水の安全性を確保しつつ、生物の生息・生育環境及び多様な河川景観の保全・創出に努めている。また、「魚がのぼりやすい川づくりの手引き」を活用し、全国の魚道整備等を推進している。さらに、多様な自然環境を有する本来の川の姿に戻すため、礫河原の復元や湿地の再生等を行う自然再生事業を釧路川、荒川等、全国37水系において推進している。
このほか、河川水辺の国勢調査及び世界最大級(延長約800m)の実験水路を有する自然共生研究センターでの取組み等、学識経験者や各種機関と連携して様々な調査・研究を行っている。
2)外来種対策の推進
生物多様性を保全する上で大きな脅威の1つである外来種は、全国の河川において生息域を拡大しており、生態系への影響等が問題となっている。この対策として、「河川における外来種対策の考え方とその事例」等を作成するとともに、各地で外来種対策を実施している。
(2)河川水量の回復のための取組み
良好な河川環境を保全するには、豊かな河川水量の確保が必要である。このため、河川整備基本方針等において動植物の生息・生育環境、景観、水質等を踏まえた必要流量を定め、この確保に努めているほか、水力発電所のダム等の下流の減水区間における清流回復の取組みを進めている。また、ダム下流の河川環境を保全・改善するため、洪水調節に支障を及ぼさない範囲で洪水調節容量の一部を有効に活用するダムの弾力的管理および弾力的管理試験を行っている(平成21年度は、全国の計16ダムで実施)。さらに、平常時の自然流量が減少した都市内河川では、下水処理場の処理水の送水などにより、河川流量の回復に取り組んでいる。
(3)山地から海岸までの総合的な土砂管理の取組みの推進
近年、土砂の流れの変化による河川環境の変化や海域への土砂供給の減少、沿岸漂砂の流れの変化等による海岸侵食等が気候変動により加速するおそれがあることから、山地から海岸まで一貫した総合的な土砂管理の取組みを関係機関が連携して推進している。具体的には、渓流、ダム、河川、海岸における土砂の流れに起因する問題に対応するため、関係機関との事業連携のための方針の策定を目指すなど連携の強化を進めている。