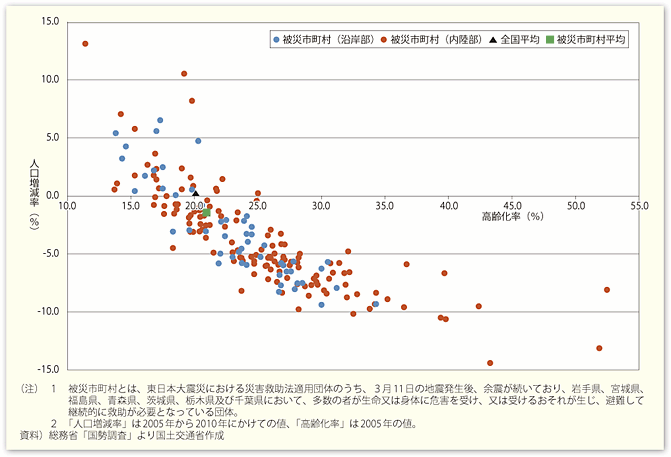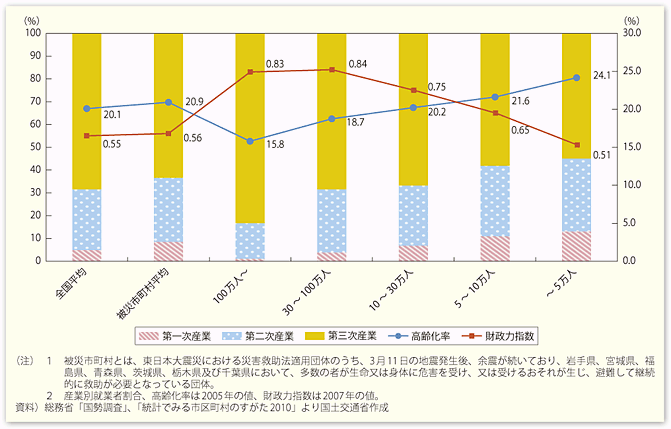5 被災地の復興に向けた課題
東日本大震災による広範囲にわたる被災地においては、大津波によるまちの壊滅的な被害、地盤沈下や海岸堤防等の損壊による二次的な災害の危険性、さらには原発事故の影響等から、一言で「被災地」とくくれない、様々に異なる状況が生じており、復旧・復興の取組状況も大きく異なっている。特に、原発事故の影響により長期にわたる避難生活を余儀なくされている地域においては、今も未曾有の複合災害が継続している状況にあることから、一日も早い原発事故の収束とふるさとへの帰郷が何よりも求められており、被災地の復興に向けた動きへの大きな障害に直面している。
一方で、震災から1ヶ月後の4月11日には、岩手県から「東日本大震災津波からの復興に向けた基本方針」が、宮城県から「宮城県震災復興基本方針(素案)〜宮城・東北・日本の絆・再生からさらなる発展へ〜」が、それぞれ発表された。また、福島県においても復興ビジョン・復興計画の策定に着手するなど、地域の実情に応じ、復興に向けた歩みも始まった。
同日には、政府においても東日本大震災復興構想会議が設置され、被災地の復興に向けた検討が進められるところとなった。
その後、被災地においては、岩手県において、「岩手県東日本大震災津波復興計画」として、「復興基本計画 〜いのちを守り 海と大地と共に生きる ふるさと岩手・三陸の創造に向けて〜」及び「復興実施計画(第1期)」が策定された。宮城県では、「宮城県震災復興計画 〜宮城・東北・日本の絆・再生からさらなる発展へ〜」の第1次案及び第2次案が公表され、9月を目途に復興計画が策定される予定となっている。福島県においても、「福島県復興ビジョン」が策定され、具体的な取組みや主要な事業を記載する「復興計画」の策定が進められている。
また、被災市町村においても、それぞれの実情に応じ状況は異なるものの、復興計画等の策定に向けた動きが進められている。
政府の東日本大震災復興構想会議においては、5月10日に「復興構想7原則」が発表され、6月25日には「復興への提言〜悲惨のなかの希望〜」が取りまとめられた。また、東日本大震災復興基本法の制定を受け、政府の東日本大震災復興対策本部が設置され、7月29日には「東日本大震災からの復興の基本方針」が策定された。
こうした検討とあわせ、国土交通省においても、応急対応、応急復旧から本格的な復旧・復興に向けて、被災地を支えていくための取組みについて検討を重ね、6月14日には、「国土交通省における東日本大震災の復旧・復興に向けた対応」を公表した注。この中では、1)被災者の生活再建と安定、2)新たな発想による復興まちづくり、3)地域産業・経済の再生とそれを支える都市・交通基盤、4)災害に強い国土構造への再構築といった4つの柱について、被災地が直面する課題に応じた施策を総合的に展開していく方針を示している。
これは、多くの被災地方自治体から、津波災害に強い安全なまちづくりのあり方やインフラの整備など、今後の復旧・復興の進め方について、国の考え方を早急に示してほしいとの要望も踏まえ、地域主体のまちづくりのビジョンづくりに資する復興まちづくりのあり方や、地域の産業や経済の再生を支える都市・交通インフラの復旧や整備等の方向性等について考え方を示したものである。
さらに、6月24日には、東日本大震災からの復興に関する国土交通省の施策の円滑かつ迅速な推進等を図るため、国土交通大臣を本部長とする国土交通省東日本大震災復興対策本部を設置し、政府全体の復興に向けた支援と一体となって取り組んでいくこととしている。
特に、今般の未曾有の津波災害の教訓を踏まえ、従来のハード対策のみでは大津波から守りきれない地域への対策が必要となっていることから、地域ごとの特性を踏まえ、ハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」による「津波防災まちづくり」を推進するための制度を創設することとしており、被災地の各県や市町村の復興ビジョンに向けた検討が本格化するのとあわせて、津波に強いまちづくりを推進するための制度的な枠組みを構築していくこととしている。
その一貫として、7月6日には、国土交通省社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会に設置されている計画部会において、「津波防災まちづくりの考え方」が緊急提言された。この中では、今回のような大規模な津波災害を想定して、なんとしても人命を守るという考え方で、新たな発想により、まちづくりと一体となって、ハード・ソフト施策を適切に組み合わせ、また、迅速かつ安全な避難の確保を図るなど、津波防災・減災についての考え方が整理されるとともに、具体的な検討課題として、国の役割、災害情報の共有や相互意思疎通、具体的な避難計画の策定、土地利用・建築構造規制、津波防災のための施設の整備、早期の復旧・復興を図るための制度、津波防災まちづくりを計画的、総合的に推進するための仕組み等について提言がなされた。
今後様々な復興に向けたビジョンや提言等の具体化により、一日も早い被災者の生活再建と被災地の復興を進めていくためには、国土交通省においても、まちづくりや産業復興、それらを支えるインフラ、交通、住宅等の分野で果たすべき役割は極めて大きい。様々な場で示されてきた課題とともに、被災地を取り巻く状況を踏まえつつ、被災地とともに取組みを進めていく。
(被災地を取り巻く社会経済状況)
今般の大震災の被災地域、特に、大津波により壊滅的な被害を受けた沿岸部の地域は、全国の地方部同様、深刻化する地域の疲弊に直面していた。被災地の中には、65歳以上の高齢者の人口比率が3割を超え、人口がこの5年間で5%以上も減少するような地域も多くみられる。こうした人口減少、少子高齢化といった地域社会の構造的な変化が進む中、地域に活力をもたらす人、モノ、資金が集まらない、循環しない、流出してしまう状況に、大震災の被害が追い打ちをかけてしまった。
被災市町村を人口規模別にみると、小規模な市町村ほど、農林水産業や製造業等の割合が高い一方で、高齢化率も高く、市町村の財政力指数が低い傾向となっている。
こうした被災地を取り巻く状況を踏まえると、被災地の復興を図る上では、新たな活力の再生・創出を目指した地域づくりを進めていく必要がある。そのためには、被災者の雇用が確保されることを最優先に、地域の特徴ある資源を再生・活用し、農林水産業やものづくり産業、観光業等の産業復興を果たせるよう、地域独自の復興戦略を支えていく必要がある。