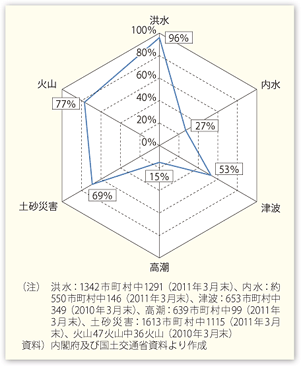第2章 災害に強い国土づくりに向けた課題
第1節 東日本大震災の教訓を活かした災害対策の総点検の必要性
(ハードとソフトの一体的取組み)
東日本大震災の悲惨な被害を前にして、改めて、「国土・地域の安全・安心なくして我が国の持続的な発展はない」ことが再認識された。国民生活、経済産業活動にとって、国土・地域の安全・安心は不可欠の条件である。
自然災害の発生を止めることはできない。自然条件の変化に伴う災害リスクの拡大や、高齢化等の社会環境の変化による新たな防災上の課題の拡大が懸念される中、財政制約が厳しい状況にあっても、様々な知恵と工夫により、事前の備えを進め、社会の災害に対する脆弱性を軽減することにより、災害被害を最小化する不断の取組みが求められる。
今回と同じような被害を繰り返さないためにも、今後様々な場で検証がなされる大震災の教訓を、災害に強い国土づくりに活かしていく必要がある。
1896年の明治三陸地震津波では、死者が2万人以上に達し、その後、1933年に再び昭和三陸地震津波が同じ地域を襲い、この時も死者・行方不明者がほぼ3,000人に達した。この2回の津波の間には、ほぼ40年の開きがあるが、2度目の災害の発生に当たり、地震後の津波の襲来に対する警戒心が人々の間に十分になく、このことが被害の増大を招いたことが知られている。また、昭和三陸地震津波以降も同様に、防波堤・防潮堤の整備、土地利用規制、高台への移転、避難体制等の様々なハード・ソフト施策が行われてきたが、施策によっては、長い時間の経過につれて、生活の不便等から、持続・徹底がなされてこなかったものもあった。このような例を考えるとき、防災で最も大切なことは、過去の災害から教訓を引き出し、それに対していかに継続的な対策を実施していくかということである。
これまでの巨大地震対策においては、東日本大震災が発生した日本海溝・千島海溝周辺の海溝型地震のほか、東海地震や東南海、南海地震、首都直下地震など、起こりうる地震や津波の姿を明らかにし、被害を想定した上で、被害を軽減する具体的な目標を設定し、その達成のための対策を進めてきた。
こうした地震防災戦略の手法自体の重要性に変わりはないものの、東日本大震災における大きな教訓の一つとして、こうした戦略の前提となる想定する災害の設定のあり方の検証にとどまらず、ハード対策のみでは自然の猛威を完全には抑えきれないことを前提に、ハード対策、ソフト対策の両面にわたり、自然災害の最大規模の外力に対して災害時の被害を最小化するため備えを準備しておく必要があることが挙げられる。
もとより、災害から命や暮らしを守る上で、ハード対策は重要な役割を占める。住宅や公共インフラの耐震性の向上や治水対策、海岸保全など、被害軽減に大きな効果を発揮する事業に重点をおいて、「選択と集中」の下、早急に進めるべきことはいうまでもない。
また、ソフト面でも、各種災害の監視・観測体制や災害・避難情報の迅速な伝達体制の充実・強化、地域が抱える災害リスクを共有化するためのハザードマップの整備・充実など、依然として改善、強化すべき課題は山積している注。
そうした取組みと合わせて、迅速かつ円滑な避難や救急救助、被災者支援、さらには被災地の復旧・復興も含めて、あらかじめきめ細かに、様々に生じうる事態に柔軟に対応できるような態勢や仕組みを整えておくことが重要である。
一朝一夕にできるものではないが、大震災の教訓を風化させることなく、息の長い継続した取組みを積み重ねていく必要がある。