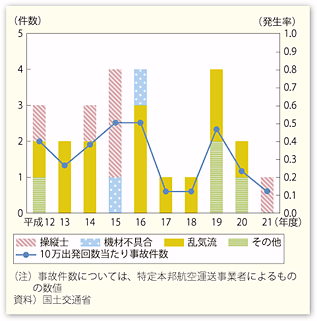4 航空交通における安全対策
航空事故や安全上のトラブル等の発生を未然に防止するため、規範遵守を監督する従来の安全行政から、各主体の安全パフォーマンス(指標)を継続的に評価し、航空全体として安全パフォーマンスの向上が図られるよう、総合的な安全マネジメントを行っていく次世代型安全行政への転換を図っている。
(1)航空の安全対策の強化
特定本邦航空運送事業者注において、乗客の死亡事故は昭和61年以降発生していないが、安全上のトラブルに適切に対応するため、航空会社に対し、安全管理体制の構築や安全上のトラブルの報告を義務付けているほか、専従組織により抜打ちを含む厳正な監査を実施している。平成22年度は、これらの義務付けを小規模航空運送事業者や整備事業者に拡大する制度改正を行うとともに、引き続き安全情報の一元管理、情報共有を図り、予防的安全対策を推進している。また、我が国に乗り入れる外国航空機に対して立入検査等による監視を強化するとともに、国産旅客機開発プロジェクトに対しても製造国政府として安全性の審査の適切かつ迅速な実施に努めている。
図表II-6-4-4 国内航空会社の事故件数及び発生率
(2)安全な航空交通のための航空保安システムの構築
安全性を確保しつつ、首都圏空港・空域の容量拡大による航空交通サービスの充実を図るため、羽田空港においては、平成22年10月より4本の井桁配置の滑走路を使用し、他の滑走路に離発着する航空機の間隙を縫って航空機の離発着を行う、これまでと全く異なる運用方式を導入しており、今後は44.7万回の年間発着容量の実現に向け、D滑走路供用後の新たな運用方式の慣熟を着実に進める。
また、成田空港においても30万回の年間発着容量の実現に向け、現行の2本の滑走路を前提としつつ、騒音影響区域を広げずに発着能力を拡大するため、世界的にも例が少なく、我が国では初となる同時平行離着陸方式を導入するなど、新たな運用方式の導入・慣熟を進める。
さらに、管制指示に対するパイロットの復唱のルール化等管制官とパイロットのコミュニケーションの齟齬の防止や管制官とパイロットに対する視覚的な表示・伝達システムの整備等のヒューマンエラー対策を推進する。
注 客席数が100又は最大離陸重量が5万キログラムを超える航空機を使用して航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者のこと