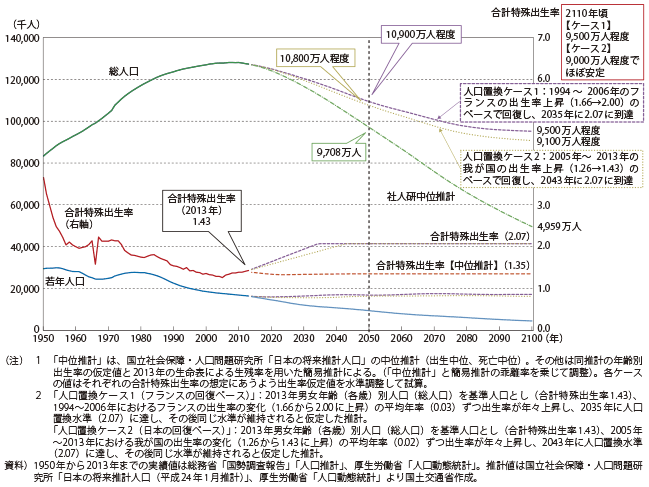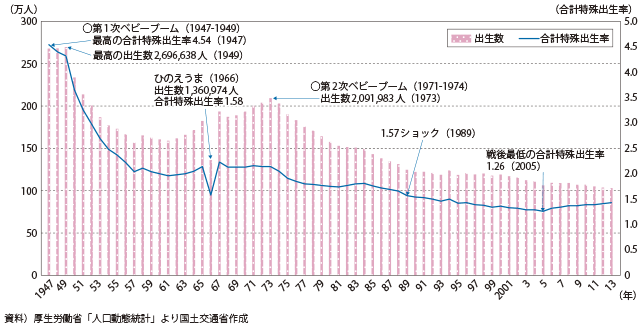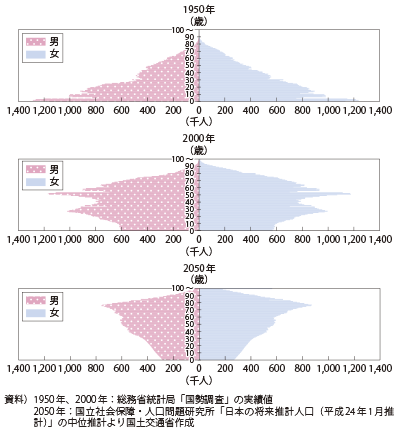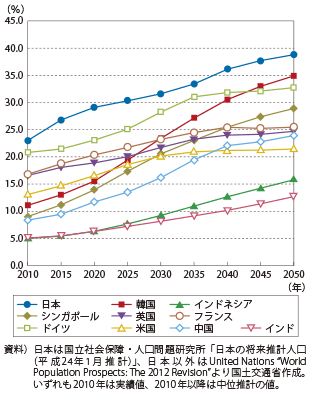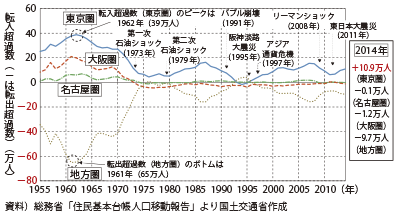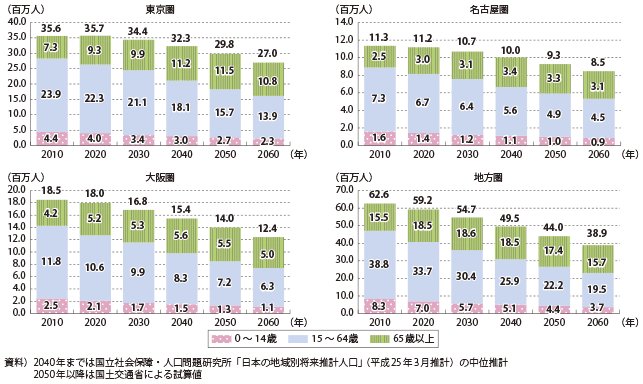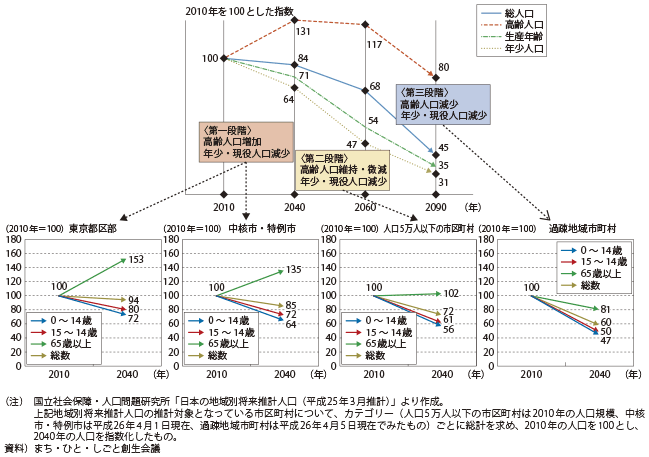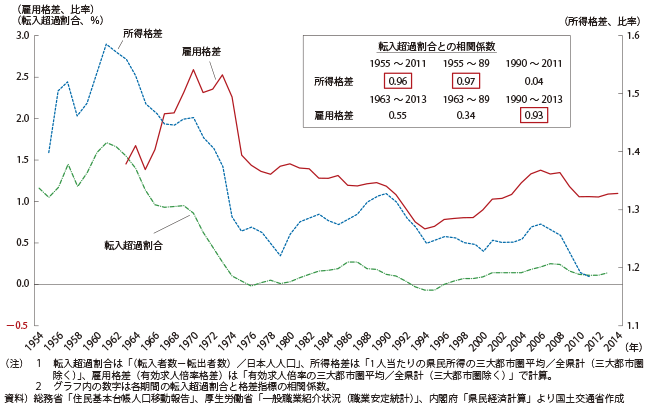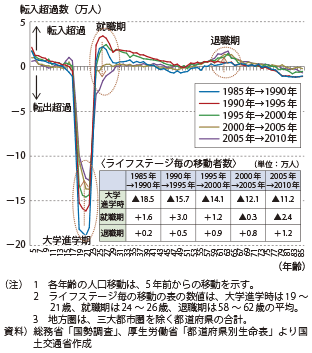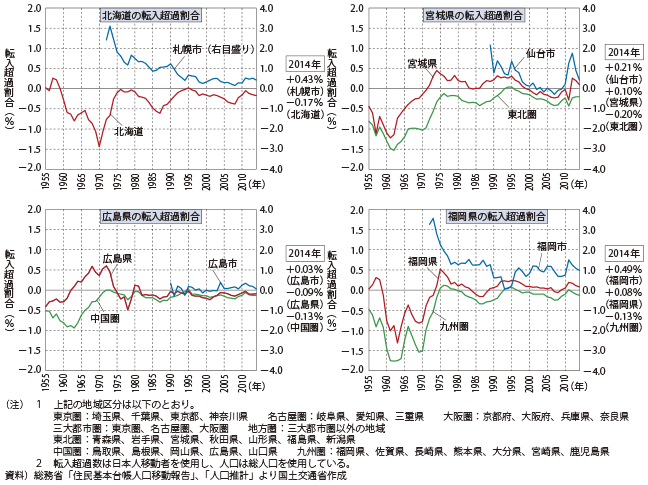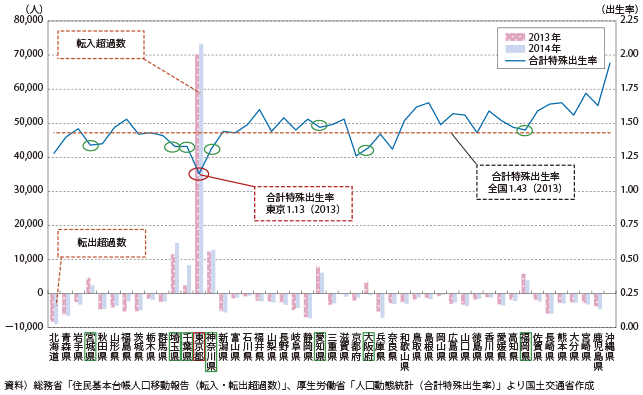■1 我が国の人口動向及び人口推計
(1)将来推計人口の動向
(我が国の人口動向)
我が国の総人口は、戦後の第1次ベビーブーム(1947〜1949年)や第2次ベビーブーム(1971〜1974年)等を経て、一貫して人口増加傾向であったが、人口のピークである2008年に1億2,808万人に達した以降は、減少傾向にある。
国立社会保障・人口問題研究所(以下「社人研」という。)が公表した「日本の将来推計人口」によると、合計特殊出生率注1(以下、本節の本文中では単に「出生率」という。)が1.35程度で推移した場合を想定した中位推計では、2050年の人口は1億人を割り込み、2100年にはその半分の5千万人を割り込むまで減少すると推計されている(図表1-1-1)。
図表1-1-1 我が国の人口推移
仮に、今後20年程度で、人口置換水準である出生率2.07まで回復した場合「人口置換ケース1(フランスの回復ペース)」では、人口減少のペースは緩やかになり、総人口は2110年頃から9,500万人程度で安定的に推移することとなる。出生率を大幅に回復させるのは容易なことではないが、若い世代の結婚・子育ての希望の実現に取組み、出生率の向上を図ることが重要である注2。
(出生数と合計特殊出生率)
出生率は、戦後の第1次ベビーブーム期の1947年に4.54となり、出生数では、1949年に約270万人となるなど、ベビーブーム期の3年間において、出生数・出生率共に最高となった(図表1-1-2)。
図表1-1-2 出生数及び合計特殊出生率の推移
その後、第2次ベビーブームの1973年に出生数約209万人と高い数値を記録してからは、出生数・出生率共におおむね右肩下がりの減少傾向となっている。
1989年には、出生率が1966年の丙午(ひのえうま)注3の年に記録した1.58を下回り、社会的な反響の大きさから「1.57ショック」と呼ばれた。
2005年には、戦後最低の出生率1.26を記録し、その後は微増傾向ではあるものの、出生数では2011年以降3年連続で過去最低を記録し、2013年には過去最低の約103万人となった。
次に、いわゆる「人口ピラミッド」で年齢層の推移を50年ごとで比較する(図表1-1-3)。
図表1-1-3 我が国の「人口ピラミッド」の推移(1950年、2000年、2050年)
1950年では、いわゆる団塊の世代を筆頭に若年層が圧倒的に多かったため、グラフの形状は「富士山型」となっている。2000年では、いわゆる団塊の世代と団塊ジュニア世代が総人口を牽引しているものの、20〜30歳代以下の世代が急減しているため、グラフの形状は「釣鐘型」となっている。社人研の中位推計に従った2050年の図では、より一層人口減少が進行するため「つぼ型」になるとされている。
「人口ピラミッド」とはいうものの、近年ではピラミッドの形状をなしておらず、今後もピラミッドの下部となる若年層の部分が先細ることが予想される。
(諸外国との高齢化率比較)
我が国は高齢化社会と言われて久しいが、諸外国との高齢化率注4を比較した場合、どのように推移するだろうか(図表1-1-4)。
図表1-1-4 諸外国における高齢化率の推移
高齢化率を見ると、諸外国全体で上昇することとなるが、我が国においては、諸外国に比べ、群を抜いて高いことがわかる。
2010年の時点で、既に高齢化率は20%を超えており、我が国の5人に1人は高齢者という状況である。また、社人研が作成した中位推計によれば、2013年の高齢化率は25.1%となり、我が国の4人に1人が高齢者になっていると推計されている。さらに、2025年には、我が国全体で高齢化率が30%を越え、2050年には40%弱にまで届くと推計されており、我が国は今後一層高齢化社会へと進行する見込みとなっており、世界の主要国が経験したことのない社会を迎えようとしている。
(2)都市圏と地方圏の人口移動の推移
(三大都市圏と地方圏の人口移動推移)
戦後、我が国の人口増加とともに、1950〜70年代の高度経済成長期には、地方圏注5で生まれ育った若者が就職や進学のために三大都市圏へ移動したこと等により、三大都市圏での急激な人口増加が生じた。地方圏からの人口移動により、三大都市圏では住宅の供給が追いつかず、郊外の大規模ニュータウンの開発等が盛んとなったが、1970年代半ばから名古屋圏と大阪圏の転入超過数は、ほぼ横ばいとなっている(図表1-1-5)。
図表1-1-5 三大都市圏と地方圏の転入超過数(転入者数−転出者数)の推移
1980年代半ばのいわゆるバブル経済により東京圏への転入超過数が増加したが、都心部の地価が高騰したことから、郊外に住居を求め中心市街地が空洞化するドーナツ化現象が発生した。
バブル経済が崩壊した1990年代前半には、東京圏への人口移動は一時減少したが、1990年代半ばには、地価の下落や住宅ローン金利の低下等を受け、以前に比べ住宅が入手しやすい価格帯になったこと等の要因もあり、再び東京圏への人口移動が増加した。
2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災の影響による一時的な転入超過数の下落傾向はあるものの、近年では東京圏へ人口移動が再び集中する傾向が強まっている。
(地域ごとの将来推計人口の動向)
人口動向は地方圏と三大都市圏で異なる性質を持っている。
三大都市圏と地方圏別の将来推計人口の中位推計での動向を年齢別(0-14歳、15-64歳、65歳以上)でみると、2010年から2060年までの間に、すべての地域において人口減少や高齢化が進むことがわかる(図表1-1-6)。
図表1-1-6 地域ごとの将来推計人口の動向
高齢者の実数を地域別に見ると、地方圏では2030年に1,860万人とピークになり、その後は減少傾向となる。しかし、東京圏では、2040年に1,120万人、2050年に1,150万人とピークとなり、2060年には減少するものの、1千万人以上が高齢者である。
以上のように、三大都市圏と地方圏では高齢者数が増加する時期が異なることがわかる。
(都市と地方との人口減少の時間差)
人口減少は、大きく分けると下記の三段階を経て進行することとなる。
「第一段階」:若年人口は減少するが、老年人口は増加(2010〜2040年)
「第二段階」:若年人口の減少が加速化、老年人口が維持から微減(2040〜2060年)
「第三段階」:若年人口の減少が一層加速化、老年人口も減少(2060年以降)
2010年を100として各年の推計値を指数化したのが下図である(図表1-1-7)。
図表1-1-7 地域によって異なる将来人口動向
現在では、東京都区部や中核市等の都市部は「第一段階」の状況で、生産年齢人口と年少人口は既に減少しているが、今後2040年まで高齢者が増加する予測である。しかし、地方の小都市や過疎地域では、「第二・三段階」に突入しており、生産年齢・年少人口のみならず高齢者も既に維持又は減少している状況である。
つまりは、地方のみが衰退するのではなく、まず地方から先んじて衰退していき、その後、地方から大都市への人材供給が枯渇して、大都市部も衰退し、ついには我が国全体が衰退していくことになると考えられる。
(人口移動に伴う所得格差と雇用格差)
地方圏から三大都市圏に人口が移動する要因については、所得と雇用が大きく関連している。
三大都市圏について、転入超過割合と所得格差、雇用格差の関係をみると、1990年以前は所得格差との相関が高く、所得格差が高まると転入超過割合が増加していたことがわかる(図表1-1-8)。
図表1-1-8 三大都市圏への人口移動と所得格差・有効求人倍率格差
逆に、1990年代以降は、雇用格差との相関が高くなり、有効求人倍率が相対的に高まることにより、転入超過割合が増加していること等から、都市と地方との間での人口移動には、経済的要因が深く作用してきたことがわかる。
(地方圏における年齢別人口移動の状況)
地方圏においては、ライフステージの変化と人口の移動に関連性がある(図表1-1-9)。
図表1-1-9 地方圏における年齢別人口移動の状況
第一の大きな移動時期は、大学進学期の人口流出である。1985→1990年代では、18.5万人の人口流出があったが、年々減少し、2005→2010年代では11.2万人となり、全盛期の6割程度と大幅に減少している。
また、かつては地方から移動した者が、就職期に地方へ戻ることが多かったため、転入超過に転じていたが、2000年以降では、地方から移動した者が、就職期に都市にそのまま残ることが増え、転出超過となる傾向が見られる。
一方で、退職期を見ると、地方圏への人口流入が1985→1990年代から2005→2010年代の間で1万人程度増加しており、近年では退職期における地方回帰の動きが見られる。
(地方ブロック内の人口移動)
地方ブロック内での人口移動について、地方中枢都市が存在する4つのブロック(「北海道(札幌市)」、「東北圏:宮城県(仙台市)」、「中国圏:広島県(広島市)」及び「九州圏:福岡県(福岡市)」)での比較を下図に示す(図表1-1-10)。
図表1-1-10 地方中枢都市が存在する県・ブロックにおける人口移動
1955年から2014年までの人口移動をみると、各中枢都市では、総じて転入超過の傾向となっているが、各ブロックでは、転出超過傾向が見られる。
(都道府県別転入・転出と出生率)
2013年と2014年の都道府県別の転入・転出超過数(棒グラフ:左軸)を見ると、東京都の転入超過が極端に多くなっており、東京一極集中の状況が一目瞭然である(図表1-1-11)。
図表1-1-11 都道府県別の転入・転出超過数と合計特殊出生率の比較
東京都のほか、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府(2013年のみ)及び福岡県といった大都市で転入超過になっており、その他の地域は転出超過となっている。特に2014年に大阪府では転出超過となった上、東京圏以外の県でも転入超過数が減っており、足下では更に東京一極集中が進んでいることがうかがえる。
2013年の出生率(折れ線グラフ:右軸)を見ると、東京都で極端に低くなっており、転入超過となっている他の府県の出生率も総じて低い傾向にある。
以上のことから、我が国の人口は、戦後の経済成長の要因等により、若年層を中心に、地方圏から所得や雇用条件の良い東京圏へ吸い寄せられ、社会経済情勢等による多少の波はあるものの、依然として東京一極集中は続いている傾向にあると言える。
人口減少のペースを緩めるためには、東京一極集中を是正し、出生率が比較的高い地方圏への人の移動を促進することが重要となると考えられる。
注1 合計特殊出生率とは、その年次の15〜49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が、仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子どもを生むと仮定したときの子ども数に相当する(
図表1-1-25)。
注2 「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」(2014年12月)によれば、結婚や出産はあくまで個人の自由な決定に基づくものであることを前提としつつ、「若い世代の結婚・子育ての希望が実現するならば、我が国の出生率は1.8程度の水準まで向上することが見込まれる」とされている。
注3 丙午(ひのえうま)とは、干支の1つで、60年に1回まわってくる。ひのえうまの年に生まれた女性は気性が激しいという迷信から、この年に出産する事を避けた夫婦が多いと考えられている。
注4 総人口に占める高齢人口(65歳以上)の割合。
注5 地域区分は以下のとおり。
東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 名古屋圏:岐阜県、愛知県、三重県 大阪圏:京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 三大都市圏:東京圏、名古屋圏、大阪圏 地方圏:三大都市圏以外の地域