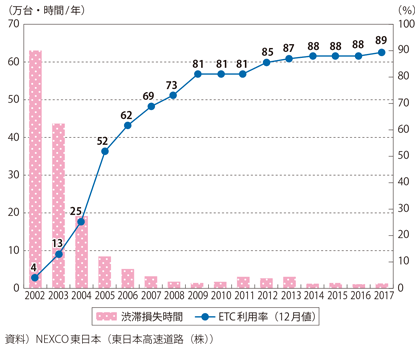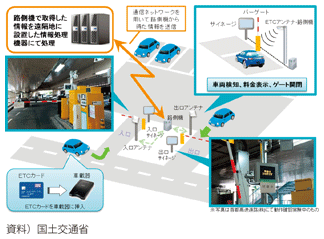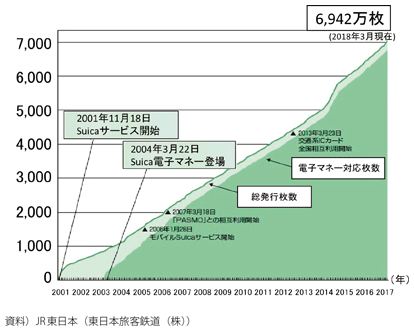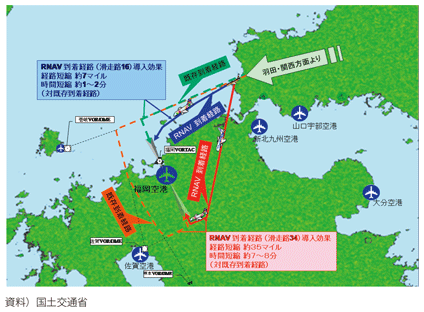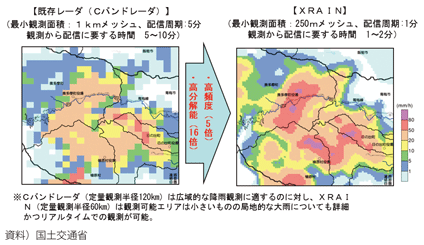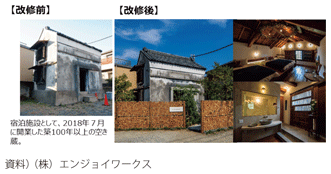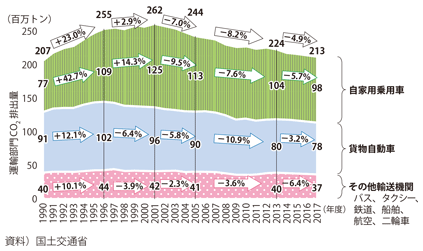■1 情報通信技術(ICT)・省エネルギー化等による変化
(情報通信技術(ICT)の進展による変化)
■ETCの導入と拡大
有料道路の料金所を止まらずに通過できるETC(Electronic Toll Collection System)は、平成に入り、非接触でデータを送受信できる技術が発展するなどのICTの進展に伴い、技術的に導入が可能となった。ETCは、2001年(平成13年)には、高速道路において一般に向けたサービスとして開始された。その後、国・道路事業者等による普及活動もあり、その利用率は上昇し、現在では、料金所を通過する自動車の、およそ9割がETCを利用している。ETCの利用率が上昇するとともに、高速道路の料金所における渋滞による待ち時間は減少していき、高速道路の利便性は高まっている(図表I-2-1-1)。
図表I-2-1-1 ETC利用率と渋滞損失時間の推移
2015年からは「ETC2.0」として、従来の料金収受機能に加え、高速道路等に設置された路側機(通信アンテナ)とETC2.0車載器との間で双方向通信を行うことにより渋滞情報、安全運転支援情報、災害時支援情報等の情報提供を行うとともに、路側機から収集された走行履歴・挙動情報(プローブ情報)を活用したサービスの導入や民間サービスの充実を推進している。
また、ETC2.0データを官民連携で活用することで、民間での新たなサービスの創出を促し、地域のモビリティサービスを強化することとしている。さらに、高速道路料金以外の利用料金へのETCの活用について検討を進めており、2017年度より順次、ネットワーク型ETC技術注1を活用した試行運用を自動車駐車場、フェリー乗り場等で行い、技術面・運用面の検証を行っている(図表I-2-1-2)。
図表I-2-1-2 駐車場におけるETC技術の活用例
■ICカードの普及
1996年(平成8年)にソニー(株)によって開発された非接触ICカード「Felica」の技術は、2001年にJR東日本のIC乗車券「Suica」に採用されたのをはじめとして、各地の交通機関でも乗車券に採用され、この結果、多くの人が非接触ICカードを利用するようになった。それ以来、交通系ICカードの発行枚数は拡大を続けており、その利用が広がっていることがわかる(図表I-2-1-3)。
図表I-2-1-3 Suica発行枚数の推移
2013年には、全国10種類の交通系ICカードを相互に利用することができるサービスが開始され、1枚のICカードによって利用できる範囲が大幅に拡大した。しかし、交通系ICカードが未導入、あるいはその相互利用ができない地域は、地方部を中心に依然として存在している。このような状況を踏まえて、2015年に作られた「交通政策基本計画」では、2020年度までにSuica、PASMO等の既に相互利用が可能な交通系ICカードについて、すべての都道府県の交通機関において使えるようにするという目標を定めた。
また、乗車券に非接触型ICカードを用いるシステムは、2019年3月に開業したインドネシアのジャカルタ都市高速鉄道でも採用されるなど、海外においても我が国の技術が円滑な旅客輸送に貢献している。
■航空機の新たな航行方法(RNAV)の導入
ICTの発展に伴い、航空機の航行ルート等を決めるコンピューターなどの能力が向上した。このような中、2005年(平成17年)頃には、新たな航行の方法であるRNAV注2が導入された。従来、航空機は地上施設(VOR/DME注3等)からの情報(電波)を受けて、飛行経路を決めており、目的地までの最短ルートではなく、地上施設を結ぶ経路によってしか航行することができなかった。新たな航法では、GPS情報等も活用することにより、地上施設の位置に左右されることのない柔軟な経路設定が可能となった(図表I-2-1-4)。
図表I-2-1-4 従来の航法とRNAV航法の比較
この結果、効率的な飛行経路が設定できるようになり、目的地までの飛行時間や距離が短縮され、CO2の排出量も削減できるようになった(図表I-2-1-5)。
図表I-2-1-5 RNAV経路の一例(福岡空港到着経路)
■気象レーダーの発展
平成における通信技術の進歩や計算処理能力の向上を受け、気象レーダーによる雨量の観測精度も大幅に向上した。2007年(平成19年)には、レーダーと地上の雨量計を活用することにより、それまで3kmメッシュであった雨量情報を1kmメッシュに高解像度化し、局地的な天気予報の監視能力が高まった。また、この情報は河川の水位などを観測する「統一河川情報システム」などにも活用され、河川の防災機能の向上等にも貢献した。
しかし、2008年の兵庫県神戸市の都賀川(とががわ)における水害など、従来のレーダーでは、捉えきれない局地的な大雨や集中豪雨が頻発するようになった。このような中、2010年からは従来のレーダーよりも高精度なレーダー注4を用いることにより、これまでの5分間隔から1分間隔で雨量情報を把握することができるようになった。さらに、2016年からは、従来のレーダーと高精度なレーダーの双方を活用することにより、雨量情報を250mメッシュかつ1分間隔でとらえられるまでに至っている。(図表I-2-1-6)。
図表I-2-1-6 雨量レーダーの変遷
■不動産投資市場におけるクラウドファンディングの活用
平成におけるICT等の進展により、不特定多数の人がインターネットを経由して他の人々や組織に財源の提供や協力などを行う「クラウドファンディング」という手法が広がっている。クラウドファンディングは、「共感」に基づいて少額であってもその事業を応援したいという気持ちを持った多くの人々から直接的に出資を受けることができるという特徴を有しており、新たな資金調達手段として注目されている。実際、その市場規模は、2013年から2017年までの5年間で約8倍となっている。
このような中、不動産特定共同事業については、書面による取引を前提とし、多額の資本金を必要とする許可要件等があり、クラウドファンディングを活用することが困難であった。これを受け、2017年6月には、不動産特定共同事業法の改正を行い、電子取引への対応や小規模事業者の参入促進のための制度改正を行った。
この結果、クラウドファンディングにより空き蔵が宿泊施設として改装される例も生まれており、今後、さらにこのような取組みが広がることが期待される(図表I-2-1-7)。
図表I-2-1-7 不動産クラウドファンディングを活用した空き家等の再生・活用事業の例
(省エネルギー化・環境対策の進展)
■排出ガス対策(運輸部門)
2017年度(平成29年度)における日本全体の二酸化炭素排出量のうち、運輸部門からの排出量は17.9%を占めている。その中でも、自動車の占める割合は大きく、運輸部門の86.2%であり、日本全体の15.4%に達している。運輸部門における二酸化炭素排出量についてみると、1990年度から1996年度までの間に、23.0%増加したが、その後、ほぼ横ばいとなり、2001年度以降は減少傾向に転じている(図表I-2-1-8)。
図表I-2-1-8 運輸部門における二酸化炭素排出量の推移
自動車分野では、燃費基準について、1998年には、ガソリン乗用車等について、最も品質の高い車体の能力を規制基準とする「トップランナー基準」を採用し、2010年度、2015年度及び2020年度までに達成すべき目標を設定してきた。次世代自動車の急速な普及(図表I-2-1-9)などにより、2013年度には2020年度の目標を達成するなど、燃費改善の大幅な進展が見られてきた。また、次期燃費基準について、国土交通省と経済産業省の合同会議において、平成30年3月から検討を開始した。
図表I-2-1-9 ハイブリッド車の保有台数

航空分野では、航空機の排出ガス対策、エコエアポートやバイオジェット燃料の促進などの環境負荷低減に向けた取組みを進めている。また、国際民間航空機関(ICAO)において、国際航空全体で、2020年のCO2排出量を上限とするなどの目標達成を目指した取組みが進められている。
港湾における環境対策としては、船舶・荷役機械・トレーラー等の輸送機械の低炭素化や陸上給電設備の導入等を実施している。また、船舶における温室効果ガス(GHG)対策としては、2018年に国際海事機関(IMO)において、2030年までに国際海運全体の燃費効率を40%改善し、今世紀中にはGHG排出ゼロを目指している。また、排気ガス中の硫黄酸化物(SOx)については、国際的な規制(SOx規制)において、2020年1月以降、規制値が3.50%以下から0.50%以下に強化されることが決まっている。
鉄道分野については、自動車等からシフトが進めば交通分野全体の環境負荷軽減が進むことから、鉄道の利用促進や貨物鉄道輸送へのモーダルシフトの推進に向けた取組みを進めてきた。また、鉄道の更なる環境負荷の低減を図るため、エネルギー効率の良いハイブリッド車両の導入等も促進している。
■建設施工現場の省エネルギー化
国土交通省は、建設施工現場においても省エネルギー化の推進や低炭素型社会の構築に取り組んできている。
まず、2003年(平成15年)には、現場の管理者や建設機械のオペレータ等に対して、燃料の消費を抑えるための運転方法などをまとめた「省エネ運転マニュアル」を作成し、啓発を図ってきた。また、2010年からは、先進技術の導入により省エネ化が進んでいる建設機械の普及のため、「低炭素型建設機械認定制度」を創設し、支援を行うことにより、普及を促進してきた(図表I-2-1-10)。さらに、2013年には、世界で初めて、建設機械の燃費について、測定方法や目標値を定め、建設機械を使用するユーザーが、統一的な基準に基づいて、省エネの効果等を把握できるようにした。目標値の設定にあたっては、最も燃費の効率性が高い機械の性能を全体の基準とする「トップランナー基準」を採用するとともに、2020年を目標年として設定した。既に目標値に到達している主要3機種(油圧ショベル、ホイールローダー、ブルドーザ)の燃費改善率は、1990年と比較すると、平均約20%にもなっている。
図表I-2-1-10 環境負荷の低い建設機械
■下水道資源の活用
下水の汚泥は、従来、廃棄物として埋立てなどで処分されてきたが、近年の技術の進歩等により、燃料肥料など多様な資源として活用することが可能となってきている。
例えば、現在、下水の汚泥は約3割しか燃料(バイオマス)として利用されていないが、すべての汚泥を活用することができれば、約110万世帯の電力をまかなうことができる。また、下水処理場に流入する「リン」について、農業においてすべて利用することができれば、現在、海外から輸入しているリンの約10%(約120億円/年)を削減することができる。
国土交通省では、2013年(平成25年)8月より、下水道資源を農作物の栽培等に有効利用する取組みを推進している(「BISTRO下水道」)。2018年4月には下水道資源を農業利用した事例集を作成・公表しているところである(図表I-2-1-11)。
図表I-2-1-11 佐賀市の事例(汚泥由来肥料を利用した農作物の販売の様子)
注1 ネットワーク型ETC技術とは、遠隔地に設置したセキュリティ機能を有した情報処理機器と駐車場等における複数の路側機を通信ネットワークで接続し、ETCカードを用いた決済の安全性を確保する技術
注2 RNAV航行とは、航空機が搭載する高機能なFMS(航法用機上コンピューター)等により、自機の位置を算出し任意の経路を飛行する航法であり、地上施設(VOR/DME等)の配置に左右されることのない柔軟な経路設定が可能な運航方式。
注3 VOR/DMEとは、地上から電波を発射し、航空機に方位及び距離の情報を同時に提供するための施設。
注4 XバンドMPレーダー。波長が短い周波数帯を用いて観測を行うレーダーであり、雨粒の形状や動き等のより詳細な観測が可能である。