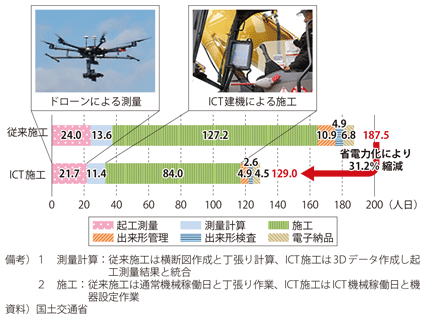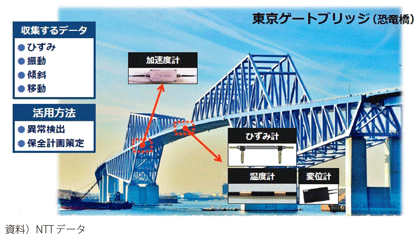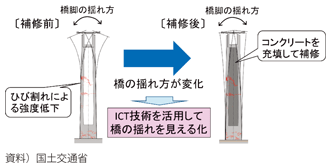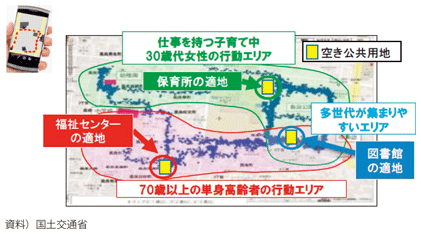■2 超スマート社会(Society 5.0)につながる新技術による変化
■i-Constructionによる生産性向上
建設業において、現在の技能労働者は、約340万人であるが、今後、10年間で約110万人が高齢化などにより離職することが見込まれている。このような中、国土交通省では、調査・測量から設計、施工等の全ての建設生産プロセスにおいてICTを活用する「i-Construction」を推進し、建設現場の生産性を2025年度までに2割向上させることを目指している。具体的には測量作業を効率化するためのドローンの導入、3次元設計データを活用したICT建設機械による施工といった取組みを推進している。また、産学官連携のコンソーシアム等を設置し、技術開発や現場への導入促進などに取り組んでいる(図表I-2-1-12)。
図表I-2-1-12 ICT土工の活用効果(作業時間の削減)
■インフラの維持管理におけるビッグデータの活用
我が国では、高度成長期以降に整備したインフラが今後一斉に老朽化することが見込まれる。例えば、道路橋では、15年後には、建設後50年以上経過する施設の割合が60%を超える。このように老朽化が進むインフラの計画的な維持管理・更新が求められている。
計画的な維持管理・更新をする上で重要なことは、インフラの損傷が軽微な段階で補修をして、施設の機能を保つことでインフラを長寿命化させる「予防保全」の取組みである。これに加え、維持管理に関して蓄積した膨大なデータや新技術を積極的に活用することで、維持管理に係るトータルコストの縮減・平準化を図ることも重要である。
特に、データ活用については、維持管理情報を蓄積・分析することで、効率的な維持管理に繋げる取組みが進められている。
例えば、2012年(平成24年)に建設された東京ゲートブリッジでは、橋梁に50個以上のセンサーを取り付け、ひずみや振動、変位など1秒あたり数千のデータを測定・分析しており、リアルタイムで異常の検知をおこなっている。蓄積したデータは、今後、経年劣化の予測等に活用し、更なるインフラ維持管理の高度化を図る(図表I-2-1-13)。
図表I-2-1-13 東京ゲートブリッジ
2016年度に熊本地震により被災した阿蘇長陽大橋の復旧工事に際しては、高性能加速度計により、橋の揺れ方を計測し、補修前後の変化を「見える化」するなど、ICT技術を活用して補修効果を確認し、効率的な維持管理に役立てている。また、そのデータから得られる知見を他の橋にも応用し、インフラの維持管理の高度化を図っている(図表I-2-1-14)。
図表I-2-1-14 橋の揺れ方の見える化
今後とも、予防保全の取組みとともに、データや新技術の活用により、持続的・実効的なインフラメンテナンスを推進する。
■スマート・プランニング
従来の都市計画では、公共施設等の立地を検討する際に、人口分布や施設の立地状況等から、概ねの位置を決定していた。
このような中、昨今のビッグデータの増大を受け、国土交通省では、より効果的・効率的な都市計画を行うため、人の属性ごとの「行動データ」を基に、利用者の利便性、事業者の事業活動を同時に最適化する施設立地を可能とする「スマート・プランニング」を推進している。この手法では、例えば、施設の立地を決定する際、ビッグデータを活用して、個人の移動特性を把握するとともに、施設配置や道路空間の配分を変えたときの「歩行距離」や「立ち寄り箇所数」、「滞在時間」の変化を検討することになる(図表I-2-1-15)。
図表I-2-1-15 スマート・プランニング
また、スマート・プランニングを用いることで、行政や民間事業者が、データに裏付けられた現状の姿などを共有した上で、最適な施設立地について議論することが可能となる。さらに、ワークショップなどの市民への説明の場においても、複数の立地案を定量的に比較した説明が可能となり、取組みの成果の「見える化」や効果検証、継続的なモニタリングの促進が期待される。
■ビッグデータを利用した交通安全対策
主要先進7ヶ国中、日本は、自動車乗車中の安全性は最も高い一方、歩行中・自転車乗車中の安全性は最下位であり、歩行者・自転車利用者に対する安全対策は十分と言える状況にはなかった。また、交通事故の約半数は自宅から500m以内で発生しているとともに、生活道路の事故件数の減少率は、幹線道路と比較して小さいなど、生活道路における安全対策がさらに求められている。
このような状況に際して、ビッグデータを活用することにより、生活道路において、従来行われてきた事故発生箇所への対策のみならず、潜在的な危険箇所への対策も可能となった。なお、潜在的な危険箇所の特定に当たっては、速度超過、急ブレーキ発生など車の運行データ等を用いている。
この取組みは、2017年(平成29年)度から開始され、現在、全国で907エリア(417市町村)にまで広がっている注5。一例として、新潟県新潟市の生活道路においては、規制速度の超過や急ブレーキの発生状況等を分析し、自動昇降するポール(ライジングボラード注6)を設置することなどにより、速度超過の割合が約45%減少するという効果が生まれ、その安全性が高まっている(図表I-2-1-16)。
図表I-2-1-16 ビッグデータを活用した生活道路対策
■データの利活用の推進
国土交通省では、様々なデータをオープン化するとともに、その利活用を促進することによって、生産性の向上や新ビジネスの創出に資する取組みを支援している。
1)気象データ
国土交通省では、気象データの高度化・オープン化を進めることで、気象ビジネスの創出を促進している。
2018年(平成30年)6月には、降水量の予報について、従来は6時間先であったものが15時間先まで公表することが可能となり、2019年6月には、気温の予報について、従来は1週間先であったものが2週間先まで公表することが可能となるなど、基礎的な気象データの更なる高度化・オープン化を進めている。
また、2017年3月には、気象、IoT、AI等の専門家や幅広い産業分野の企業、気象事業者等から構成される「気象ビジネス推進コンソーシアム」を設置した。産業界と気象サービスがマッチングできる場、気象データ利用のためのスキルアップができる場等を提供し、IoT・AI技術とともに気象データを利用した産業活動を創出・活性化すること等を目的としている。
現在においても、気象データは、荷物量、漁場の選定、商品の需要予測など様々な分野において利用されてきており、今後、更なる広がりが期待される(図表I-2-1-17)。
図表I-2-1-17 ロードヒーティング遠隔監視サービス向け気象予測データの活用
2)地理空間情報(位置情報)
国土交通省では、「誰もが・いつでも・どこでも」必要な地理空間情報(位置情報)を活用できる社会の実現のため、様々な取組みを進めている。2007年(平成19年)の「地理空間情報活用推進基本法」の制定を踏まえ、電子地図上の位置の基準である基盤地図情報の整備を開始するなど、様々なデータの整備を進めるとともに、2016年には、これまで産学官の様々な主体が収集していた地理空間情報を集約・加工して、誰もが使いやすい形のオープンデータとして提供する「G空間情報センター」を立ち上げている。2018年には日本版GPSである準天頂衛星「みちびき」の4機体制でのサービスが開始され、位置を測定する際の誤差が数センチメートルという高精度の測位が可能となることにより、自動運転や無人航空機物流など、第四次産業革命・Society 5.0を牽引するような新たな産業・サービスの社会実装が期待される(図表I-2-1-18)。
図表I-2-1-18 地理空間情報の活用イメージ
地方自治体における取組みとしては、熊本県上天草市において、約8km離れた本土と離島間において人の操作を必要としない完全自律飛行のドローンを用い、「みちびき」からの位置情報を活用しつつ、物資を輸送するという実証実験を行い、成功している(図表I-2-1-19)。
図表I-2-1-19 上天草市における実証実験
このような中、2020年(令和2年)に開催される「東京オリンピック・パラリンピック競技大会」を契機に、衛星の信号が届かない屋内においても正確な位置情報を提供するサービスの創出の促進を目指している。訪日外国人が多く利用する東京駅周辺や新横浜国際競技場などにおいては、屋内の電子地図を作成してオープンデータとして公開するなど、イノベーションの源泉としての地理空間情報の活用事例を世界に向けたショーケースとして発信している。
3)海洋情報
2018年度(平成30年度)、海上保安庁は、政府関係機関等が保有する様々な海洋情報を地図上に重ね合わせて表示できるウェブサービス「海洋状況表示システム(海しる)」を構築し、2019年4月から運用を開始した。
海しるを通じて地球全域を対象とする情報やリアルタイムの情報を広く民間事業者、行政機関等に提供することにより、災害や事故の発生・被害状況の把握といった海洋の安全保障のみならず、海運、水産業、再生可能エネルギー等の開発といった海洋の産業活動の促進等、海洋に関する幅広い産業の生産性向上や新たな産業の掘り起こしに寄与していく(図表I-2-1-22)。
図表I-2-1-22 海洋状況表示システム
注5 2019年3月末時点。
注6 地面下に収納されているボラード(車止め)が自動昇降して地上に現れることで、無人で車両通行を制御する施設のこと。