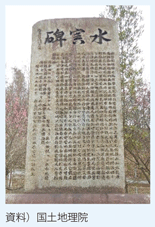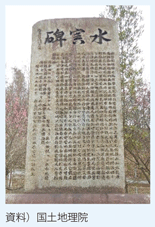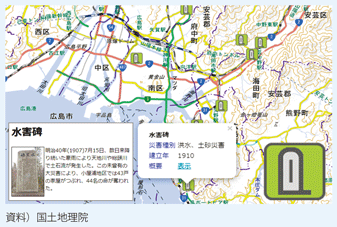しかし、我々、現代人は、この「伝承碑」に記された、過去からの貴重なメッセージを有効に活用できていないように思われます。昨年7月に起こった西日本の豪雨災害の際、多くの犠牲者を出したある地区には、「伝承碑」がありました。111年前に起きた大水害の被害を伝えるものです。ところが、被災後、住民の方の声として「石碑があるのは知っていたが関心を持って碑文を読んでいなかった。水害について深く考えた事は無かった。」(平成30年8月17日 中国新聞)といった報道がなされています。このように、災害を伝える「伝承碑」は全国各地にあるものの、古くて読みにくいといったこともあり、十分な関心を持たれていないのが現状です。
そこで、国土地理院では、地方自治体などの協力を得ながら、全国にある自然災害の「伝承碑」の情報を集め、電子地図である「地理院地図」(
https://maps.gsi.go.jp)等に記録し、本年6月から順次公開します。地理院地図では、「伝承碑」の位置だけでなく、災害の日時、被害の内容などの情報も閲覧することができます(図表I-2-1-21)。あわせて、新しい地図記号「自然災害伝承碑

」を制定し、本年9月から2万5千分1地形図等へ順次掲載を開始する予定です。自然災害の「伝承碑」の情報は、住民の防災意識・対応の向上、教育活動等への活用が期待されることから、石碑に刻まれた過去のメッセージを現代の情報技術も用いて様々な手段で広く発信していくことにより、先人の知恵を未来に引き継いでいきます。