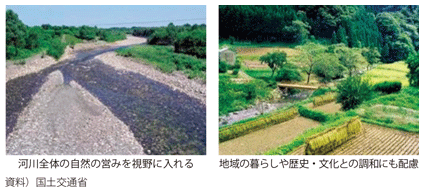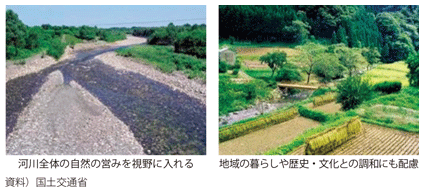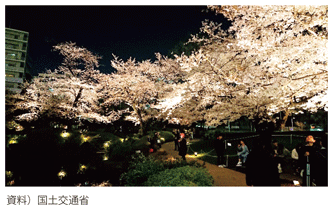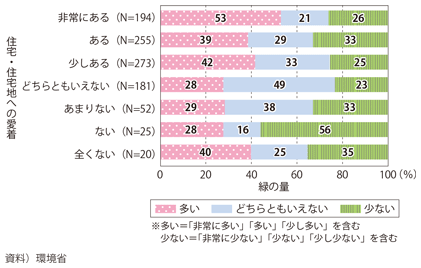■3 自然との調和に向けた変化
■多自然川づくりの推進
平成においては、河川管理について、より自然と調和した動きが生まれてきた。例えば、1990年(平成2年)から、代表的な河川における先進的な取組みとして「多自然型川づくり」が行われ、2006年の「多自然川づくり基本指針」に基づき、「多自然川づくり注14」をすべての河川における川づくりの基本とした(図表I-2-2-14)。
図表I-2-2-14 多自然川づくり
また、1997年には、河川法を改正し、河川管理の目的として、「治水」「利水」に加え、「河川環境」(水質、景観、生態系等)の整備と保全を位置づけること等を行っている。
その後も着実に取組みを進めており、例えば、2017年には、有識者からなる「河川法改正20年 多自然川づくり推進委員会」において、これまでの成果等をレビューし、今後の方向性等について提言がなされている。
この提言を踏まえ、河川環境の整備と保全のため、持続性ある実践的な多自然川づくりを進めていくこととしている。
■都市緑化の推進
我が国では、高度経済成長期において、急激な都市化が進むとともに、緑が失われていった。平成に入り、自然や美しい街並み等の良好な景観に対する国民の意識が高まりを見せ、都市の緑化への関心も強くなってきた。
このような中、都市の再開発に当たり、超高層ビルの建設と併せて、その周辺に緑豊かな公共空間を創出する動きが生まれ、国土交通省においても支援を実施している。例えば、東京都港区の六本木ヒルズでは、地上54階の超高層ビルの建設にあわせ、その周辺に庭園(毛利庭園)等を設けるなど、緑が存在する公共空間をつくり出している(図表I-2-2-15)。
図表I-2-2-15 六本木ヒルズ「毛利庭園」
さらに、都心のみならず、広く市民の手による緑化などを図る動きもある。例えば、千葉県柏市では、NPOの手により個人所有の空き地を活用した緑地が創出され、現在は地域住民のためのイベント広場として利用されている。このような取組みを進めるため、2017年(平成29年)に都市緑地法を改正し、緑化の担い手としてNPO等に公的な位置づけを与え、支援すること等を行っている(図表I-2-2-16)。
図表I-2-2-16 千葉県柏市「ふうせん広場」
環境省の緑化に関する調査注15によれば、住宅・住宅地への愛着を感じている人ほど、自宅周辺の緑の量が多いと感じているという結果となっており、緑化に関するこのような取組みが、緑の量を増やすのみならず、住民の地域への愛着を生み出すことにつながることが期待される(図表I-2-2-17)。
図表I-2-2-17 緑化の意識調査
■エコツーリズム等の推進
平成においては、自然を対象に持続可能な、活用していこうとする「エコツーリズム」の推進が活発になってきた。「エコツーリズム」とは、自然環境や歴史文化等の地域固有の魅力を観光客に伝えることにより、地域の住民も自分たちの資源の価値を再認識し、その保全や地域の活性化につなげていこうとする取組みである。
具体的には、国立公園等の自然豊かな地域から、田舎と言われる里地里山まで、多様な地域・環境において、トレッキングやバードウォッチング、ホエールウォッチング等、地域の様々な資源を活かしたエコツアー等がある(図表I-2-2-18)。
図表I-2-2-18 ホエールウォッチング(小笠原)
国土交通省においても、「エコツーリズム」を推進するため、国内外の観光客に新たな地域への来訪動機を与えることを目的とした「テーマ別観光による地方誘客事業」にて、2018年度(平成30年度)のテーマとして選定した。その上で、積極的に情報発信を進めるとともに、地域間の課題や成功事例を共有し、ネットワーク化等を支援している。
また、多様な主体による協働の下、道を舞台に、地域資源を活かした修景・緑化を進め、観光立国の実現や地域の活性化に寄与することを目的に「日本風景街道」を推進している。2019年3月末現在142ルートが日本風景街道として登録されており、「道の駅」との連携を図りつつ、道路を活用した美しい景観形成や地域の魅力向上に資する活動を支援している。
注14 「多自然川づくり」とは河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、河川管理を行うこと。
注15 平成27年度低炭素ライフスタイルイノベーションを展開する評価手法構築事業 委託業務 成果報告書(緑化等による住宅周辺の温熱環境改善に着目した低炭素ライフスタイル提案手法の開発)