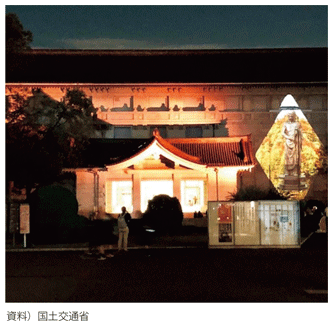■2 官民が一体となった集う空間・優しい空間づくり(つながりの創出)
(集う空間)
■都市公園における官民連携の推進
人々が集う公共空間である都市公園を柔軟に活用するため、民間事業者による売店設置やPFIを活用した水族館運営等、官民連携による都市公園づくりを推進している。
東京都豊島区の「南池袋公園」では、事業者が公園内にカフェを設置するとともに、カフェの収益の一部を公園の整備にも充てている。さらに、この資金を公園のイベント等にも利用することで地域に賑わいをもたらしており、都心の中にありながらも美しい景観を創出したこと等が評価され、2017年度グッドデザイン賞に表彰される等、注目を集めている(図表I-2-2-12)。
図表I-2-2-12 南池袋公園
2018年(平成29年)には、都市公園のさらなる活用を推進するため、新たに「公募設置管理制度(Park-PFI)」を設けた。この制度は、公募により選定された事業者が、飲食店や売店等の収益施設を設置管理し、その収益の一部を公園の整備・改修等に充てることを条件に収益施設を設置管理できる期間を従来の10年から20年まで延長する等のメリットを事業者に与えるものである。また公園内に保育所等の社会福祉施設を占用することが可能となった。
■プロジェクションマッピング等による集う空間づくり
「プロジェクションマッピング」とは、プロジェクターを用いて建築物等に映像を映し出す手法のことであり、海外はもちろんのこと、日本国内においても、遊園地をはじめとして利用されるようになってきている。特に、近年では、映像技術の進歩もあり、お祭りなどにおいて広場や建物などに投影することによって、通常の公共空間を人が集い楽しむ空間に変えるといった取組みが多く行われている。例えば、東京国立博物館では、プロジェクションマッピングにより、重要文化財等の作品を建物に映し出すイベントを開催するとともに、夜間の開業時間を延長することによって賑わいを創出している(図表I-2-2-13)。
図表I-2-2-13 東京国立博物館でのプロジェクションマッピング
一方で、プロジェクションマッピングは、屋外広告物法に基づく地方自治体の条例により看板等と同様の規制を受けており、駅前広場や官公署等における実施が禁止されていることや禁止されていない地域であっても許可が必要とされる場合があることなど、必ずしも柔軟な活用ができるという状況ではなかった。
そこで、2018年(平成30年)に、国土交通省では、プロジェクションマッピング実施の環境整備を推進するため、新たな「条例ガイドライン」を作成した。このガイドラインでは、プロジェクションマッピングについて、禁止する地域を景観上の配慮が必要なところに限定したことのほか、公益性があり期間限定で行われるものは許可制の適用除外とすることができること等を明示している。
(優しい空間づくり)
■あらゆる人に優しい社会の実現
平成においては、全世界的に、高齢者、障害者等が社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害や精神的な障壁を取り除く、「バリアフリー」に関する考え方が広く普及した。
このような中、国土交通省では、2006年(平成18年)に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」を制定し、建築物や公共交通機関のバリアフリー化を進めていった。その結果、視覚障害者等のためにホームドアの設置された鉄道駅数は、2006年当時318駅であったが、2017年度末現在では、725駅までになっている。
さらに、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした、共生社会の実現や一億総活躍社会の実現を目指し、2018年に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立した。同法は、公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組みの推進、バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組みの強化等を主な内容とするものである。
また、国土交通省では、2020年度末までの整備目標を定め、旅客施設及び車両等のバリアフリー化を推進しており、鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルを100%バリアフリー化することなども目指している。