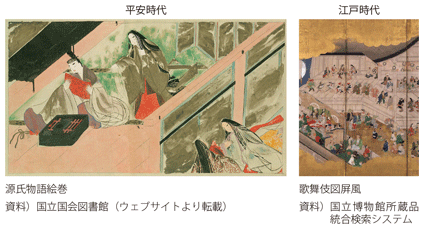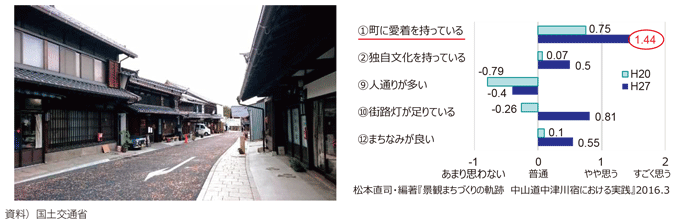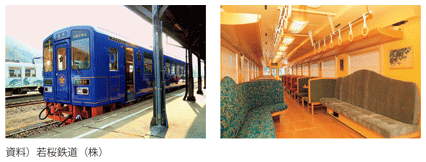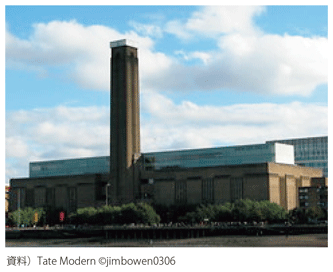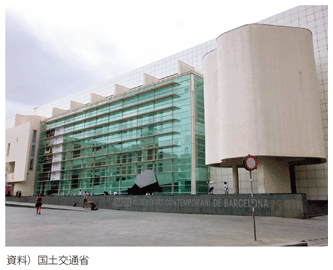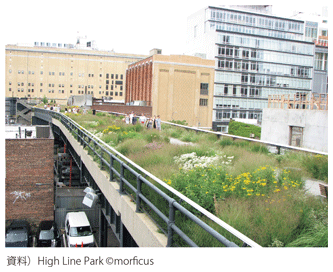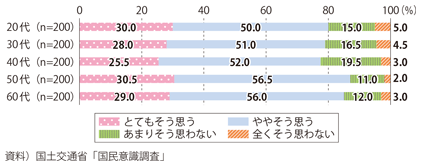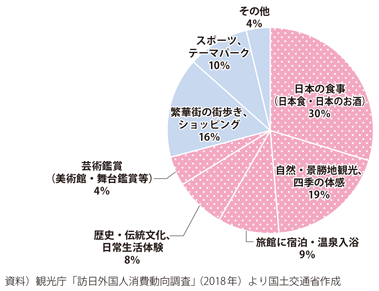■1 新しい時代における日本人の感性(美意識)と「生活空間」の関係
(1)人々の感性(美意識)を取り込んだ生活空間の必要性
(歴史の振り返り)
我が国の歴史を振り返ると、時代ごとに特徴的な文化が栄えている。そのような中にあって、特に生活のゆとりが生まれた人々(階層)は、様々な文化的な営みを行い、日々の時間を更に豊かに過ごそうとしており、そのような動きが各時代の文化に彩りを与えていた。例えば、平安時代には貴族たちを中心に、和歌や月見の風習等の文化が生まれ広まっていき、また、江戸時代においては、ゆとりを持つ庶民が現れ、彼らを中心に歌舞伎などの文化が流行し、日々の生活を豊かにしていった(図表I-3-2-1)。
図表I-3-2-1 豊かな時間の過ごし方(歴史の振り返り)
(現代における文化等の効果)
平成においては、文化を大切にするなど、日本人の感性(美意識)を生活空間に取り込もうとする様々な取組みがなされており、これらのうち、具体的な結果が現れているものも存在する。
その中の一つに「景観まちづくり」が挙げられる。これは、我が国に広がる様々な景観(自然に形成されたものや人々の普段の生活によって生まれたもの等)を守る、あるいは取り戻すことにより、日本の魅力を将来に伝えていこうとする取組みである。
この効果については、例えば、かつて中山道の宿場町であった岐阜県中津川市は、当時のまちなみの景観を取り戻すため、電線地中化や建築物の修景等を行った。このような中において、実施された住民へのアンケートの結果を見ると、「町に愛着を持っている」という回答が全体として、平成20年には「普通」と「やや思う」との間に位置していたものが、平成27年には、「やや思う」と「すごく思う」の間まで増加となり、住民の間で町への愛着がより深まっていることがわかる(図表I-3-2-2)。
図表I-3-2-2 景観を活かしたまちづくりの取組み(岐阜県中津川市)
また、2013年に運行を開始した「ななつ星」をはじめとして、日本の伝統文化等を踏まえて車両をデザインし、快適な移動空間を創出しつつ集客を図る取組みが各地で行われている。このような中、鳥取県の若桜(わかさ)鉄道は2018年3月に観光列車「昭和」の運行をスタートさせた。「昭和」は「川の青」「水の青」をイメージした外観、木を多用し時代の求める「用」と「美」を表現した内装が特徴的である。
若桜鉄道全体の2018年4月から2019年1月までの輸送人員は約30.4万人であったが、2017年度の同時期は約28.0万人と約2.4万人増加しており、「昭和」による輸送人員も寄与しているものと考えられる。また、「昭和」による効果は、経済効果としても現れており、3月から11月までの9ヶ月間で約6,100万円に上ると推計されている注13(図表I-3-2-3)。
図表I-3-2-3 観光列車「昭和」
(海外の流れ)
海外においては、従来より、その国の人々の感性(美意識)を感じられるような空間を守り、また、そのような感性(美意識)をできるだけ取り込むことにより、新たに活性化を図ろうとする動きが見られる。
フランスでは、1982年から、「フランスの最も美しい村」を認定する運動が行われている。これは、人口は少ないがフランスらしい美しい村について、「美しい村」として認定し、知名度を高め観光業の発展等につなげ、維持発展させていこうとする取組みである(図表I-3-2-5)。こうした動きは、その後フランス以外の国においても見られるようになり、2003年には、ベルギー、イタリアを加えた3カ国による「世界で最も美しい村連合」が結成され、2017年現在では、カナダや日本もこの連合に加盟している。
図表I-3-2-5 過疎化が進む小さな村ルールマラン(「フランスの最も美しい村」に認定)
また、イギリスのロンドンには、「テート・モダン」と呼ばれる近現代美術館がある。この美術館は、1981年に閉鎖された巨大な火力発電所を美術館としてリノベーションすることによって誕生したものであり、かつてタービンが置かれていた巨大なスペースをそのままエントランスホールとして利用したり、煙突をあえて残すなどの工夫がなされている。世界で最初の産業革命により工業国となったイギリスらしさを感じさせるこのような特徴から、「テート・モダン」は、2000年の開館以降、世界中から毎年500万人以上という、世界でもトップクラスの来訪者数を誇っている。さらに、観光ビジネスを中心に約4,000人の新規雇用を生み出したと推計されており、この地域における従来の高い失業率の改善や地域活性化に大きく貢献していると考えられる(図表I-3-2-6)。
図表I-3-2-6 テート・モダン
スペインのバルセロナにある「ラバル地区」の旧市街地では、建物の老朽化、治安・衛生環境の悪化等の問題に直面していた。このような中、地域を再生するため、建物が密集する街区が取り壊され、広場等の公共空間として生まれ変わった。さらに、この空間に美術館を誘致するとともに、文化やアートに関するイベントを開催できるようにすることによって、地区内の住民が憩う場所になるとともに、文化やアートに関心を持つ地区外の人々を呼び込むことにも成功した。このことにより、周辺地域に店舗やギャラリー等が立地され、それが更に地域のブランドイメージを高めて人々を集めるという好循環を生み、治安の改善や経済の活性化等、地区の再生につながっている(図表I-3-2-7)。
図表I-3-2-7 バルセロナ現代美術館
アメリカのニューヨークにある「ミートパッキング地区」には、廃線となった高架式の貨物鉄道の跡地を再生した「ハイライン」と呼ばれる公園がある。この跡地は、1980年の廃線以降、約20年に渡り放置されたことによる治安の悪化等を受けて取り壊しの予定であった。ところが、1999年以降、近隣に住む2人の青年が歴史的価値を重視し取り壊しに反対する運動を始めたところ、多くの市民や政治家、メディア等の支持を集めることとなり、2004年に公園へ転用されることが決定した。こうして生まれた「ハイライン」は、2009年のオープン以降、その歴史的価値やそこから眺める景観の良さ、さらには美しい植栽や様々なイベントの開催等により、多くの人々を集めるようになった。その結果、周辺地域にはホテルやブティック、レストランや美術館等が続々と整備されることとなり、「ハイライン」は、年間約700万人の訪問者を誇る、都市再生の成功例となっている(図表I-3-2-8)。
図表I-3-2-8 ハイライン
(現代の日本人等の意識)
今後、新技術の活用等により、我々は今よりも「時間的・場所的な制約」から解放されることが想定される。このような中、現代の日本人は、将来の生活空間において、日本人の感性(美意識)がもっと取り込まれていくべきと考えているどうかについて、調査した。
その結果、20代から60代以降までのすべての世代において、「とてもそう思う」と「ややそう思う」と答えた人をあわせると約8割となり、多くの人が将来の生活空間において日本人の感性(美意識)がもっと取り込まれていくべきと考えていることがわかった。その中においても、特に50代と60代以降の人々の意識が総じて高く、また、20代において「とてもそう思う」と答えた割合が高いという結果になっている(図表I-3-2-10)。
図表I-3-2-10 未来の生活空間において、現在以上に感性や美意識を取り込むべきと考える人の割合
なお、近年、観光客数が著しく増加し、その影響が大きくなってきている外国人の意識についても言及する。
第1章第3節で引用した観光庁「訪日外国人消費動向調査」を踏まえ整理
注14すると、2018年に日本を訪れた外国人が訪日前に最も期待していたこととして、日本の食事、自然・景勝地観光、四季の体感等があり、いわゆる「日本らしさ」が約7割を占めている(図表I-3-2-11)。「日本らしさ」は日本人の感性(美意識)を反映したものが多く、訪日外国人はそれらに触れることを期待していることがわかる。
図表I-3-2-11 訪日外国人が訪日前に最も期待していたこと
この結果等を踏まえると、将来の生活空間に日本人の感性(美意識)がもっと取り込まれることは、外国人にとっても望ましいことであると推察される。
(2)将来の生活空間の方向性
前節で概観したように、将来は、新技術等の活用により「時間的・場所的な制約」から解放されるとともに、新たな「自由時間」を活かした、充実したヒューマンライフの実現がますます重要となってくると考えられる。
このような中、(1)では、歴史的にはゆとりが生まれた人々が文化により豊かな時間をつくろうとしたこと、現代では文化等により一定の結果が生まれていること、海外においてはその国の人々の感性(美意識)を生活空間に取り込もうとする動きが見られること、さらに、現代の日本人は将来の生活空間に感性(美意識)をもっと取り込んでほしいと考えていることなどについて触れた。
以上を踏まえると、将来において、「住空間」、「公共空間」、「移動空間」といった「生活空間」に日本人の感性(美意識)をもっと取り込んでいくことが更に重要になってくることが想定される。そして、その際には、
第2章で述べたような、歴史まちづくりをはじめとする、関連するこれまでの国土交通省の取組みを深化していくとともに、これから更に発展する新技術と一体となった新たな取組み(サイエンスとアートの融合)を行い、豊かな「生活空間」をつくることが重要になると考えられる。
注13 (一社)麒麟のまち観光局による推計
注14 ここでは、訪日外国人消費動向調査(2018年)における21個の選択肢を図表I-3-2-11に示す8個の選択肢に集約している。