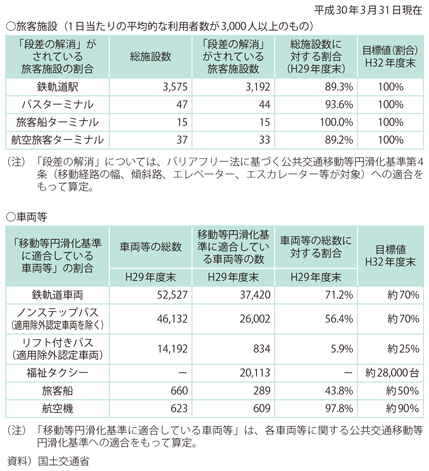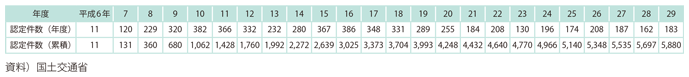第7章 安全・安心社会の構築
第1節 ユニバーサル社会の実現
■1 ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー化の実現
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえた「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」により、施設等(旅客施設、車両等、道路、路外駐車場、都市公園、建築物等)の新設等の際の「移動等円滑化基準」への適合義務、既存の施設等に対する適合努力義務を定めるとともに、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」において、令和2年度末までの整備目標を定め、バリアフリー化の推進を図っている。
また、市町村が作成する基本構想に基づき、重点整備地区において重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進しているとともに、バリアフリー化の促進に関する国民の理解を深め、協力を求める「心のバリアフリー」を推進するため、高齢者、障害者等の介助体験や疑似体験を行う「バリアフリー教室」等を開催しているほか、バリアフリー施策のスパイラルアップ(段階的・継続的な発展)を図っている。
こうした中、「バリアフリー法」を取り巻く環境の変化、また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした、共生社会の実現を目指し、全国において更にバリアフリー化を進めるため、平成30年5月、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第32号。以下「改正バリアフリー法」という。)が第196回国会で成立した。具体的には、1)公共交通事業者等によるハード対策及びソフト対策の一体的な取組を推進するための計画制度の創設、2)バリアフリーのまちづくりに向けた地域における取組を強化するための移動等円滑化促進方針制度の創設、3)バリアフリー法の適用対象の拡大、4)建築物等のバリアフリー情報の提供の努力義務化等の措置を講ずることとしている。加えて、改正バリアフリー法の円滑な施行に向け、必要な政省令等を公布した(平成30年11月1日施行。ただし、一部の規定は平成31年4月1日施行。)。
(1)公共交通機関のバリアフリー化
「バリアフリー法」に基づき公共交通事業者等に対して、旅客施設の新設・大規模な改良及び車両等の新規導入の際に移動等円滑化基準に適合させることを義務付け、既存施設については同基準への適合努力義務が課されているとともに、その職員に対し、バリアフリー化を図るために必要な教育訓練を行うよう努力義務を定めている。加えて、改正バリアフリー法においては、公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組みを推進するため、一定の要件を満たす公共交通事業者等が、施設整備、旅客支援、情報提供、教育訓練、推進体制等を盛り込んだハード・ソフト計画を毎年度作成し、国土交通大臣に提出するとともに、その取組状況の報告・公表を行うよう義務付ける制度を新たに設けた。さらに、旅客船、鉄道駅等旅客ターミナルのバリアフリー化やノンステップバス、リフト付きバス、福祉タクシーの導入等に対する支援措置を実施している。なお、移動等円滑化基準については、平成30年9月には航空機に乗降するためのタラップ等の基準を新たに規定するための改正を行った。また、平成31年4月より新たに貸切バス車両及び遊覧船等がバリアフリー法の対象となることに伴い、平成31年3月にこれらの基準を規定する改正を行った。