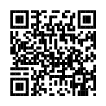国土交通白書 2022
第2節 自然災害対策
(1)多重性・代替性の確保等
風水害・土砂災害・地震・津波・噴火・豪雪・原子力災害等が発生した直後から、救命・救助活動等が迅速に行われ、社会経済活動が機能不全に陥ることなく、また、制御不能な二次災害を発生させないことなどを目指し、高規格道路のミッシングリンクの解消及び暫定2車線区間の4車線化、高規格道路と代替機能を発揮する直轄国道とのダブルネットワークの強化、災害時の道路閉塞を防ぐ無電柱化等を推進し、災害に強い道路ネットワークの構築を進め、鉄道・港湾・空港等の施設の耐災化や緊急輸送体制の確立を図ることにより多重性・代替性を確保するとともに、利用者の安全確保に努めている。
(2)道路防災対策
大規模災害時の救急救命活動や復旧支援活動を支えるため、災害に強い国土幹線道路ネットワークの構築、レーザープロファイラ等を活用した土砂災害等の危険箇所の把握及び防災対策(斜面・盛土対策等)、震災対策(耐震補強等)、雪寒対策(防雪施設の整備等)、道路施設への防災機能強化(道の駅及びSA・PAの防災機能の付加、避難路・避難階段の整備)等を進めるとともに、道路啓開計画の実効性を高めるため、民間企業等との災害協定の締結や、道路管理者間の協議会による啓開体制の構築を推進している。また、平成26年11月の「災害対策基本法」の改正を踏まえ、速やかな道路啓開に資する、道路管理者による円滑な車両移動のための体制・資機材の整備を推進している。
さらに、バイクや自転車、カメラの活用に加え、UAV(無人航空機)による迅速な状況把握やETC2.0等の官民ビッグデータなども活用した「通れるマップ」により関係機関に情報共有・提供を実施している。
また、近年の自然災害の頻発化・激甚化を踏まえ、広域災害応急対策の拠点となる道の駅等について、災害時に防災拠点としての利用以外の禁止・制限等が可能となる防災拠点自動車駐車場の指定制度の創設や、都道府県が、市町村からの要請により、市町村管理道路の道路啓開・災害復旧を迅速に代行できる制度を創設する道路法の改正について、令和3年6月に施行した。
このほか、地方公共団体のニーズを踏まえた、津波や洪水による浸水から避難するため、道路の高架区間等の活用が可能な箇所において、避難階段等の整備を推進している。
なお、東日本大震災による津波により壊滅的な被害を受けた地域等において、復興計画に位置付けられた市街地整備に伴う道路整備や、高速道路ICへのアクセス道路等の整備を推進している。また、津波被害を軽減するための対策の一つとして、標識柱等へ海抜表示シートを設置し、道路利用者への海抜情報の提供を推進している。
(3)無電柱化の推進
道路の防災性の向上や安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成、観光振興の観点から、令和3年5月に策定した無電柱化推進計画に基づき、無電柱化を推進した。また、緊急輸送道路や幅員が著しく狭い歩道等も対象に電柱の新設を禁止する措置を拡大、道路事業等や市街地開発事業等にあわせた道路上の電柱の設置抑制、沿道区域における電柱等を設置する場合の届出・勧告制度の運用を開始するとともに、地方公共団体が実施する無電柱化への重点的な支援を実施した。
(4)各交通機関等における防災対策
鉄道については、旅客会社等が行う落石・雪崩対策等の防災事業や、開通以来30年以上が経過する青函トンネルについて、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う先進導坑や作業坑に発生している変状への対策等に対し、その費用の一部を助成している。
また、土砂災害等からの鉄軌道の安全確保を図るため、トンネル、雪覆、落石覆その他の災害等防止設備等の点検、除雪体制の整備及び災害により列車の運転に支障が生ずるおそれのあるときには当該路線の監視等の適切な実施など、災害に強く安全な鉄道輸送の確保のために必要な対応を行っている。
さらに、平成30年度からの取組みである「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」の更なる加速化・深化を図るため、令和2年12月に「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」がとりまとめられ、河川橋梁の流失・傾斜対策、斜面からの土砂流入防止対策、地下駅・電源設備等の浸水対策、地震による駅、高架橋等の倒壊・損壊対策を推進するとともに、予防保全に基づいた鉄道施設の老朽化対策についても、7年度までの間に集中的に実施することとしている。
被災した鉄道に対する復旧支援については、鉄道軌道整備法に基づく災害復旧事業費補助により、地震や豪雨などの災害で被災した鉄道の早期復旧を支援している。また、特に大規模な災害で甚大な被害を受けた鉄道において、事業構造を変更し、公的主体が鉄道施設を保有する場合に、国の支援を手厚くし、復旧を強力に支援している。
港湾については、熊本地震の教訓を踏まえ、非常災害時に港湾管理者からの要請に基づき、国が港湾施設の管理を行う制度が平成29年6月に創設された。運天港においては、海底火山「福徳岡ノ場」の噴火による軽石により航路・泊地が埋塞し、離島航路の運航に支障が生じたことから、本制度に基づき、令和3年12月、港湾管理者である沖縄県の要請を受け、運天港の一部の港湾施設を国が管理し、軽石対策の円滑な実施体制を確保した。また、大規模災害時でも港湾機能を維持するため、関係機関と連携し、防災訓練の実施や港湾BCPの改善を図ることや、衛星やドローン、カメラ等を活用して、港湾における災害関連情報の収集・集積を高度化し、災害発生時における迅速な港湾機能の復旧等の体制を構築する等、災害対応力強化に取り組んでいる。
空港については、平成30年の台風第21号や北海道胆振東部地震、また令和元年房総半島台風により空港機能やアクセス機能が喪失し、多くの滞留者が発生したことを踏まえ、このような大規模自然災害による多様なリスクに対し、アクセス事業者を含めた関係機関が一体となって対応する「統括的災害マネジメント」の実現による自然災害に強い空港作りを目指している。
そのため、耐震対策や浸水対策等のハード対策に加え、ソフト対策として「統括的災害マネジメント」の考え方を踏まえ、各空港で策定された空港BCP(「A2–BCP」注14)に基づき、災害時の対応を行うとともに、訓練の実施等による空港BCPの実効性強化に取り組んでいる。
(5)円滑な支援物資輸送体制の構築等
首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の広域かつ大規模な災害が発生し、物流システムが寸断された場合、国民生活や経済活動へ甚大かつ広域的な影響が生じることが想定される。
被災者の生活の維持のためには、必要な支援物資を迅速・確実に届けることが重要であることから、災害時における円滑な支援物資物流を実現するため、引き続き、地方ブロックごとに国、地方公共団体、物流事業者団体等の関係者が参画する協議会等において、物流専門家の派遣を含む都道府県と物流事業者団体との災害時協力協定の締結の促進や、平成30年度に策定した「ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ハンドブック」等の周知、新たな民間物資拠点のリストアップの促進を行った。
また、令和2年度においては、空港が被災した場合等を想定した代替輸送手段の確立のため、主要空港が機能不全に陥った場合を想定し、災害時においてもサプライチェーンを維持できるよう、代替輸送手段の活用等に係る物流関係者間の連携体制の構築に向けた指針を策定した。
- 注14 「A2 (Advanced/Airport)-BCP」…空港全体としての機能保持及び早期復旧に向けた目標時間や関係機関の役割分担等を明確化した空港の事業継続計画