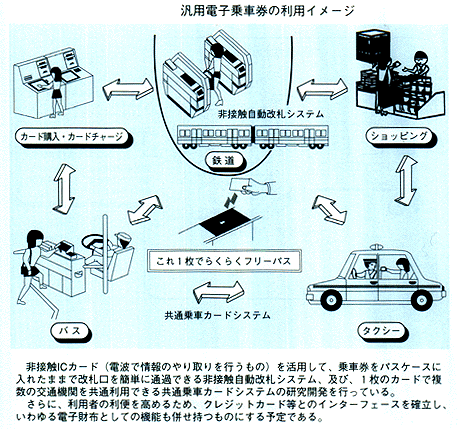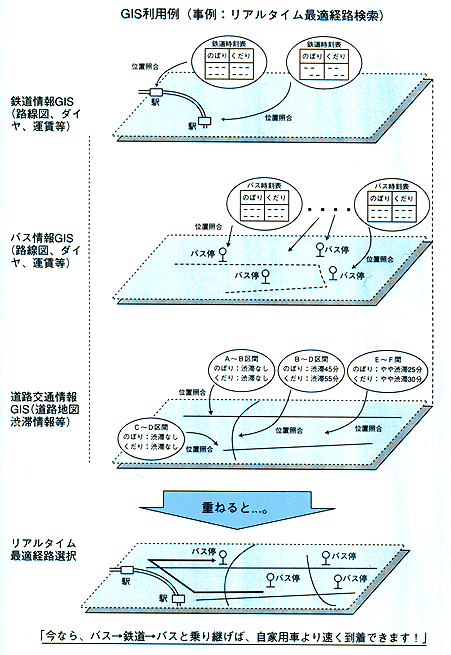第2節 交通運輸への活用
1 都市交通と情報化
都市部における輸送需要に応えるためには、インフラの増設・拡張に代わる手段として、情報通信技術を活用した輸送効率の向上による交通容量の拡大や既存インフラの最大有効活用が、極めて有力な政策手段となってきており、安全性や利便性の向上、事業経営の効率化、環境問題や高齢化問題への対応等に当たっても、情報通信技術の活用は重要な意義を有するものである。
このため、従来より各運輸事業者によって以下のような取り組みが進められてきており、運輸省としてもその推進を図ってきている。
(1) 輸送機関の安全性の向上に資するシステムの例
(ア) 運輸多目的衛星を活用した次世代航空管制
現在、運輸省は運輸多目的衛星(MTSAT)を中心とした次世代航空保安システムの構築を進めているが、これにより、地上基地局からの通信と監視のための航空通信機能や航空機の航法を支援する航法機能の向上を図り、より一層の安全性の確保と将来の航空需要に対応した航空交通容量の拡大をめざしている。
(2) 利用者の利便性を向上させるためのシステムの例
(ア) バスロケーションシステム
バスロケーションシステムは、バスに搭載した車載機から発信する電波を用いてバスの位置情報等を停留所又は各営業所に正確かつ迅速に提供することにより、利用者の利便性の向上や適切な運行管理に役立っている。
(イ) MARS
旅客販売総合システム(マルス:MARS)は、JR各社の乗車券類の他、航空券、レンタカー券、イベント券などの総合的な予約販売を行うシステムであり、昭和35年の初運用以来、最新の情報通信技術を取り入れつつ、改良を重ねている。
(ウ) ストアードフェアシステム
ストアードフェアシステムは、乗車券を購入せずに磁気カード(ストアードフェアカード:SFカード)を直接自動改札機に挿入することができるシステムである。
最近では、多くの事業者がこれを導入しているほか、地域ごとの共通利用化が図られている。
(エ) CRS
CRS(Computer Reservation System)は、一台の端末で一度に複数の航空会社の便を検索し予約できる航空機座席予約システムである。国際線のネットワークが広がる中、近年は航空座席に加えてホテルや主催旅行(いわゆるパッケージ・ツアー)などの予約もできる海外旅行の総合システムへと進化している。
(3) 効率的な事業経営を行うためのシステム
(ア) 運行管理システム
トラックの運行管理システムは、トラック事業者が荷主、トラック等とのネットワークを構築することにより、通信システム等を経由して、詳細な走行実績の把握や経営分析等を可能とし、輸送の安全性、効率性等の向上に大きく寄与している。
(イ) CTC
列車集中制御(CTC: Centralized Traffic Control)は、広範囲の線路等に設置されている信号機や転てつ器等を一箇所の制御室において集中的に遠隔制御する方式であり、これにより、運行管理の能率向上、運行本数の拡大、各駅の省力化、ダイヤ乱れの早期復旧等、効率性の面から極めて大きな意義を有している。
2 ITSについて
高度道路交通システム(ITS:Intelligent Transport Systems)は、最先端の情報通信技術等を活用して、人と道路と車両とを一体化し、安全で快適な、環境にも優しい交通システムの構築をめざすものであり、都市交通の円滑化にも資するものとして大いに期待されている。
運輸省においては、現在、以下のプロジェクトに取り組んでいる。
(ア) 先進安全自動車(ASV:Advanced Safety Vehicle)の研究開発
(イ) 道路運送事業におけるITS技術の活用
(a) 環境に配慮した安全で円滑な自動車の運行の実現を図るため、道路運送事業においてITS技術を活用し、公共交通の利用促進や物流の効率化を進める。
(b) ITSの活用方策を調査研究し、平成11年度より公共交通高度情報システム及び貨物輸送高度情報システムの整備に係る課題の抽出、実証実験等を実施する。
(ウ) ナンバープレート等の活用の検討
3 今後の取り組み
利便性の向上、安全対策、環境対策といった観点から都市交通の情報化を促進して行く上では、これまで輸送機関毎に別々に行われてきた施策を有機的に組み合わせるとともに、人の流れや物の流れに着目した、利用者の視点、インターモーダルな視点から、ドア・ツー・ドアで隙間のない良質なサービスが提供できるような仕組みを構築していく必要があり、運輸省では以下のような施策に取り組んでいくこととしている。
(1) 非接触式ICカードを活用した汎用電子乗車券の研究開発
運輸省では、非接触式ICカードを活用し、鉄道・バスといった異なる輸送機関や複数の企業間で共通利用を行えるとともに、電子マネー機能を付与することにより買い物にも利用できるICカード乗車券の開発を推進してきた。11年度は、鉄道・バス間の仕様の標準化、普及促進方策の検討を行っている。
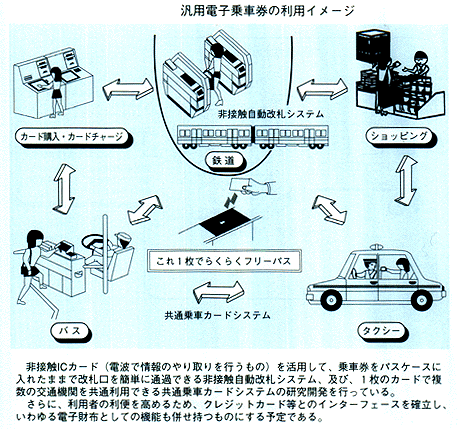
(2) 簡易無線端末を活用した移動制約者支援モデルシステムの研究開発
運輸省では、郵政省等と連携して、PHS等の簡易無線端末関連技術を活用し、高齢者、身体障害者といった移動制約者に携帯端末を通じて駅構内の施設案内や列車の接近などの危険情報などを提供するシステムの研究開発を10年度から3ヶ年計画で行っており、11年度はJR東日本高崎駅で実証実験を行っている。
(3) 地理情報システム(GIS)の活用方策の検討
GIS(地理情報システム:Geographic Information System)とは、地理的位置や空間に関する情報を持った自然、社会、経済等のデータを地図上に重ね合わせて表示するシステムであり、防災計画、各種行政計画への活用のほか、運輸分野での活用の可能性についても大いに期待されている。
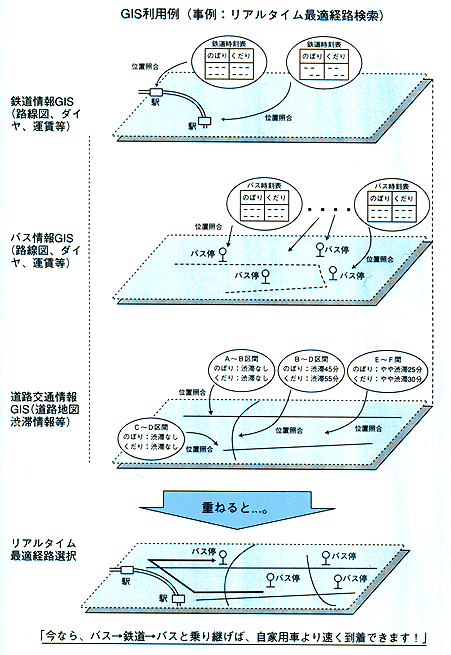
(4) 電子データ交換(EDI)の普及促進
商取引を効率化するため、異なる企業間で、商取引のためのデータを、広く合意された規約に基づき、コンピュータ間で交換するいわゆるEDI(電子データ交換:Electronic Data Interchange)の普及を促進している。運輸分野では鉄道、航空分野で早くから進められてきたが、近年は物流分野や観光分野においても様々な取り組みが進められている。
このほか、これらの取り組みを有機的に組み合わせ、必要な情報をオープンなネットワークにおいて流通させることにより、総合的な交通情報を入手したり、自宅で予約・発券等を行えるような総合交通情報提供システムの構築をめざし、現在検討を進めている。