|
2 通勤・通学輸送
〔I−4−29表〕は,三大都市交通圏の都心流入人口の推移を示したものであるが,都心部における住宅難から居住地が都市周辺部に拡がつているため,三大都市交通圏全体でみると都心流入人口は昭和30年の124万人から35年には175万人と実に41%も増加し,三大都市交通圏内の人口全体に占める比重も4・9%から5.9%に上昇している。
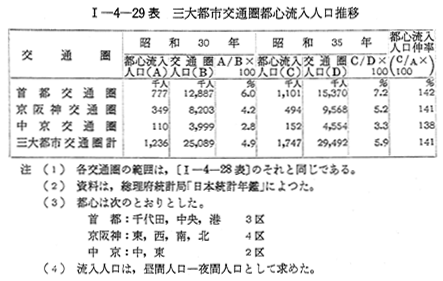
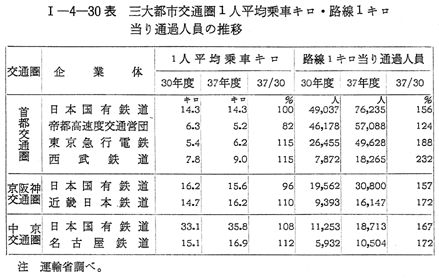
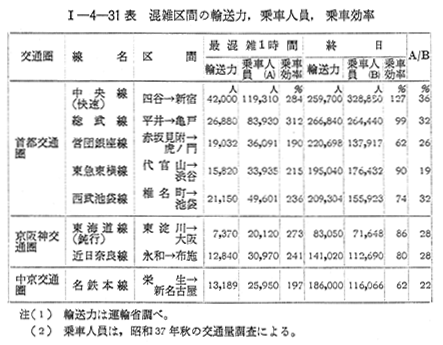
三大都市交通圏内の輸送人キロを交通機関別にみると, 〔I−4−32−1表〕のとおり各交通圏によつて差があるが,全体としては高速鉄道すなわち国鉄,私鉄,地下鉄の比重が圧倒的で全体の83%を占め,残りを路面電車,パス,ハィヤー,タクシーが輸送している。交通機関別の輸送人員の推移をみると, 〔I−4−32−2表〕のとおり,地下鉄,バス,次いで国鉄,私鉄の増勢が著しく,路面電車は絶対数では横ばいであるが全体に対する比重は大幅に減少している。地下鉄の伸びが著しいのは通勤通学輸送難改善のため大規模な地下鉄網建設が三大都市交通圏において進められている,ためであり,バスの増加原因は,人口増加が鉄道網の粗い中心都市周辺部に著しいので,これらの人々の輸送需要をまかなうために,バスが弾力的に最寄鉄道駅までのバス綱を形成していくためであろうと思われる。また,路面電車の減少傾向は路面混雑激化にともない速度低下が著しく,通勤交通機関としての機能が低下し,また,都心部には地下鉄の建設が意欲的に進められているためそれに乗客をうばわれたためと考えられる。
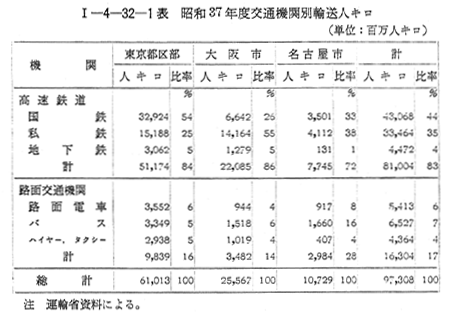
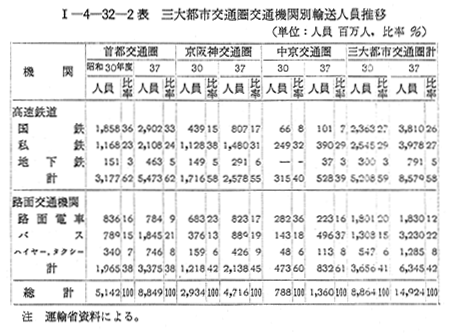
各都市交通圏別にみると首都、京阪神交通圏のように超大交通圏となると高速鉄道の比重が高く,全体の84〜86%を占めているが,中京交通圏では,72%となつており,路面交通機関とくにバスも16%とかなりの比重を占めている。都市交通圏内の人口増加傾向が今後も継続し,さらに職場の都心への集中,住宅の郊外への分散が続くならば,両者を結ぶ通勤通学幹線輸送機関として高速鉄道の重要性は増大し,バスは高速鉄道最寄駅と住宅とを結ぶ末端輸送および通勤通学幹線輸送の補助としての役割を果たすようになるであろう。
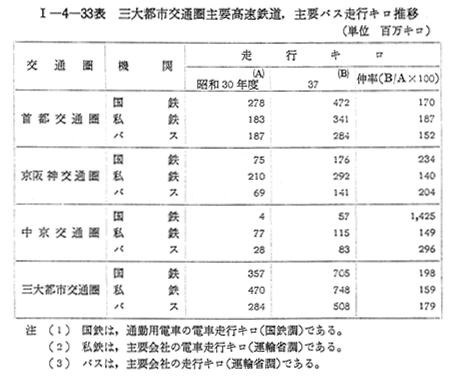
以上の輸送力増強とならんで既存の輸送力を有効に利用するために,時差出勤が35年の冬から国鉄によつて強力に提唱され相当の効果が挙げられたので,その後政府においてとりあげ年々強力,広範囲にこの時差出勤が推進され,39年1月末現在,東京では,協力官公庁,事業所,学校数は662カ所・協力人員40万6000人(前年比33%増)に達し、ラッシュピーク時の混雑はかなり平準化の動きがみられ,電車の遅延についても改善がみられた。しかし,この通勤時間帯の幅を拡げていくことには,官公署,会社,工場の勤務体制を大幅に変更しない限り限度があり,都市交通の根本的解決策とはならない。したがつて,通勤時間帯の幅を拡げる努力とならんで積極的に輸送力の増強を強力に推進する必要がある。
|