|
3 需給関係ひつ迫化の運輸事業への影響
さきにみたように,労働力の不足は従業者の充足率の低下によつて日常業務の正常な遂行を困難にする傾向があること,とくに輸送力の維持発展を図るうえに大きなあい路となる危険性を大きくもつていること,また,就業構造の安定性を欠き雇用計画を立案しにくくさせていること等の悪影響をもたらしている。ここでは,賃金面における影響およびそれがさらに運輸事業の経営上にもたらす影響についてみよう。
〔I−5−4表〕のように運輸業における昭和30年以降の賃金水準は全産業平均よりも高くなつているが,賃金の上昇率を現金収入総額によつてみると,30年から37年までの間に63.9%と全産業平均の60.6%を上回る伸びを示した。
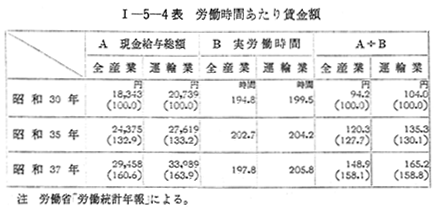
中小規模の企業における賃金は,新規学卒者や若年労働力の不足を中心とする労働力需給のひつ迫化に刺激ざれて,ここ数隼来,増勢を強め 〔I−5−5表〕にみるように,大企業の賃金上昇率を上回る上昇率を示した。この結果規模別賃金格差は縮小している。しかし,これを全産業平均と比較すると,運輸事業の賃金は規模別格差が元来相対的に小さいため,格差の縮小幅も相対的に小さくなつている。
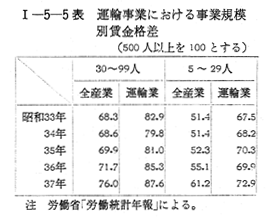
また,若年層賃金の上昇により年令別賃金格差も縮小している。このような人件費の上昇は,運輸事業にとつて経営圧迫要因とたることは避けられず,しかも,運賃水準は,公共的見地から,容易に引上げられず,その要因を企業体内で吸収すべく,事業の協同化あるいは,機械化の推進や,生産性向上の必要性が増大してくるものと思われる。
|