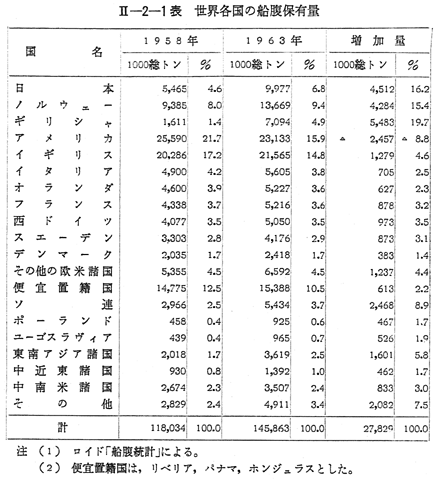|
1 きびしい試練に立つ外航海運
(1) 世界海運の動向
1963年の世界の貿易は,輸出1347億ドル,輸入1421億ドルに達し,1962年にくらべてそれぞれ9%,8%の増加となつた。この世界貿易の増加を数量指数(1958年=100)によつてみると,輸出は141で,1962年の131に対して8%弱の上昇であり,輸入もまた144で1962年の135に対し7%弱の上昇を示した。このような世界の貿易量の増加によつて,世界の海上貿易量も1962年の12億3000万トンをかなり上回る13億トン程度に達したものと推定されている。
一方,1963隼の世界の商船船腹量は,1億4586万総トンに達し,1962隼より588万総トン,4%増加した。この増加量は,1962年の1961年に対する増加量406万総トン,3%を上回つており,1962年にやや増勢が鈍化した世界船腹は,いぜん根強い増加傾向を持続している。
1963年の1962年に対する船腹増加量を船種別にみると,世界の海上貿易における工業原燃料の比重が高まつているのを反映して,ばら積専用船および油送船の増加量の割合が著しく高く,増加船腹量のうち,46%をばら積専用船が,33%を油送船が占めている。また,これらばら積専用船および油送船の大型化の傾向がいつそう強まつてきている。
世界各国の商船船腹の増加の動向をみると,四つの特徴がみられる。その一つは,わが国の船腹拡充が,世界に類例のない経済成長にともなう貿易規模の拡大に対応するため,大型油送船および専用船を中心にして,急速に進められていることである。その二つは,ノルウエーと,便宜置籍国を含めたギリシャ系の海運が,大型油送船およびばら積専用船を中心とする船腹構成のもとに著しい船腹の拡充を進めており,三国間輸送を主とする,いわゆる国際型海運として世界の海運市場に大きく進出してきていることである。その三つは,低開発国が経済の自立体制強化のため,手厚い保護育成政策のもとで自国海運の増強を進め、漸次その勢力を強めていることである。また,その四つは,先進海運国であるアメリカ,イギリスの海運が停滞ないしは後退し,フランス,オランダ,西ドイツ,イタリアの海運の船腹増加が少量に止まつていることである。
すなわち,1958年と1963年の世界各国の商船船腹量をみると 〔II−2−1表〕のとおりで,この5年間の世界船腹の増加量2783万総トンのうち,わが国は451万総トン,16.2%,ノルウエーは428万総トン,15・4%,ギリシヤは548万総トン,19.7%とこの三カ国で大半を占め,低開発国は290万総トン,10.5%,ソ連は247万総トン,8.9%とその勢力を強めてきており,これに対してノルウエー,ギリシヤを除く欧米海運国の相対的地位は低下してきている。
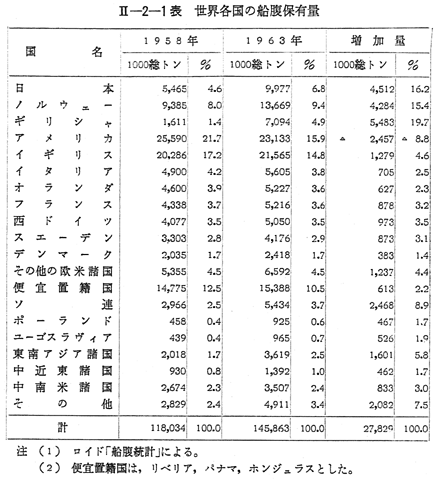
(2) わが国海運をとりまく国際情勢
外航海運はその活動の場がすべて世界市場に直結しているために,世界の政治9経済情勢の変化による影響をじかに受けるという点においてきびしい環境にあるといえる。
(3) 東南アジア諸国は,ホンコン,インド,パキスタン,中国,インドネシア,フィリピンの6カ国とした。
(4) 中近東諸国は,エジプト,イスラエル,トルコの3カ国とした。
(5) 中南米諸国は,アルゼンチン,ブラジル,チリ,メキシコ,ペルー,ベネズエラの6カ国とした。
わが国外航海運をとりまく国際情勢は,二つの異つた面からいつそうきびしくなつている。一つは,わが国のOECDへの加盟にともなう開放経済体制への移行であり,一つは,伝統的な海運自由の原則を否定しようとする勢力の国際海運活動に対する干渉がひきつづき強化される動きが現われてきたことである。
わが国が開放経済体制に入る過程においてまず海運に及ぼした影響は,OECD加盟にともなう外国用船の規制の排除である。
OECDへの加盟によつて,わが国が先進国国際社会の一員として認められたことにより,欧米先進諸国との貿易の伸長による海上貿易量増加への期待や,国際海運問題の多くが多数国間の話し合いで解決される方向に進むと考えられるなどの点で,わが国海運にとつても利点が考えられるといえよう。
しかしながら,わが国がこれまで行なつてきた長期外国用船の制限がOECDの自由化規約にてい触するために,わが国がOECDに加盟するにあたつて,用船制限を撤廃することが問題となつた。わが国としては海運業の再建整備計画に着手したばかりで,現状では日本船はとうてい外国船との競争に耐えられないことから,長期外国用船の規制を向う5年間存続することを要望したが,ノルウェーをはじめとする西欧海運国の強い反対をうけ,その結果石油については2年,石炭,鉄鉱石については1年の期限で用船規制の存続が認められたに止まつた。これによりわが国外航海運は完全な自由化体制をとることとなつた。
一方,国際海運活動については,自由な民間の商業活動として行なわれるべきであり,政府が直接これに介入してはならないという伝統的な海運自由の原則が,従来広く慣行として受け入れられてきたのであるが,近年米国および低開発諸国がこの慣行に反する政策をとり,しだいにこれを強化する方向に向つている。
その最も影響力の大きいものは,米国政府の運賃同盟に対する干渉とシップ・アメリカン政策である。
米国は,従来からアンチ・トラスト主義を基本的な考え方としており,国際的なカルテルである運賃同盟に対しても,1916年の海運法により,独占禁止法規の適用は除外しているものの,政府がその活動を監視するという条件を付しており,また同盟の自衛手段の多くを禁止していた。さらに1961年10月には,米国最高裁で海運法違反とされた二重運賃制を合法化はするが,これを認可割のもとにおき一定の条件を備えることを要求し,また連邦海事委員会に定期航路運賃に対する広範な規制権限を与えることなどを内容とする。海運法の一部を改正するボナー法案が,世界の海運国あげての強硬な反対にもかかわらず成立した。この改正法によつて,米国政府の国際海運活動に対する干渉権は著しく弦化され,その施行にともなつて国際的に多くの問題が生じている。
また,シップ・アメリカン政策については,米国はすでに第2次世界大戦前から政府関係特定物資の輸送について米国船優先積取措置をとつてきたが,1960年頃からドル防衛政策の一環としてこれをいつそう強化してきている。すなわち,米国輸出入銀行借款物資および余剰農産物の輸送における米国船優先積取措置の強化からさらに1963年10月には米国小麦の対ソ輸出の許可にあたつてこれが全くコマーシャルな取引でなされているものであるにもかかわらず甘米国船優先使用の方針を強行するにいたつた。こうした,シップ・アメリカン政策の強化が,日米間航路に重点をおいているわが国海運に及ぼす影響は非常に大きい。
さらに,東南アジア,中南米等の諸国は,以上のような米国の海運政策の影響もあつて,自国商船隊の育成のため,多国間協定または三国間取極めにより,あるいは,国内法の規定や行政措置により,自国船の優先使用をはかる国旗差別政策をとり,また自国の輸出の伸長をはかるため,政府が運賃同盟に干渉するなどの措置をとつている。しかも,こうした動きは,これまで通常個々に行なわれてきたが,最近はエカフエ,国際貿易開発会議等の国際会議の場を通じて多数の低開発国が結集し,共同で伝統的な海運国に対抗する傾向が強まつている。
|