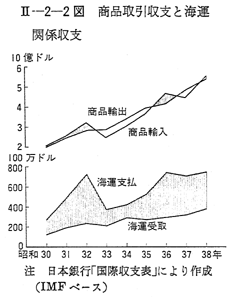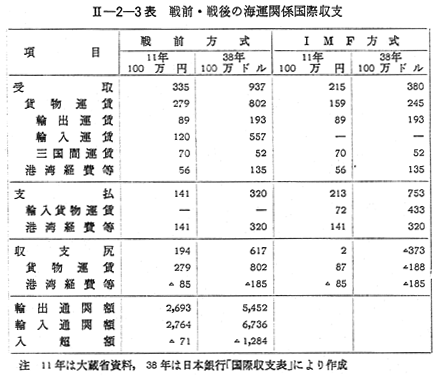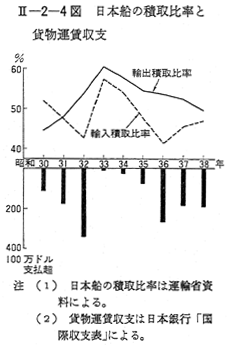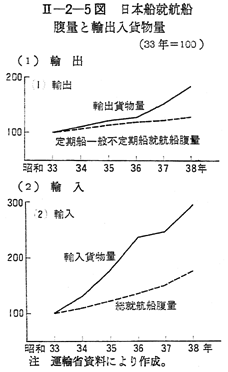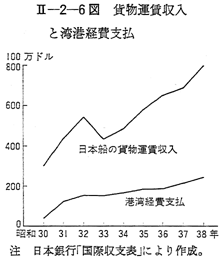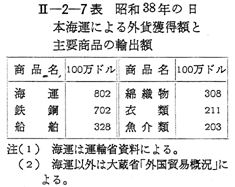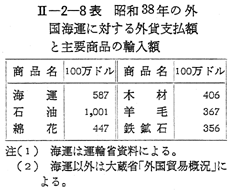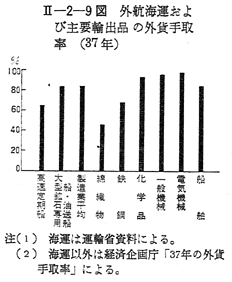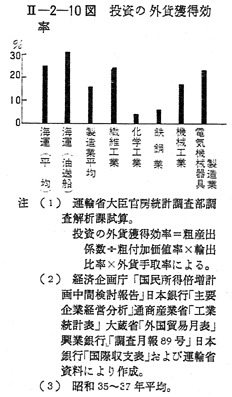|
2 国際収支に貢献する外航海運
(1) 海運関係国際収支の動向
わが国の国際収支は外国為替収支とIMF国際収支の2方式で公表されているが,海運関係収支について貿易および外航海運活動との関連で,その実体を把握しようとする場合には,商品取引と運賃とを別個に切り離して作成されているIMF国際収支による方が適切である。
IMF方式による海運関係収支は, 〔II−2−2図〕のように毎年赤字であり,昭和38年には3億7300万ドルの赤字となつた。海運関係収支の推移を受け払いの各項目別にみると,まず貨物運賃の受取(日本船による輸出運賃,三国間運賃)のうち,輸出運賃はわが国外航船腹の拡充にともなつて33年の1億700万ドルから38年には1億9300万ドルに増加している。また,三国間運賃は5000〜6000万ドルで横ばい状態にある。これに対して貨物運賃の支払(外国船による輸入運賃)は,日本船による輸入運賃節約額が2億5900万ドルから5億5700万ドル増加しているにもかかわらず,1億8500万ドルから4億3300万ドルへと大幅に増加しており,この結果,貨物運賃収支は33年の800万ドルの赤字が38年には1億8800万ドルの赤字に拡大している。
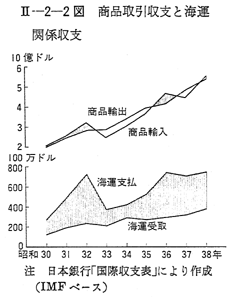
つぎに用船料収支は,わが国の貿易規模の急激な拡大により船腹需要が旺盛であるため,日本船の外国への用船はわずかで用船料の受取も38年において500万ドルであつたのに対し,逆にわが国の海運会社による外国船の用船が増加しており,これにともなつて用船料の支払が33年の1500万ドルから38年には5700万ドルに増大し,38年の赤字は差引5200万ドルに達した。港湾経費の支払は,外航船腹の拡充にともなつて増大するものであり,このうちの船用油の支払は33年の7000万ドルから38年に9600万ドルに増加している。港湾経費のその他の項目は,貨物荷役料,港費,船舶需品等で,年々8,000万ドル前後の赤字になつており,38年には受取6800万ドル,支払1億5000万ドルで8200万ドルの赤字であつた。
(2) 海運関係国際収支の赤字の原因
海運関係国際収支については,一般に戦前はその大幅な黒字が貿易収支の赤字をカバーしていたが,戦後は逆にその大幅な赤字が国際収支の足を引張つているといわれている。
昭和11年と38年の海運関係国際収支を比較すると 〔II−2−3表〕のとおりである。戦前方式により推算すれば38年においても6億1700万ドルの黒字で,通関ベースによる輸入超過額12億8400万ドルをかなりカバーすることとなり,逆にIMF方式により推算すれば11年でも黒字幅はわずか200万円にすぎないこととなり,戦前の海運の国際収支に対する功績を過大評価すべきではない。
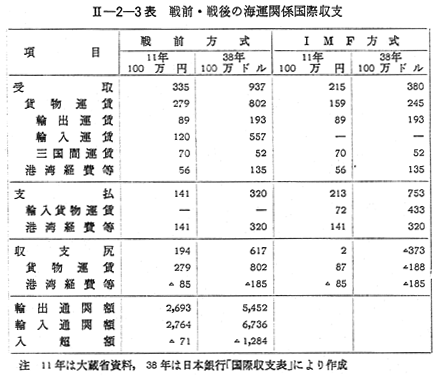
しかし,いずれにせよ,戦前黒字であつたのが戦後赤字に転じたのは,貿易構造の変化によるところが大きい。すなわち,わが国の輸出量と輸入量との比率は11年には1:25であつたのが,38年では産業構造の重化学工業化によつて鉄鉱石,石炭,原油等の工業原燃料の輸入が増大したため1:9に拡大している。しかも,貿易の地域構成は戦前の中国大陸を中心とした近距離地域から,現在はアメリカを中心としてヨーロッパ,南アメリカ,アフリカ等にその比重を高めており,輸入物資の平均輸送距離は,11年の3500カイリから38年には5800カイリヘと大幅に延びており,輸出についても,ほぼ同様の現象がみられるのである。
つぎに,商品取引と貨物運賃との関係をみよう。わが国は工業原材料を輸入し,これを加工して製品輸出をするという貿易構造をとつているため,輸出入物資のFOB価格に対する貨物運賃の比率が輸入の場合に輸出より大きくなつている。すなわち,38年には,輸出6.4%に対して輸入17.9%になつている。このことは商品取引の収支が均衡した場合においても,輸出貨物運賃額に対して輸入貨物運賃額が2.8倍であることから,もしIMF方式による貨物運賃収支を均衡させようとけるならば,日本船の輸出運賃収入と外国船への輸入運賃支払いが等しくならなければならないので日本船による積取比率を輸出,輸入同率として計算すれば,それぞれ73.7%にする必要があることを意味するものである。
そこで,日本船の積取比率と貨物運賃収支との関係をみると, 〔II−2−4図〕のように日本船の積取比率が最も高かつた33年でさえも輸出60.5%,輸入57.4%にとどまり,以来輸出積取比率は低下の一途をたどり,38年には49.6%となり,また輸入積取比率も35年に40%台におちこみ,38年にも46.9%にとどまつて低迷している。貨物運賃収支の赤字はこの積取比率の低下傾向を大きく反映して拡大しており,日本船の積取比率が低いことが,海運関係国際収支の赤字幅拡大の大きな原因となつている。そしてこの日本船の積取比率の低下は, 〔II−2−5図〕のようにわが国の貿易量の急増に対し,外航船腹の拡充がともなわなかつたことによるものである。また,用船料支払の増加も貿易量の増加に対して外航船腹量が不足していることによるものであるが,この不足を外国海運の輸送に直接委ねることにくらべれば,まだ外貨の流失を抑える効果をもつているのである。港湾経費については,現在日本船の積取比率が50%前後であるにもかかわらず,船用油を除く港湾経費収支が大幅な赤字になつているのは,わが国海運のもつ性格などほかの要因もあるが,わが国港湾における貨物荷役料,水先料,曳船料,けい船料,トン税等の港湾経費が,諸外国にくらべてかなり低位にあることが一因になつている。また,港湾経費の支払は 〔II−2−6図〕のように外航海運活動の拡大にともなつて増加するものであり,わが国外航海運の輸送活動が拡大し,輸出入運賃および三国間運賃の獲得が増加するにしたがつて港湾経費の支払が増加し,一方外国海運に支払う輸出入運賃が減少するとともに港湾経費の受取りが減少し,運賃収支が改善されるのと反比例して港湾経費収支は悪化するという性格をもつている。ちなみに,イギリス,西ドイツ等の欧州海運国においても港湾経費収支は大幅に赤字となつている。
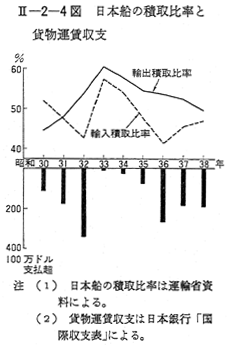
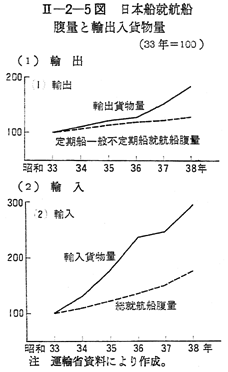
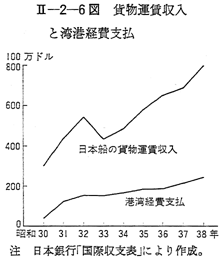
(3) 外航海運の国際収支への貢献度
IMF方式による海運関係国際収支においては,外航海運の運賃獲得額のうち輸出貨物運賃と一国間貨物運賃が貨物運賃受取に計上されているが,輸入貨物運賃収入も外国船への貨物運賃の支払を減少させる点で国際収支に貢献している。したがつて,外航海運の国際収支への貢献の度合をみる場合,輸出運賃,輸入運賃,三国間運賃を合計した運賃総額でみる必要がある。この外航海運による獲得運賃総額は,外航船腹の増強にともなつて年々増加し,30年の3億ドルから38年には8億200万ドルに達した。この運賃額は,38年の商品輪出額にくらべると 〔II−2−7表〕のとおりで,外航海運の外貨獲得による国際収支への貢献の度合がきわめて大きいことを示している。一方,外国海運に支払つた運賃総額は38年には5億8700万ドルに達し,これは38年の商品輸入額にくらべると 〔II−2−8表〕のように多額であり,貨物運賃支払いの節減がいかに重要であるかを示している。
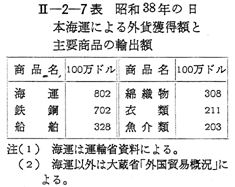
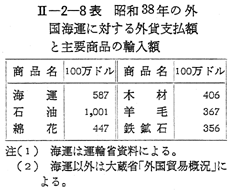
さらに,以上のような外貨獲得額に対して外貨手取率はどうかをみると, 〔II−2−9図〕のように外航海運の外貨手取率は高速定期船では65%程度,大型鉱石専用船,油送船で84%程度であり,輸出商品にくらべて必ずしも高いとはいえないまでも,決して低いものではない。
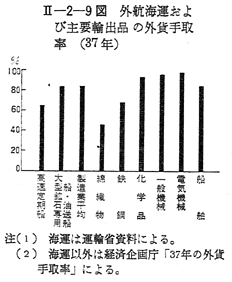
つぎに,設備投資による外貨獲得効率をみると, 〔II−2−10図〕のとおりで,海運業が最も高くなつている。しかも,商品輸出が国際輸出環境によつて大きく左右されるのにくらべ,海運はわが国の貿易に依存しており,かつ現在積取比率が必ずしも高くなくその向上が期待できるだけに,今後とも国際収支の改善に果す役割はきわめて大きいものがある。
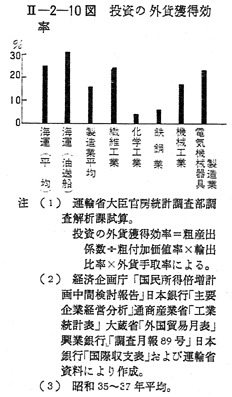
|