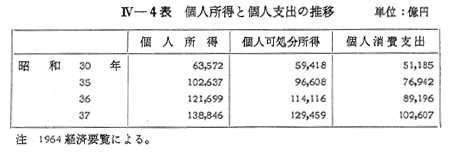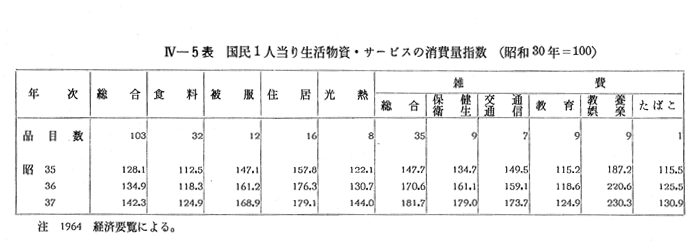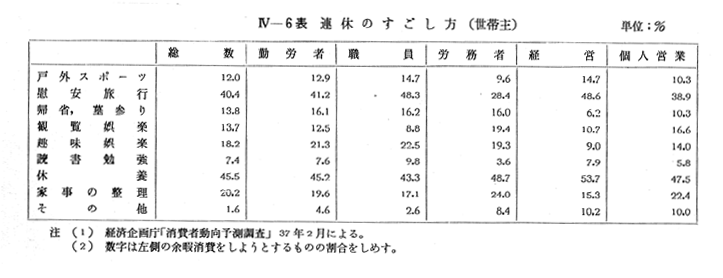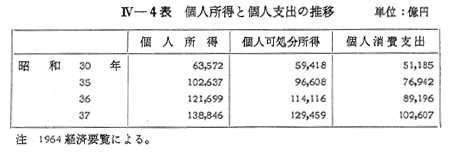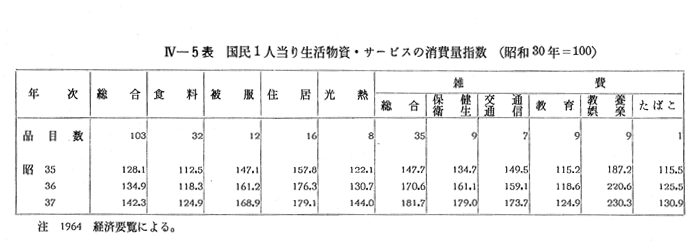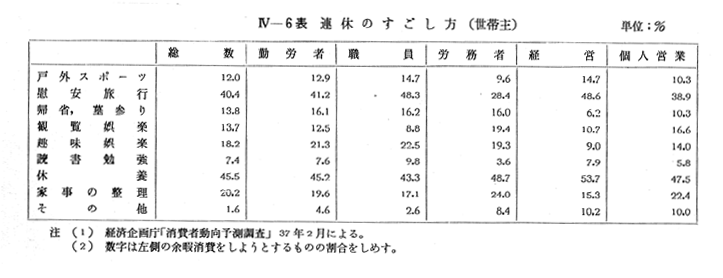|
2 国内情勢の変化
観光は,従来ともすれば,物見遊山的なものとしてぜいたく視される傾向にあり,国民生活において観光の果たす役割の重要性もとかく見失なわれがちであつた。
しかし,近年のわが国における著しい経済成長に伴い,人口の都市集中の激化,労働形態の変化等の現象が著しく,社会生活における緊張の度合も塔大し,いかに緊張を緩和するかが大きな問題となつており,観光に対する考え方も変化しつつある。つまり,国民の余暇のすごし方が「ひまつぶし」という消極的なものから,観光旅行,スポーツ等による積極的な利用へと,特に若い世代を中心に移り変つてきている。
いまや,観光は国民生活の一部となり必需化するとともに,観光旅行への意欲がたかまつてきている。
近年,観光旅行者が著しく増加している背景には,経済成長がもたらした国民所得の増加,それに伴う個人の消費構造の変化,労働時間の短縮による余暇時間の増大とがあるわけである。
ここで,近年の個人所得の伸びを 〔IV−4表〕によりみてみると,昭和37年度は13兆8846億円に達し,前年度に比し,14.1%の増加で昭和30年度の約22培になつている。
一方,余暇時間については,NHKが行なつた調査「日本人の生活時間の変化」によつてみると,その変化が最もきわだつている農業従事者の場合は昭和16年は,余暇時間は1日平均2.29時間であつたが,昭知35年には5.15時間と倍増している。
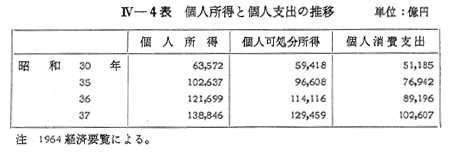
家庭主婦,職員,労務者についても余暇時間は,5時間を超えており,二重計算その他の統計方法の違いによる誤差を差引いても,大幅に増加したことがわかる。
所得の増加と余暇時間の増大とが,観光旅行者の増大をもたらしたと考えられるが,まず旅行した実績を「消費者動向予測調査」でみると,世帯別にみて,1泊以上の慰安・観光旅行をした世帯は昭和33年8月(調査時から過去1年間)には,43.9%であつたが,6年後の39年2月には58%,その平均回数は2.7回と急激に増加している。次に,国民一人当り生活物資,サービスの消費量指数(昭和30年を100とする)は,〕表のとおりであり,昭和37年には,総合は142.3であるが,旅行,スポーツ,映画,演劇等に関する消費,いわゆる余暇消費が含まれている雑費は,181.7であり,そのうち交通通信,教養娯楽はそれぞれ173.7,230.3という指数を示している。
また,休日のすごし方を37年8月の「消費者動向予測調査」によりみると,世帯主については,休日を旅行によりすごそうとしたものは,5.6%にすぎないが,連休のすごし方についてみると 〔IV−6表〕のようになる。これによると,休養によりすごそうとしたものは,やはり一番多いのであるが,旅行によりすごそうとするものが,普通の休日の場合に比べて,かなり高い数字をしめしている。このことから,すでに一部の大企業で実施されている連続的な休暇制度が普及するにつれて,観光旅行者はさらに大幅に増加することが予想される。
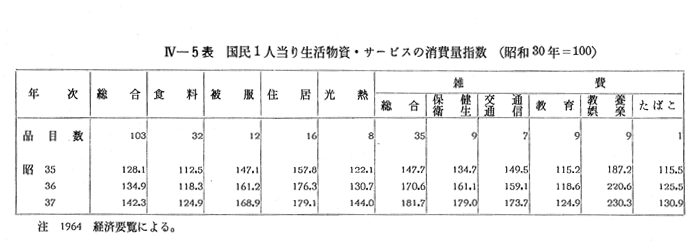
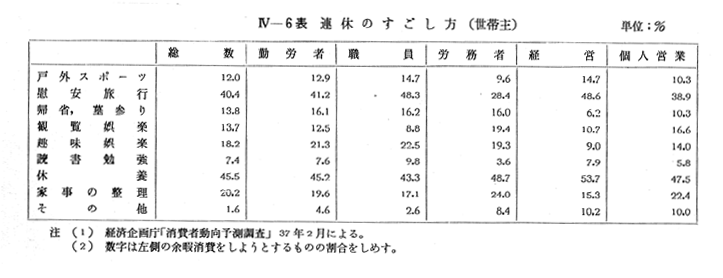
|