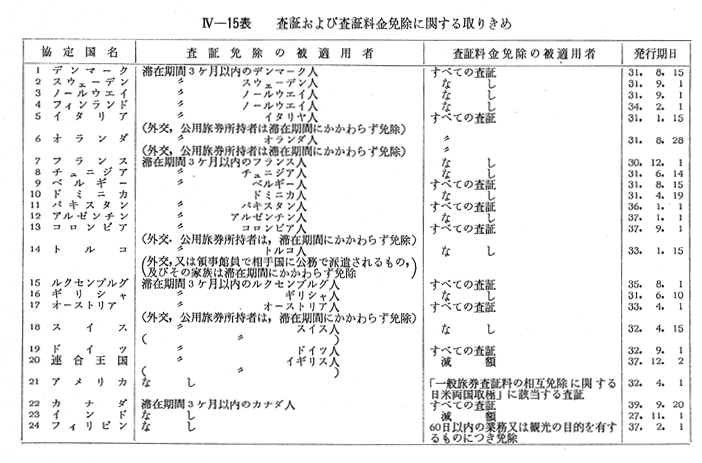|
3 外国人観光旅客の出入国に関する措置の改善
外客が,観光旅行の意欲をもつた場合にも出入国手続きがはんさであれば,その旅行目的国を変更し,あるいは旅行それ自身をとり止める等,外客の誘致に当たつて出入国手続きの難易さが影響するところは非常に大きい。
したがつて,観光収入を重視する国においては,出入国手続きが簡略化されているのが,普通であり,出入国手続きの難易さが,その国の国際観光に
対する考え方の一端を示しているということができる。
現在,出入国手続きに関する世界の大勢は,これをできる限り簡易かつ迅速なものにしようとする方向にむかつて進んでいる。このことは,昭和38年9月ローマにおいて開かれた国際旅行および観光に関する国際連合会議においてその簡易迅速化を図るよう各種の勧告が行なわれたことにもうかがえるところであり,また,本年わが国が加入したOECDにおいてもその前身であるOEEC時代からこの問題にとり組んでおり,出入国手続きの簡易迅速化に関する多くの規約を定めている。
この出入国手続きとして問題になるのは,(1)旅券,査証および入国審査に関する手続き,(2)通関に関する手続き,(3)自家用自動車の一時輸入に関する手続き(4)検疫に関する手続き,(5)通貨および為替に関する手続き等についてである。
(1) 旅券,査証および入国審査に関する手続
外国人旅行者は,原則として入国しようとする国の領事官等の査証を受けた有効な旅券を所持していなければならず,さらに,上陸しようとするときに,上陸の許可を受けることを求められる。
わが国の場合には,このような原則どおり,来訪する外国人は有効な旅券を所持していなければならないとされる。この点について,最近,ヨーロッパのOECD加盟国においては,相互協定により,旅券の代用として,身分証明書やツーリストカードなどを認め,また団体旅行について団体旅券を認めることが広く行なわれており,わが国においても団体旅券や身分証明書等の効力の承認について,近隣諸国の状況を考慮しつつ,検討する必要があろう。
次に,わが国においては,外国人が所持する旅券は,原則として日本国領事官等の査証を受けたものでなければならないものとされている。なお査証の有効期間は,在留資格により異なるほか,相手国によつても異なつているが,いわゆる観光客については,4カ月が原則的なものである。また同一の査証によつて入国できる回数は,一般に一回である。このような原則に対して例外の第一は,わが国が査証の相互免除協定を結んでいる
国からの入国者は査証を必要としないものとしていることである。なお, 〔IV−15表〕にみられるように,昭和39年10月現在,わが国が相互免除協定を結んでいる国の数は21カ国である。
また,ドイツ,カナダ,アメリカなどの特定の国の者については,査証の有効期間内(アメリカについては48ケ月)である限り何回でも入国できることとしており,これらの国からの再入国者に対しては査証のそれぞれの有効期間内は査証を免除したのと同様の効果を有している。
一般に査証はその取得手続きがかなり簡略化されたとはいえ,観光旅行者の旅行意欲をそぐものであるから,国際観光振興上できる限り廃止すべきであり,その意味で相互免除相手国数のできる限りの増加をはかることは有効な施策の一つである。またわが国への来訪数の一番多いアメリカに対しては再入国者の査証についてのみ特段の扱いをしているだけであり,きわめて不十分な状態である。アメリカ政府が相互免除協定を結ぶ意思のない現在,いつまでも単なる伝統的な相互主義にとらわれることなく,一方的に査証を免除してアメリカ人観光客のよりいつそうの誘致を図るべきであろう。なお,この点については,ヨーロッパのOECD加盟国相互間において,国際観光振興の観点より査証はほとんど廃止されているほか,アメリカおよびカナダの観光客に対しては,アイスランドを例外として,ヨーロッパのOECD諸国のすべてが一方的に査証を廃止していることが注目される。第二の例外は,いわゆる一時上陸客と通過上陸客についてで,これら入国者も査証は不要とされている。一時上陸客とは乗つている船舶,航空機が同一の出入国港にある間72時間以内に限つてその近傍に上陸する者で,「寄港地上陸の許可」を受ければよいとされている。また,通過観光客とは,船舶に乗つている外国人が,その船舶が本邦で一の港から他の港に移動している間,15日間以内に限り一の港から上陸して観光を行ない,他の港で帰船する者で,この場合には「観光のための通過上陸計可」を受ければよいとされている。この観光のための通過上陸許可の制度は周遊観光船,定期旅客船の乗客にきわめて多く利用されており,便宜な制度となつている。しかしながら「寄港地上陸の許可」については,船が
旧本の港に着くたびに何度でも同許可を受けなければならずはんさにたえないという苦情が強く,「観光のための通過上陸の許可」の制度については国際交通機関のスピード化に伴いいわゆる気まぐれの客が増加するりに対処して,同制度を同一の船に乗船する客のみならず,飛行機相互間あるいは船と飛行機相互間を乗り継ぐ短期の観光客にも適用するべきであるとの声が強い。なお,査証料金について,現在アメリカ等12ケ国と査証料金相互免除協定を,またイギリス等二ケ国と査証料相互減額協定を結んでいるが,この相手国数の増加を図ることはもちろん望ましいことである。
わが国へ入国するための前述の形式要件をそなえた外客も,わが国に入国するに当たり最後に旅券および査証に関する要件を具備しているかどうか等について出入国港で入国審査官の審査を受けなければならないことになつている。この審査に当たつては,出入国記録カード(EDカード)の提出が必要とされている。諸外国においては,この出入国カードは,国際民間航空機構(ICAO)の勧告したものを採用しているが,わが国のものはかなり記入すベき項目が多く複雑であるので,できる限りその簡易化が望まれている。また従来周遊観光船の入港時等一時に多数の外客が来訪する際に審査に長時間を要する等の苦情が多く,出張臨船審査の実施,審査要員の増強,審査方法の簡素化等が望まれていた。この点について,昭和37年,38年度において三回にわたり海外出張審査を行ない,また,法務省入国管理局,羽田間にテレックス1台を設置し,その間の連絡を密にする等問題はやや改善されつつある。また,本年は,オリンピック東京大会に備えて入国審査官の増援,大型観光船に対する出張臨船審査が実施された。
(2) 通関に関する手続き
通関については,1954年は国際連合会議が開催され,「観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約」と「観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約に追加された観光旅行宣伝用の資料の輸入に関する議定書」が決定採択された。今日わが国も,この二条約に加入しており,旅行者は携帯品として一定限度額までの宝石,写真機,撮影機等を免税で持ちこむことができ,また,私用に供するための一定量のたばこ類,ぶどう酒,化粧水等の身回り品も免税で持ち込むことができることとなつている。この携帯品および身回り品で免税対象となつている品目および数量は,各国において多少異なるが,わが国の場合は国際的に見てほぼ妥当なものということができる。また,携帯品および身回り品以外の物品については,外客が自分で使用するために持ち込む自動車,船舶又は航空機であつて,その持ち込みの許可の日から1年以内に持ち出されるものは,その関税を免除する(自動車については(3)参照)こととされている。検査手続きについてのわが国の現状は,外国人が入出国するときは携帯品については口頭申告としているが,別送品があるときは書面を提出させている。口頭申告されたものについては,観光客の場合はきわめて簡単な抜取検査によつており,あまり間題はない。しかしながら,出国の際に物品税の免税物品を購入しているときは,輸出免税物品購入記録票に記載されている物品を携帯しているかどうか照合するため,一々荷物をほどく点に,旅客からの苦情が多く抜取検査方式または販売店からの直送方式の採用等,なんらかの簡素化措置をとることが望まれている。
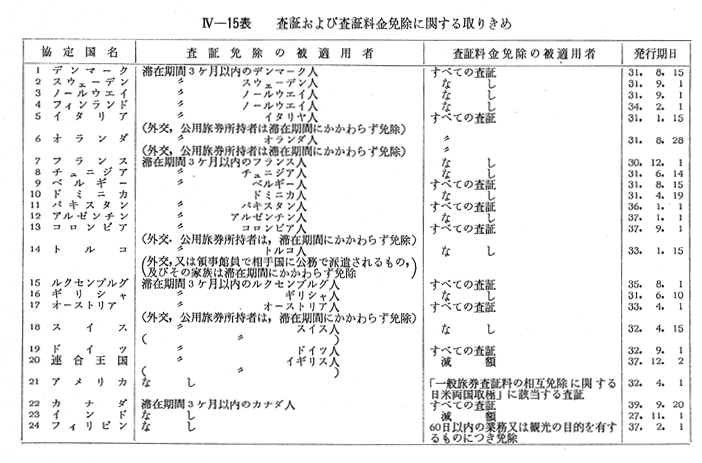
(3) 自家用自動車の一時輸入に閥する手続
世界的にみて,自家用自動車による観光旅行は多く,観光客が容易に自動車を持ち込み運転しうる制度が必要となつてくる。この点に関し「自家用自動車の一時輸入についての通関に関する条約」,および「道路交通に関する条約」があつて持ち込みの容易化と運転免許証,道路標識,車両番号等の標準化が図られている。特にヨーロッパ諸国では,自動車による国境の通過は,一時輸入証明書により,輸入税を納付することもなく,きわめて簡単に持ち込むことができ,また運転免許証や車両番号等は自国のものがそのまま有効であり,道路標識等も統一されている。しかるに,わが国は,従来,これらの条約のいずれにも加入しておらず,観光客の自動車の持ち込みや運転免許証等については,きわめて厳しい規制が行なわれており,道路標識等は世界のものと異なるものを実施していた。特に自動車の持ち込みについての規制は,20数種類の書類が必要とされるほか,輸入税(関税および物品税)の合計額を税関に担保として提出しなければならない等厳しいものであつた。現在のところ自家用自動車の持ち込みは年間10件余にすぎないが,これは,一部ではわが国が他の大陸と陸続きでないという事情にもよろうが,持ち込みに関するわが国の厳しさにも大きな原因があると思われる。
しかし今後,自家用自動車を持ち込み,あるいは持ち込まない場合でもレンターカー等を利用して国内を自動車で旅行しようとする外客も増えることが十分予想され,これらに関する規制も緩和ずる必要があるところから,わが国は,「自家用自動車の一時輸入についての通関に関する条約」,「道路交通に関する条約」の二条約を昭和39年5月20日に承認するとともに,これら二条約を国内的に実施するため,自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律,道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の制定および道路交通法の改正等関係国内法令の制定改正を行なつた。上記二条約およびこれに伴う三法律は本年9月6日から発効,施行された。
新しい法令によると,外客の自家用自動車の持ち込みおよび国内における自動車の使用は,次のような手続によることになつている。まず自家用自動車の持ち込みは,その自動車が自家用に供され,かつ,一時輸入の許可後一年以内に国外へ持出されるものに限り,その輸入に際し,保証団体の承認を受けた一時輸入書類を税関に提出すれば,許可され,輸入税(関税及び物品税)が免除される。当該車両を,先に述べた条件に反し、自家用以外の用に供した場合は,その者および関係者は輸入税を徴収さ札また,期限内に国外に持出さなかつた場合には保証団体が,輸入税を徴収される。また,一時輸入の手続きを経て輸入された自家用自動車について,自国で受けた車両検査および車両番号は,輸入の許可後一年間はわが国において有効とされる。さらに道路交通条約締結国の国民の所持する国際運転免許証は,その所持者の上陸後一年間はそのまま国内的に通用する。これにより自家用自動車の国内持込みおよび自動車の国内使用に関するわが国の取扱いは,国際的な水準に達したものといえ,今後のわが国の外客誘致政策に寄与するものと期待されている。
(4) 検疫に関する手続き
検疫に関する手続きについては,国際衛生規則が定めており,わが国も同規則に従つて行なつているため,手続きについてとくに不便である等の問題はない。ただ,わが国の場合,外国と社会慣習などが異なるため,わが国が行なう検疫方法について問題が生じる場合もあるので,このようなことのないよう十分な配慮をすることが望まれる。
(5) 通貨および為替に関する手続き
世界的にみて,外国人の通貨の持込みと持出しについての制限は,廃止の方向に進んでおり,持込みと持出しがまつたく自由であるか,または持込んだ額(申告額)までの持出しは自由というのが通例である。
わが国の場合,旅行者が日本国および外国銀行券,旅行小切手等の対外支払手段を携帯して持込むことは税関の確認を受けるだけでその額に制限なく認められており,一方持出しについては,日本円は船舶又は航空機内で使用する目的で2万円まで認めら札外国銀行券旅行小切手等の対外支払手段は,税関の確認を受けるだけで無制限に認められている。また,外貨を交換して得た日本円の外貨への再交換限度額は,従来1人1回100ドルに制限されていたが,昭和38年11月,外貨を交換して得た円貨の範囲内であれば,出国時1回限り為替銀行又は両替商(外貨の保有を認められている両替商に限る)において金額に制限なく外貨への再交換ができることに改められた。この場合100ドル相当額をこえる場合に限つては,当初両替に際して為替銀行又は両替商から交付を受けた「対外支払手段買取記録書」の提出を要することとなつている。
なお,両替を行ないうる機関は,外国為替公認銀行の外国為替取扱店舗および認可を受けた両替商に限られており,これらの数は全国で約1,300余にのぼつている。
|