|
3 地域経済と旅客輸送
旅客の地域流動と地域経済構造との関係をみるため,全国を,貨物の場合と同様 〔1−1−9表〕に示す15地域に区分し,地域内および地域相互間の流動量をまとめてみると 〔1−1−25図〕のようになる。
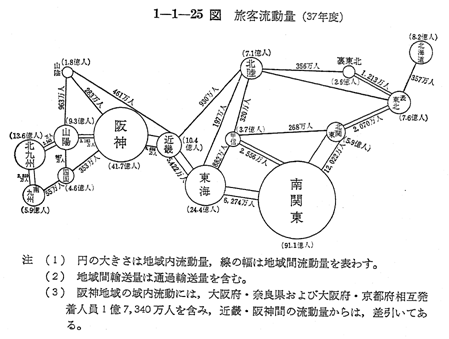
流動量の大きい区間は,地域内では南関東ブロック内(総流動量の約40%),阪神ブロック内(全体の約20%),東海および北九州ブロック内(それぞれ全体の約10%)等であり,産業や人口の集中する大都市周辺において輸送量も著しく高いことを示している。これに対し,地域間の流動は,表東北から北九州にいたる太平洋岸ベルト地域に集中している。
近年,太平洋岸ベルト地帯への人口の流入は増加しており,とくに首都,京阪神,中京の三大交通圏への流入は著しく,なかんずく都市周辺部へ集中している。その結果,都心の昼間人口は激増し,通勤・通学時における混雑の原因となつている。

三大交通圏における輸送機関別の輸送量を37年度と38年度とを比較すると 〔1−1−27表〕のようになり,総輸送量は,38年度において,首都圏95億6,253万人,中京圏15億1,251万人,京阪神50億3,918万人となり,対前年度比それぞれ8%,11%,7%の増加を示している。

|