|
1 輸送基礎施設および可動施設の近代化輸送施設には基礎施設と可動施設とがあり,近年の大量高速輸送の需要に応えて,それぞれの分野で近代化が行なわれてきている。
輸送力不足の解消に主眼をおいて,基礎施設としては物資流通の中心となる都市,又は産業地帯に貨物営業拠点駅として高速貨物車の発着拠点を設け,高速列車の発着設備,コンテナおよびパレット輸送に適した荷役設備,出荷波動対策のためのストックポイントの設備等をもつた近代的貨物駅が考えられている。
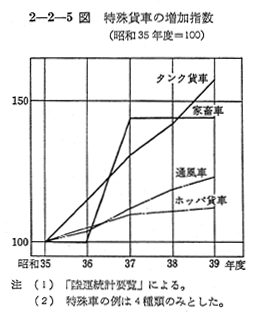
基礎施設の道路としては大型車の採用,高速輸送に適した高速道路の建設がめざましい。昭和40年7月には名神高速道路が全面開通し,中央高速道路,東名高速道路,首都高速道路,阪神高速道路等と計画又は着工されており,将来は高速道路が国の道路体系の中核となつて現在の国道が高速道路網の下に再編成されることも考えられる。高速道路とともにトラックターミナルの姿が浮び上がつてくる。39年11月にはターミナルは一般,専用を合せて1,683個所設置されているが,規模の小さいものが多い。最近は15〜20バース程度のものが増加してきている。このトラックターミナルは幹線輸送と集配を分離するためのトラック輸送の必須要件であるばかりでなく,流通センターの一部としての機能をもち,倉庫等と一体となつて経済的効果をより高めることができる。たとえば,東京都外周部に数カ所の総合的トラックターミナルを建設する予定であり,日本自動車ターミナル(株)により,40年度には第1号として板橋地区に流通センターの核としてのトラックターミナルの建設に着手する。
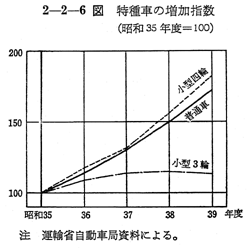
海上輸送における基礎施設としての港湾は専用船,大型船の出現,地域開発の中心としての役割,過密地帯の流通の合理化といつた必要性に対応して近代化が行なわれている。すなわち,大型岸壁,新しい総合埠頭経営としての定期船埠頭,石油,鉄鋼などの港湾にみられるような近代的施設などの建設である。しかし,このような質的な近代化に対して量的には横浜,神戸港等の6大港においては,入港船舶の1割強が沖待ちを余儀なくされている現状を見逃すことはできない。
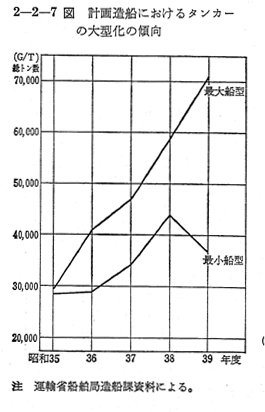
また,内航船については 〔2−2−8図〕にみられるように専用船が増加している。
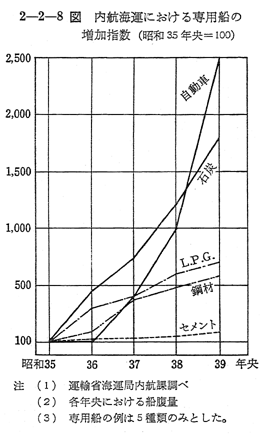
航空貨物は毎年約30%という大きな増加率を示している。輸送品目についても従来は緊急輸送の必要性がある書類,印刷物,機械部品等が多かつたが,最近は生鮮食糧品の輸送も目立つてきている。基礎施設としての空港は輸送需要の増加に伴い航空機の大型化,高速化(ジェット化),および運航回数の増加に対処するために,適正な運航管理も含めた整備および近代化が進められ,滑走路,エプロン,ターミナルビル等の新設および改良が行なわれている。
|