|
2 荷造包装の標準化
荷造包装を標準化,規格化することによつて物資流通経費を節減し,物的流通の近代化,合理化を図ることを目的として,国鉄では昭和33年10月に荷造包装標準化委員会を設置し,荷造包装の標準化を試み,後述するような実績をあげている。また,通運事業者も関係業者との連けいのもとに荷造包装の標準化増強運動を40年3月より展開し,鉄道貨物協会においてもこの問題に取り組み,日本包装技術協会も38年設立以来,包装技術の向上改善のために努力してきたが40年6月から包装標準化推進運動を実施している。
荷造包装標準化による物資流通経費の節減率は 〔2-2-24表〕に示すように荷造包装費では缶詰およびみかんで約13%,電気冷蔵庫で約17%の節減になり,荷造包装費,運賃および通運料金の合計では約10%の経費を低減することができる。
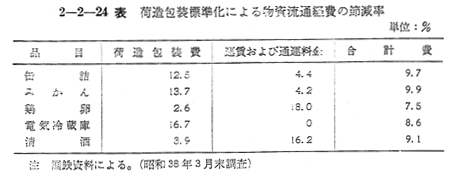
貨物の軽量化,手かぎ使用の禁止,肩荷役の禁止等により貨物事故が減少した。たとえば鶏卵の破損率は標準化前には約1%であつたが,標準化後には0.02%と大幅な減少を示している(国鉄資料よる)。また,みかんの品質保持の面に例をとつても,従前の木箱の場合には,一箱にできるだけたくさんつめこむ傾向があり,いたみものも多くあつたが,統一規格による段ボール箱においては,機械的な流し込み方法がとられ,大きな改良効果が見られる。
貨物の寸法,重量等が一定し,また,まとめやすい姿となるのでフォークリフト等による荷役の機械化およびパレチゼーションが推進された。
かん詰,マーガリン,果物等の包装の標準化については業界が多年努力したにもかかわらず業界のみの力では達成できなかつたが,荷造包装標準化委員会の審議を通じて包装規格が制定され,材料,寸法,デデイン等の統一が行なわれた。
|