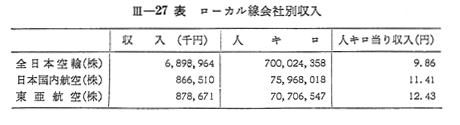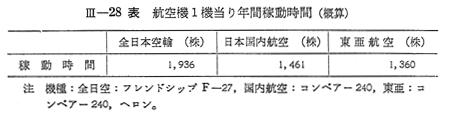|
2 収支状況
まず,日本航空(株)については,39年度下期以後,前述のとおり,東京-大阪線を中心とした大幅な需要減(利用率下期平均65.8%)に見舞われたが,上期の好調(利用率上期平均79.4%)に支えられて,年間経常利益で18億94百万円(特別償却及び税金引当等の特別損益を含まない)を計上し,前年度に引き続き好調であつた。
しかしながら,これも上期の異常な高利用率によつて可能となつたもので,下期以降の幹線需要の減退に際しては,日本航空(株)が全日本空輸(株)よりもはるかに手痛い打撃を蒙つていること,また,今後急速な需要の立ち直りが期待薄であることを考えるとき,同社の今後の幹線運営については,十分の配慮が必要であろう。
39年度の同社国内線総収入は163億47百万円で対前年度比15%増,総費用は144億53百万円で14%増であつたが,有償トンキロ当り総収入は,前年度が136.47円であつたのに対し139.95円と2.6%向上した一方,有効トンキロ当り総費用は,前年度の81.86円から78.89円と3.6%減少した結果,損益分岐利用率は,前年度の60%から56%に低下している。
有償トンキロ当り収入の増加は,主としてジェット機利用客の増加によるジェットサーチャージの増収によるものと思われ,また,有効トンキロ当り費用の減少は,燃料及び保険料単価の減等によるもので,国際線に比較してコスト減の幅が少ないのは,国際線においては,席数増加によるコストダウンが可能であつたが,国内線については,ほほ限度一杯増席しているため,この面における合理化ができなかつたためであろう。
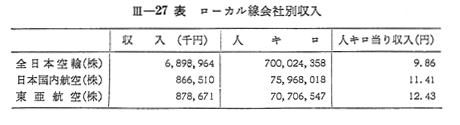
全日本空輸(株)については,39年度もおおむね前年度とほほ同様の好調を持続した。すなわち39年度では税引前利益として624百万円(38年度は603百万円)を計上した。同社の営業収入は13,472百万円で対前年度31%増(内幹線収入は17.0%増,ローカル線収入44.4%増)であつたが営業費用は事業費が30%増に留まつたのに対し販売費一般管理費は40%増となつたことが注目される。39年度の同社の営業状況の特色はまず幹線で日本航空(株)と対照的な成績となつたことである。すなわち利用率についてみると,東京-札幌線で同社は61%(日本航空(株)は78%)であるのに対し東京-大阪線では同社は79%(日本航空(株)は70%)であり特に東京-札幌線の低調は同線がチャーター機による高コスト路線であつたことと相まつて恐らく同社の収支にマイナスの影響を与えることとなつたものと思われる。また39年度中に開設された東京-山形,東京-米子,東京-北九州,名古屋-福岡,東京-鹿児島,東京-熊本,大阪-福岡の諸線の利用状況は東京-熊本を除けば,いずれも開設初年度のため低利用率(60%以下)であり経営の圧迫要因となつたものと思われる。いまこれらの年度途中新規開設路線を控除した場合には既存ローカル線の利用率は76%に達するものと推定され,現時点においては,その路線構成が他のローカル会社と比較して相対的には極めて優れていると認められる。従つて今後これら新規開設路線が成熟するとともに東京-札幌線における利用率の回復上昇と同線における購入機運航によるコスト低下により同社経営の着実な発展は今後も充分期待できるであろう。ただ,東京-大阪線のウエイトは同社においてもこれまで相当重要であつたので(39年度で同線収入のウエイトは約25%)今後東海道新幹線の影響如何が問題であるが,幸い同社同線の旅客数は前年同月対比で40年4月は約10%増,同5月で約18%増と良好な傾向を見せており,多くの自社ローカル線と接続する有利性を考慮すれば今後必らずしも悲観すべきものではないであろう。
次に日本国内航空(株)であるが,同社は発足以来のこの1年間に1,580百万円(上期667百万円,下期914百万円)の赤字を生じた。同社の路線は比較的北方,或は裏日本に偏しているが,下期の大幅な赤字増加は季節的に運航不能又は需要沈滞期に入つたこと及び幹線参加のための開発的経費が増加したことに求められるであろう。同杜の路線は一般的に利用率が極端に悪いが(年間平均51%)いま同社が昨39年度に運航した路線(幹線及び採算性が極めて悪い水上機路線並びに運航廃止した路線を除く)が寄航した都市は17都市であるが,うち一般に低開発地域とされる裏日本,東北,北海道方面の都市は12に上り,しかも,これら関係ローカル路線21路線(途中区間も含む)中東京又は大阪発着のものは僅か6(うち3は裏日本及び東北地方)にすぎない。このように低開発地域への路線が多いこと,東京,大阪と地方都市を直行便で折返す路線が少ないことは同社路線の集客力が貧困なことの有力な一因であろう。また路線寄航地が上述の如き低開発地域に集中していることはとりもなおさず冬季の自然条件悪化或は需要の極度の悪化による休航を余儀なくされることであり,これは航空機稼動率の悪化ひいては運航原価の上昇をもたらすこととなる 〔III−28表〕このような同社路線網の特殊性は収入面経費面でのマイナス要因として相乗的に作用しており,今後の同社の再建過程において問題となるものであろう。なお,路線網以外の問題として39年度の場合のみについて言えば同年2月の大分の事故のため同社の主要路線である東京-高松-大分-鹿児島線が利用率極めて悪く,長大路線であるために赤字要因としても大きく作用したことは否めない。
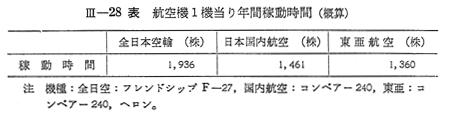
東亜航空(株)は決算期の改正(2期決算→1期決算)のため39年7月1日→40年3月31日の9カ月間決算であつたが今期は55百万円の赤字計上に留まり次期へ424百万円の欠損を繰越すこととなつた。同社の利用率は39年度後半より著しい上昇(上半期と下半期を比較すると約50%増)を示しているのが特徴である。
|