|
2 経営状況
ホテルの収入は宿泊料と飲食料が主であつたが,近年の用地費,建設費の高騰によつて,新設ホテル等は一定限度の収益しかあげ得ない宿泊部門より,収益性に弾力のある飲食部門その地部門に力を入れるようになつてきている。すなわち,「宿泊収入」の総収入に対する割合は, 〔IV−30表〕にみられるとおり全国平均で,昭和35年には30%であつたのが38年には26%と逐年減少している。一方,「飲食収入」の割合はあまり変らず,また「その他収入」の増加は著しく,38年度には宿泊収入にほぼ匹敵するまでになつている。これは,ホテルに付随した送迎用自動車,プールその他の施設の兼業に乗り出した結果と思われる。
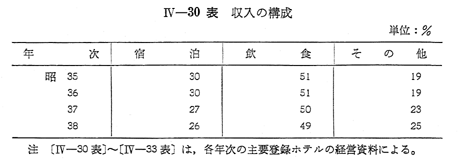
次に,収入に対する支出の割合をみると,35年には全国で96.1%であつたものが,37年には97.1%,38年には99.8%と次第に増大している。
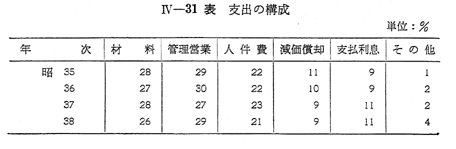
次に,ホテル業の資産の特性は,固定資産の割合が極めて大きく, 〔IV−32表〕にみられるとおり,総資産の86%以上となつていることである。これはいうまでもなく,建物自身を経営の母体とし,客室を売物として営業を行なつているためである。これは公共制の強い,電気,ガス,鉄道業等に近い資産状況である。
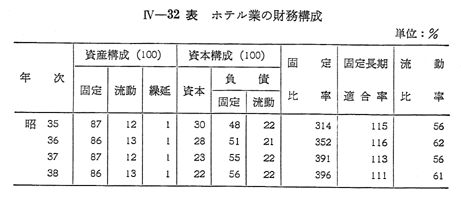
資本構成も 〔IV−32表〕にみられるように,35年には,自己資本は30%であつたものが38年には22%と急激に悪化してきている。
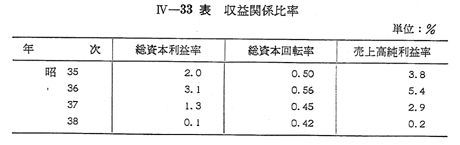
従つて,前述のとおり,ホテル本来の宿泊およびこれに伴う飲食収入では充分でないので,都市ホテルでは宴会場,バイキング,中華料理等の食堂経営,結婚式場の経営等を行ない,リゾートホテルではさらに進んで,プール,海水浴施設,ゴルフ場,スキー施設の兼営に力を入れている状況である。
|