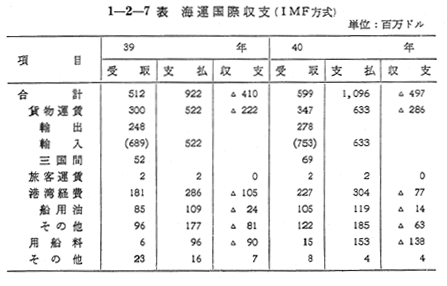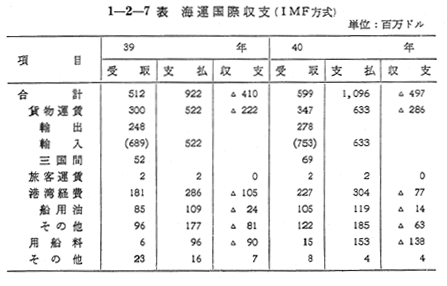|
2 海運関係国際収支
昭和40年の海運関係国際収支(IMF方式)は 〔1−2−7表〕に示すとおり,受取り5億9,900万ドル,支払10億9,600万ドルで,収支は4億9,700万ドルの赤字となった。これは前年の4億1,000万ドルの赤字よりさらに8,700万ドル悪く,赤字幅は最近において最も多かった36年の4億5,200万ドルを上回った。
貨物運賃は,受取りが輸出運賃2億7,800万ドル,三国間6,900万ドルとなり,前年度に比べて4,700万ドル増加したが,支払額が6億3,300万ドルと前年度に比べて1億1,100万ドル増加し,この結果,貨物運賃収支は,前年度より6,400万ドル悪化して2億8,600万ドルの赤字となった。
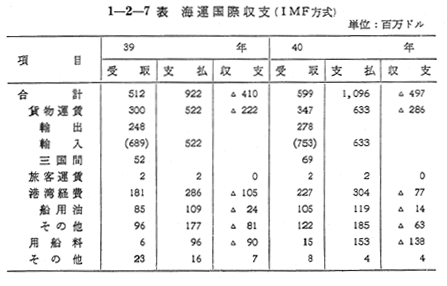
用船料は,外国船の用船が大幅に増加したため,前年度より4,800万ドル悪化して1億3,800万ドルの赤字となった。
船用油については,受取,支払とも幾分増加して,収支は前年度に比べて1,000万ドル改善され,1,400万ドル赤字となった。
その他の港湾経費については,38年から39年にかけて岸壁使用料,水先料などが引上げられ,また外国船の入港数の増加などにより,受取りが39年より2,600万ドル増加して,1億2,200万ドルとなり,収支は1,800万ドル改善されて6,300万ドルの赤字となつた。
このように40年は,港湾経費が前年より改善されたにもかかわらず,貨物運賃および用船料の大幅な赤字増加が,全体としての海運関係国際収支の著しい悪化をもたらした。
IMF方式による貨物運賃の国際収支は,わが国海運による輸出貨物輸送および三国間輸送運賃収入と,外国海運に対する輸入貨物輸送運賃の支払とによって決定される。しかるに,わが国の貿易は輸入貨物の大部分が原油,鉄鉱石,石炭その他の工業原料で占められ,輸出貨物は主として工業製品であるため,輸入量は輸出量の約8.5倍となっており,しかもその過半が外国船舶によつて輸送されている。40年は,輸入量の増加に加えて,ベトナム紛争,ソ連・中共の小麦買付けなどにより海運市況が堅調であったため,支払運費が大幅に増加した。そしてこの支払運賃の増加が,輸出の増加1隻当りの積み高の増加,運賃の値上がりなどによる受取り運賃の増加を七回り,かつ,外国用船の増加が,支払用船料を増加させたため,海運収支を悪化させた。なお,40年11月からの海運争議が海運国際収支に与えた影響は相当大きく,約3,500万ドルの外貨が流出したといわれている。
40年度には,海運助成策の奏効等による海運企業の国際競争力の強化と輸出貿易の増大を背景として,定期船の大幅な増強と鉄鉱石需要の増大,ならびに濠州,ブラジル等の新規鉱山開発など輸入ソースの変更等に対応した専用船の大幅な増強が図られたほか,油送船を中心とする三国間輸送用船舶の建造が推進された。
40年度の開銀融資による造船計画は,当初計画の150万総トンから30万総トン増加され,定期船13万3,000総トン,一般貨物船11万7,000総トン,専用船76万5,000総トン,油送船81万総トン,合計182万5,000総トン(うち三国間専従船26万総トン)と非常に大規模なものとなったが,40年においては,ほとんど建造途上にあり,国際収支にはその効果を発揮するに至つていない。
わが国の貿易規模は今後も急速な拡大を続けるものと思われるので邦船の積取比率を向上させ,海運国際収支を改善させるためにも,わが国の貿易構造に適合した商船隊の拡充を今後長期にわたって続けるとともに,邦船の三国間輸送を促進し,積極的に外貨の獲得を図る必要がある。
|