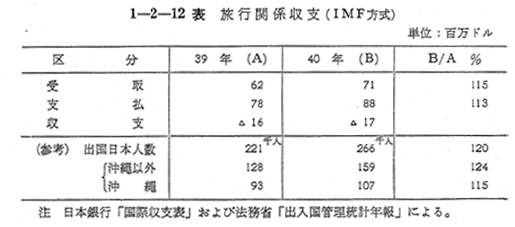|
2 観光関係国際収支
40年の旅行関係国際収支(IMF方式)をみると 〔1−2−12表〕に示すように,まず受取りは対前年比15%増の7,100万ドル,支払いは13%増の8,800万ドルで収支は前年に比しさらに30万ドル悪化して約1,700万ドルの赤字となった。
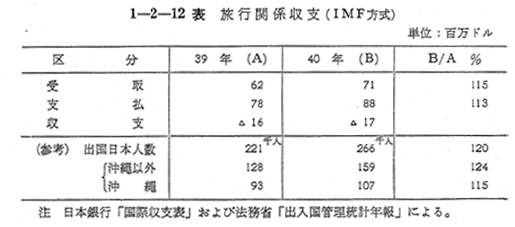
このようなわが国旅行収支の赤字基調の原因は,39年4月の観光渡航の自由化による旅行制限の緩和と国民所得の向上によって国民の海外渡航が増加したため支払が漸増している一方,日本が先進諸国から遠いという地理的条件の悪さもあって外国人観光旅行による外貨受取りが急増すると考えられないからである。
これを具体的な数字で示すと,35年以後のわが国邦人の海外渡航者数の年平均増加率は19.6%であるが,来訪外客数は同期間年平均12.5%増にすぎない。その来訪外客のうち,北アメリカ,ヨーロッパの先進諸国からの来訪客が38年,39年,40年とも70%近くを占めているが,地理的に近いアジア地域からの来訪外客は25%以下である。また39年の旅行収支でみると,北アメリカおよびヨーロッパのOECD加盟国からの受取りが84%を占め,アジア地域からの受取りは10%以下にすぎない。
次に 〔1−2−12表〕に示すように,出国日本人数の対前年伸び率が20%増であるにかかわらず,旅行収支支払いが13%増と低くおさえられた原因についてみると,39年の出国日本人の渡航目的が,商用37.7%についで観光が19.0%であつたが,40年には商用38.2%についで観光が28.2%とかなり増大し,国際観光旅行の大衆化に移行しようとする端緒が見い出されることからして,わが国邦人の海外旅行者が高所得層から中所得層まで拡大したため,近距離地域への海外旅行およびエコノミー・クラスの国際観光旅行が増大し,1人当り海外旅行支払が減少したものと思われる。
わが国の国際観光が,世界の国際観光に占める地位を,IMFの世界の旅行関係受取額に対して日本の受取額の割合でみると,39年では0.6%を占めているにすぎず,外客観光旅行者数をIUOTO(官設観光機関国際同盟)の資料でみると,世界の外客観行旅行者数の0.3%である。また旅行収支で主要国の国際観光活動と日本の国際観光活動を比較すると 〔1−2−13図〕のとおりであり,イタリア,スイス,スペイン等のいわゆる観光国の受取りの15分の1ないし7分の1程度である。

このようなわが国国際観光活動の低い地位を向上させること,およびわが国旅行収支の赤字基調を改善するために,41年3月に在外宣伝事務所をメキシコ・シティに新設して中南米に対する宣伝網の拡充を行なったほか,40年度には,国際会議または行事の誘致促進のための機関の設立および旅行あつせん業者の外貨獲得に伴なう税制上の優遇措置を講ずるとともに産業観光の推進を行なったが,今後もさらに海外観光宣伝の強化および外国人観光客受入れ体制の整備が必要であろう。
|