|
1 船舶輸出昭和40年度の輸出船受注量は,554万総トン,9億3,000万ドルに達し,これまでの最高であった38年度の437万総トン,7億7,936万ドルを凌いだ。これは,前年度に引き続き,ギリシャ系および北欧系船主よりばら積貨物船を中心に大量の受注があったためである。このように40年度において輸出船の大量受注を確保できたのは,米国の5年間にわたる景気の七異を中心とする自由主義経済圏の景気の上昇に伴う海上荷動き量の増加と海運市況の好況により,船腹の需要がおう盛であったことによることはもちろんであるが,わが国の造船技術が世界的に高く評価されている上に,世界の海運が求めている超大型船舶の建造体制が整い,建造方式の合理化による工数の低減などコスト引下げの努力が払われたこと,契約納期が確実であることなどが世界の輸出船市場におけるわが国造船業の国際競争力を有利にしたことによるものである。 輸出船の受注量を仕向国別にみると,リベリア向けが3億6,019万ドルで最も多く,以下ノルウェーの1億7,841万ドル,パナマの1億3,541万ドル,英国(バーミューダを含む)の5,685万ドル,メキシコの4,694万ドルと続いている。最近の輸出船の地域別受注比率をみると, 〔1−2−14図〕に示すとおり,ヨーロッパ向けが次第に増加している反面,ソ連を含む共産圏諸国からの受注が激減している。つぎにこれを船種についてみると,貨物船の受注比率が39年度の54%から40年度には63%と増加しており,とくに兼用船の受注量が39年度の4隻15万4,000総トンから40年度は27隻110万2,000総トンと大幅に増加している。
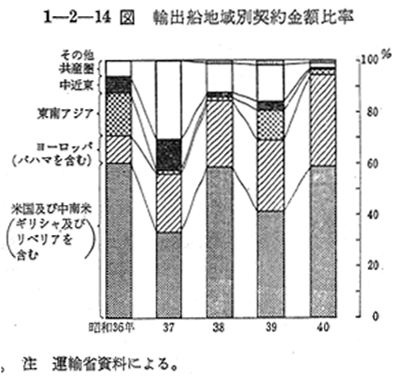
船舶用内燃機関の輸出契約実績は,ディーゼル機関を中心として,40年は1,256万ドルに達し,39年の842万ドルに比べて49.2%の大幅な増加を示した。これを地域別にみると,東南アジア向けが全体の84%を占め,輸出の中心となっているが,共産圏およびヨーロッパ向けも着実な伸びを示している。
|