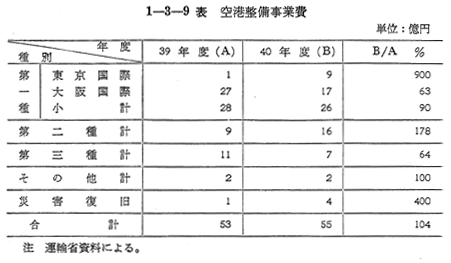|
5 航空輸送施設
航空輸送施設は,基礎施設としての飛行場施設と,可動施設としての航空機等とに大きく分けられる。まず,空港施設についてみると,空港に対する投資の推移を総合輸送活動指数に表わされる輸送活動の動向と比較すると, 〔1−3−8図〕のとおりであり,輸送需要は投資の伸びの規模を大幅に上回って増大をつづけている。

昭和40年度の空港に対する投資額は 〔1−3−9表〕に示すとおり,対前年度比3.8%増の55億円で,東京,大阪両国際空港並びに函館,広島等7空港その他の整備が行なわれた。
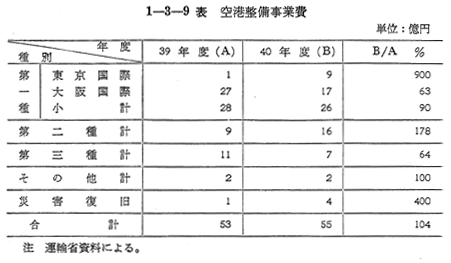
東京国際空港は,基本施設の整備が39年度で一応完了したため40年度から5カ年計画でエプロンの拡充および航空機の整備地域の整備が実施にうつされ,大阪国際空港においては,33年度から実施されている滑走路およびエプロン新設を骨子とする整備工事が継続された。一方,第2種および第3種等のローカル空港に対してはYS-11型機およびバイカウント828型機のローカル線への投入に対処するため,滑走路の延長および補強を重点とした整備が行なわれた。
航空機の発着回数の激増により,飽和状態にある東京国際空港を救済するための新国際空港建設については,数年前から調査・計画が進められ,40年6月,新空港公団法が成立し,建設候補地の選定が行なわれてきたが,41年7月,千葉県成田市の三里塚地区が,建設地として閣議決定され,46年の使用開始を目途として,用地補償費を含め約1,300億円で建設が推進されることとなつた。
大阪国際空港においても,急激な需要増加により,すでに飽和点に達しており,現在,前述のように拡張,整備が実施されてはいるものの,新空港建設の必要性は,ますます強くなっている。
つぎに,可動施設としての航空機についてみると,国内および国際を合計した航空機の数を39年度と40年度と比較すると,単発が22機,双発14機,ヘリコプター16機の増加をみており,新機種としては,多発では,ボーイング727型双発で,パイパー式PA-30型機が40年3月初めてわが国に登場した。
路線の面では,国内線においてはローカル線に重点がおかれ,14路線の新規開設をみ,その結果,座席キロは40年度において幹線では対前年度比29%増の33億5,000万キロ,ローカル線で,33%増の16億4,000万キロ,合計で30%増の498万キロとなつた。
一方,国際線においては,輸送力の増強と国際競争力の向上をはかるために,40年度においては,新たにDC-8型機を3機,国際線に投入し,それに伴う路線の拡充を行なつた結果,有効座席キロにおいて,39年度の30億座席キロから42億座席キロヘと40%の伸びを示した。
|