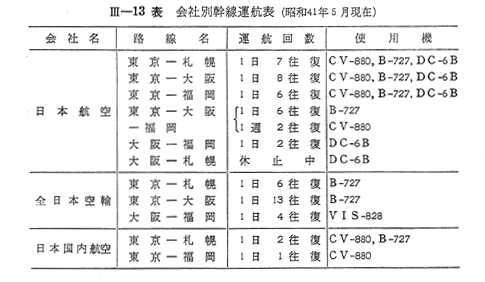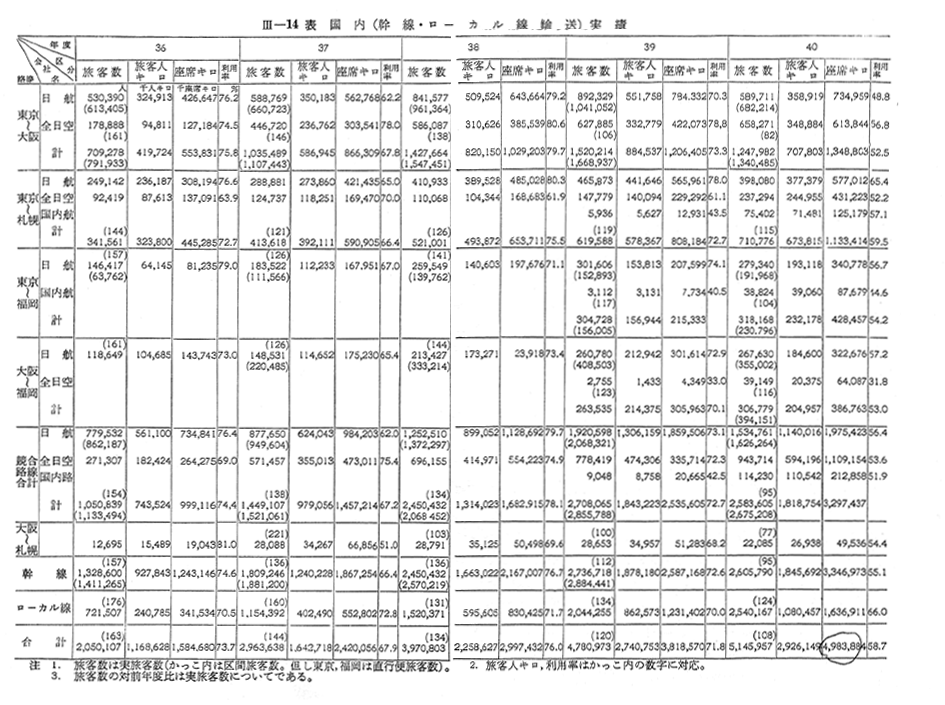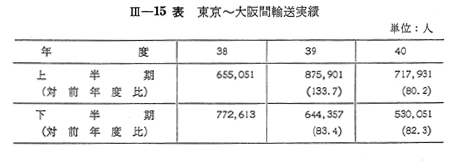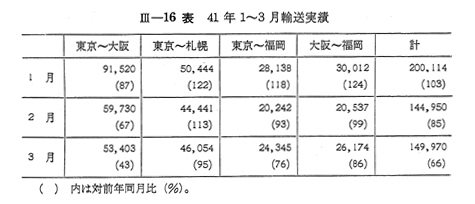|
1 幹線
札幌から東京,大阪を経て福岡に至る路線を国内航空路線の大動脈として幹線と呼び,41年5月現在で日本航空(株),全日本空輸(株),日本国内航空(株)の3社が事業を営んでいたが,その運航状況は 〔III−13表〕のとおりである。
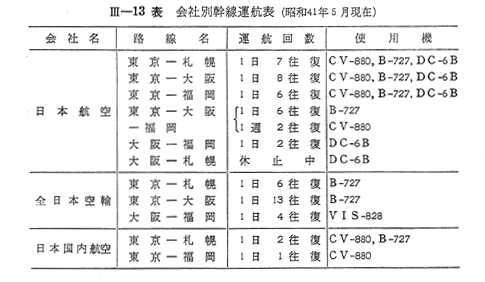
幹線における使用機材は,大阪一福岡間の一部及び夜間便を除き,ジェット化されている。
航空機のジェット化は,より安全,より低廉,より高速,かつより大量の輸送を目指す航空企業にとつて当然なことといえよう。
しかしながら以下述べるように,幹線における需要は,大幅に減退し深刻な問題になつている現在,ジェット機の導入は慎重に行なうことを要し,供給力の過剰により過当競争の弊をまねかないよう,各社間において,需要に対応した適切な機数の調整が必要である。幹線における輸送実績は, 〔III−14表〕のとおりであつて,国内航空輸送に占める比率は,前述のごとく旅客人キロで63%を占め,営業面における幹線の比重は,依然として大きいとはいうものの39年度実績を下回ることになつた。
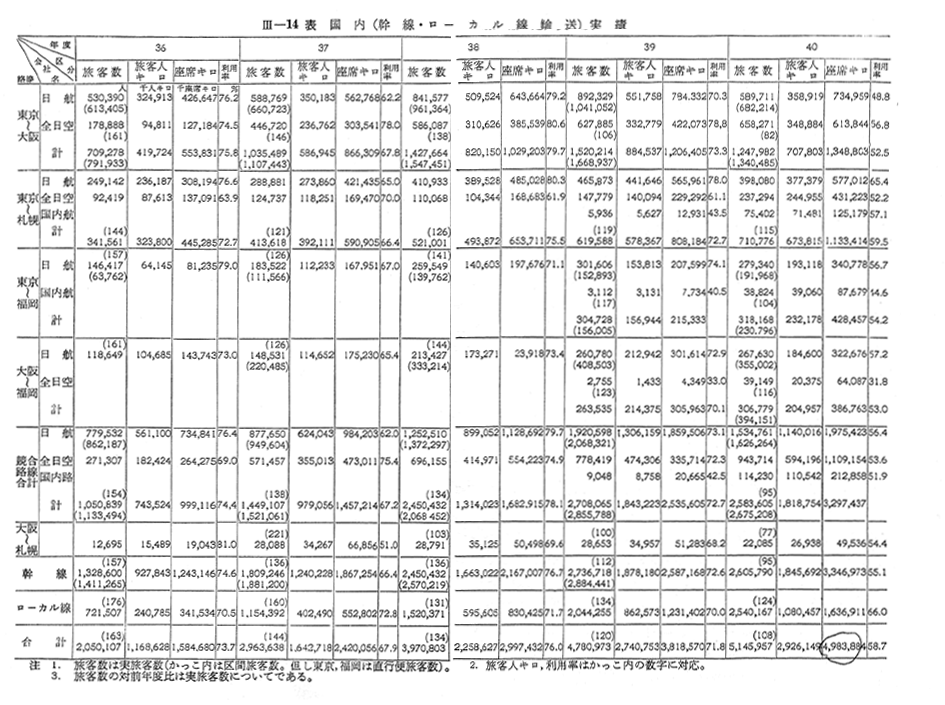
実線を路線別にみると,東京―札幌間および大阪―福岡間は対前年度比15〜16%増であるが,東京―福岡間は4%増に留まり,東京―大阪間に至つては18%の減,夏季だけレシプロ機DC-6B型機により運航した大阪―札幌間も23%の減となつており,伸び率が最も大きい大阪―福岡間の16%増にしても同表から判るように,従来の航空需要の伸びからみても決して十分とはいえない。
このように40年度の航空需要が伸び悩んだ原因としては,東海道新幹線への需要の転移,全日空機事故に伴う航空需要の減退のほかに,これらの原因とは関係のない大阪―札幌間の需要減が示すように,39年度からの一般的な経済活動の沈滞がまず航空需要全体に抑止的作用を及ぼしたものといえよう。
また,需要の著しい東京大阪間については東海道新幹線の影響がまず第一に考えられる。
すなわち39年度において新幹線の影響は下期のみであったが,40年度においては,年度全体にその影響を蒙ったこと,40年11月以降運航回数の増加およびスピード・アップを伴う本格的営業が開始されたことである。いま,多少の時期のずれはあるが,東海道新幹線の営業開始前を39年度下半期および40年度上半期,本格的営業開始後を40年度下半期とし,上半期下半期別にそれぞれ前年度と対比してみると 〔III−15表〕のとおりとなり,おおまかにいつて対前年度比で東海道新幹線の営業開始により約20%,その本格的な営業開始によりさらに約20%の需要減となつたことが判る。これは,それまで30%以上の需要の伸びを示してきたことを考慮すれば,実質的には40%以上の低下になるものと考えられる。
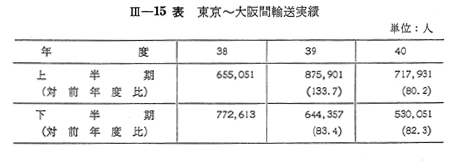
幹線における航空需要をさらに他の輸送機関に転移せしめたものは,41年2月から3月にかけて相次いで発生したジェット機の事故であつた。2月4日に全日空B-727型機が東京湾で墜落し,そのちょうど1月後の3月4日には,カナダ・パシフィック航空のDC-8型機が東京国際空港において炎上し,翌3月5日には,BOACのB-707型機が富士山附近で墜落し,合計321名の尊い犠牲者をだした。
この悪夢のような一連の事故は,一般の利用者を航空機から,特にジェット機から遠ざけることになり,これはジェット化を進めている幹線輸送には大きな打撃となつた。
今,この打撃をみるため,41年1月から3月までの幹線旅客数を前年同月と比較すると, 〔III−16表〕のとおりとなり,2月4日の事故により対前年度比率で各路線とも実質上約20%の需要減となり,さらに3月4日および5日の事故により各路線ともさらに約20%の需要減となつたのが判る。
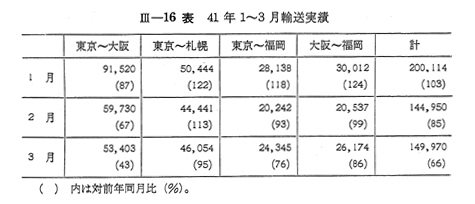
41年3月の幹線の輸送旅客数は,40年3月の66%であり,最も需要の減退が著しかった東京―大阪間にあっては40年3月のわずか43%にすぎない。同様に41年3月の座席利用率を40年3月のそれと比較してみると,東京―大阪では75%から25%に,東京―札幌間では80%から53%に,東京―福岡間では77%から41%に,大阪―福岡間では52%から42%に,幹線全体でも76%から42%と著しく低下し,特に低下の著しい東京―大阪間においては,日本航空(株),全日本空輸(株)とも41年4月からそれぞれ1日15往復から13往復へと2往復ずつの減便を余儀なくされた。
以上のように幹線における航空需要はきわめて停滞した状況にあり,需要の急速な回復は,甚だ難しいといわなければならない。
しかしながら,今後の幹線の拠点である東京,大阪,札幌及び福岡の各地点間の空陸を含めた全体の輸送需要の増大を考慮すると,ローカル線との接続の緊密化,共通乗車券の採用,搭乗手続の簡易化等需要獲得のための対策を検討し,企業として必要可能な努力を尽すとともに,今回の事故の原因を徹底的に究明し,航空輸送の安全性の向上に努めることにより,一般の信頼感を回復することがなによりも必要であり,またそれにより,今後も常業的に成立する路線の運営が可能になると思われる。
|