|
2 国際貿易における海上輸送コストの低減
わが国の外航海運による輸送量とそれに伴う運賃収入の推移は 〔1−2−6図〕のとおりである。輸送量の伸びが運賃収入の伸びを上回つており,輸送量当り運賃収入は低下の一途をたどつている。このような運賃率低下の原因は,輸送量当り運賃の高い定期船輸送のわが国海運において占める割合が減少していることもあるが,主として外航海運における運航原価が技術革新などにより低下したことである。運航原価の低下は船腹需給バランスによる運賃市況の低迷とあいまつて海上運賃率を低めた。
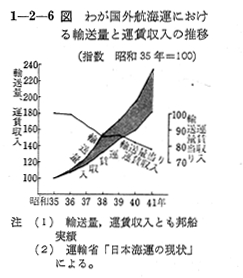
原燃料のうちわが国経済において占める比重が高く,また輸入依存度が高い原油と鉄鉱石(輸入依存度は,原油99%,鉄鉱石97%)についてみることにする。原油および鉄鉱石の輸入量は年々増加し,41年でそれぞれ8,600万トンおよび4,600万トンであり, 〔1−2−7図〕に示すように輸入量全体の37.5%および20.1%を占めている。また,海上輸送距離は輸入相手先国の構成変化に伴いますます遠距離化している。すなわち原油は中近東地域に集中し,その依存度が約90%になつている方,東南アジアからの輸入が減少している。このため平均輸送距離は35年の6,000カイリから,40年には6,400カイリになつた。
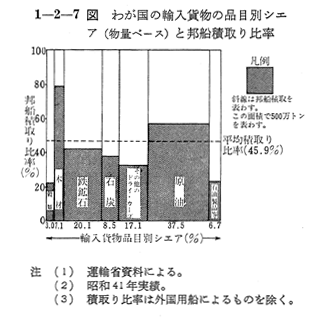
また,鉄鉱石は東南アジアを中心とした地域構成から南米,北米(近年オーストラリヤも加わつた。)などにソースの転換が行なわれ,平均輸送距離は35年の4,000カイリから40年には4,500カイリになつた。このような輸送需要の増加傾向に対して,これらの輸入CIF価格に占める海上運賃の割合は非常に大きく,40年において原油で26%,鉄鉱石で40%に及んでいる。このように海上運賃は原燃料の原価構成に大きな比重をもつているが,その運賃率は年々低下し,40年には35年と比べてトン・カイリ当り原油で41%,鉄鉱石で18%の低下を示した。物的流通コストが人件費の上昇などの要因により,一般的に上昇しているときに原燃料の海上運賃率がこのように低下したのはなぜであろうか。その1は海上輸送における原価が低減したことである。海士輸送の原価の低減は,船舶の大型化,専用船化,操縦の自動化などによつて行なわれた。船舶の船型の推移は 〔1−2−8図〕のとおりであり,大型化傾向は特に油送船において顕著である。鉄鉱石専用船は昭和33年度にはじめて建造されたが,荷役費が節減できること,大型化が可能なこと,効率的な輸送が行なえることなどの理由により増加の一途をたどり,40年の邦船による鉄鉱石の総輸送量のうち鉄鉱石専用船によるものの割合は65%に達した。さらに大型の鉱石兼油送船を三国間輸送と結合するいわゆるコンバイン配船も行なわれた。このような船舶の大型化,専用船化に伴い船舶の建造単価(総トン当り船価)は 〔1−2−9図〕のとおり低下した。また外航船員の賃金は毎年著しい上昇を続けているが,船舶の自動化などにより乗組員数はほぼ横ばいである。このため,輸送トン数当りの船員費は低下傾向にある。さらに主要燃料であるC重油の価格は 〔1−2−10図〕のとおり低下している。原燃料の海上運賃率が低下していることの理由の2として,船腹の需給バランスにより不定期船およびタンカーの短期的な運賃市況が基調としては低迷していることがあげられる。ただし,わが国海運による原油,鉄鉱石の輸入輸送はその大部分が特定荷主と2,3年から長いものでは20年位の長期契約を結んで行なつているので短期的な需給バランスによる影響は間接的なものであつた。
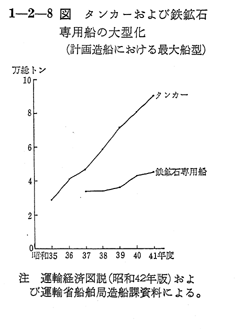
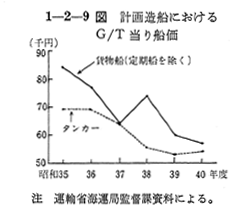
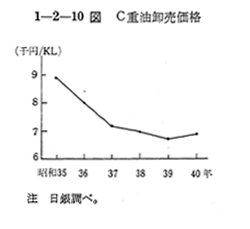
輸入品の海上運賃率の低減は,原油,鉄鉱石だけでなく他の輸入品の輸送においても行なわれたが,この2品目の海上運賃率の低減がわが国経済に及ぼしたさまざまな効果のうち,物価値下げへの寄与を産業関連表を用いて試算すると, 〔1−2−11表〕に示すように,昭和35年から40年までの期間で鉄鋼1.6%,石油製品11.1%の価格低下など多くの部門の価格低下に寄与した。この表によつて卸売物価指数の低下率を試算すると0.84%になる。
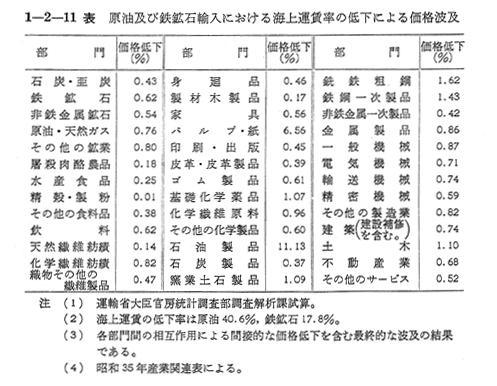
昭和41年2月に大西洋にコンテナ船が登場し,国際海運もコンテナ時代に入つた。海上コンテナによる輸送の特色は,港湾における荷役時間を短縮すること,このため船型の大型化が可能なこと,こん包費が減少すること,貨物の破損,紛失,盗難のおそれがなくなること,輸送時間の短縮と到着日時が明確化することなどにある。集荷が確実に行なわれ,これらの特色を生かすことができれば,国際的な流通コストを在来の方式に比べて大幅に減少することができる。
|