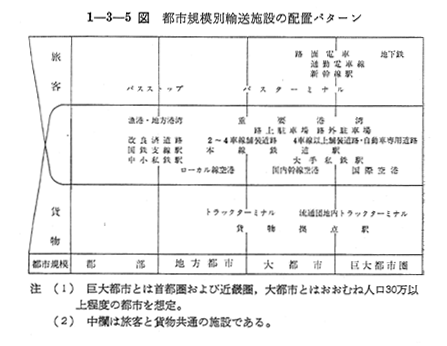|
1 都市における輸送施設の配置パターン
都市における輸送施設の配置パターンは,各都市の規模に対応しておおむね 〔1−3−5図〕のようであると考えられる。すなわち都市の規模が大きくなるにつれて輸送需要の増加傾向,質的複雑化傾向に応じて,輸送施設の面においても量的拡大とともに質的分化が進んでいる。
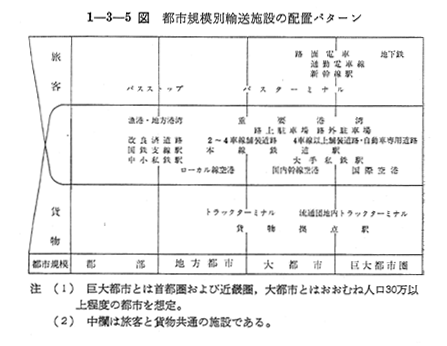
輸送施設の配置パターンをいわゆる過密過疎問題と対応させてその量的側面をみてみると,町村等の過疎地域においては輸送需要が少量なため輸送機関の運行回数も少なく,輸送サービス提供の面においても過疎問題が生じている。これらの地域において輸送施設の整備は地域の過疎状態を打開するための先行的開発投資として迎えられることが多い。これに対し,大都市等の過密地域においてはぼう大な輸送需要が発生しているにもかかわらず,輸送施設が相対的に不定しているため,輸送施設の整備はこれらの輸送需要にどのようにこたえていくかという点に焦点があてられている。
つぎに,輸送施設の配置パターンを,業務,流通,消費といつた都市機能の面からみてみると,都市が大規模になり,都市機能をより強く果たすようになるにつれ,輸送需要の複雑化,高度化傾向が進み,輸送施設についてもその量的拡大とともに質的分化,高度化が進行する。たとえば自動車関係輸送施設についてみると,地方都市においては通行および駐車の両機能を兼ねた道路の存在が一般的であるのに対し,大都市においては自動車通行帯と人の通行帯の分離(自動車専用道路がその典型である。),駐車地帯の通行地帯からの分離平面交差点の立体交差化等,種々の質的な面における分化が進行する。その他,大幹線鉄道駅,通勤電車線,地下鉄,国際空港,流通団地内トラックターミナルといつた高度な輸送施設が都市機能の維持にとつて不可欠となつてくる。
わが国の大都市における輸送施設整備の面における特徴としては,新幹線,流通団地内トラックターミナルといつた諸外国の大都市にはみられない高い水準の施設が存在または計画中である反面,都市内高速鉄道における混雑度の高さ,道路率の低さなどをもつて代表される通勤・通学輸送,道路交通混雑の問題が深刻化していることをあげることができる。
|