|
1 造船工業昭和31年以後の世界における日本造船業の地位は,順調に躍進を続け,41年には,世界の進水総トン数の46.7%を占めるに至り,第一位の地位を保つた。 このように41年度のわが国の造船業は,輸出船の大量受注に支えちれて,前年度を凌ぐ繁忙となつた。これを新造船受注実績でみると国内船の受注は総トン数で対前年度比9%増にすぎなかつたが,輸出船は対前年度比59%増で,平均44%増であり前年度の伸び率42%をさらに上回つた。 41年度の新造船受注実績7,204億円の内訳をみると,輸出船,国内船の受注実績はそれぞれ74%および26%を占め,改造許可実績は全受注額の1%未満である。 つぎに41年度の主要造船所27工場の新造船進水実績を40年度と比較すると,国内船は10%減少したが,輸出船で44%増加し,平均20%増であつた。 41年3月末現在の主要造船所27工場の新造船手持工事量を前年同月と比べると国内船5%増,輸出船56%増,平均48%増の414隻,1,415万総トン847億円であり,従来の工事実績からみて,約2年分の工事量である。 つぎに主要造船会社の収益状況をみると,新造船売上高利益率は,35年上期以後景気変動に対応した一時的な上げ下げがあるが,41年上期までは漸次低下傾向にあり,修繕船およびその他工事の売上高利益率の向上にもかかわらず,全体の売上高利益率の上昇を押し下げる原因となつていた。 これは,造船業の国際競争が激烈であるため,利益率を多少犠牲にしても受注しなければならなかつたためであり,「利益なき繁栄」といわれていたが,最近の受注船価はかなり適正なものとなつてきたので41年度下期については,新造船売上高利益率もいくらか上昇するものと思われる。 造船業の41年度設備投資実績は,38業者総計275億円で,40年度投資実績に比べて21.3%減と大幅な落ち込みをみせた。これは船台,船渠,岸壁に対する工事が著しく減少し,船台用運搬設備などの付帯設備への投資が主体となつたからである。 つぎに資金の源泉について製造業平均(内部資金48%,外部資金52%)と比較すると,造船業の外部資金依存度は79%で,著しく高い。自己資本比率は,製造業平均26%に対し,造船業は16%である。造船業の資産構成としては,売上債権,仕掛品の全資産に対する比率が高いことが特徴である。 造船業について,大企業と中小企業の経営格差をみると, 〔1−4−14表〕のとおりで,中小企業の造船業は,自己資本収益率を除いてその他の指標は著しく悪い。一方大企業の造船業も,製造業平均と比較すると収益性が悪いことがわかる。
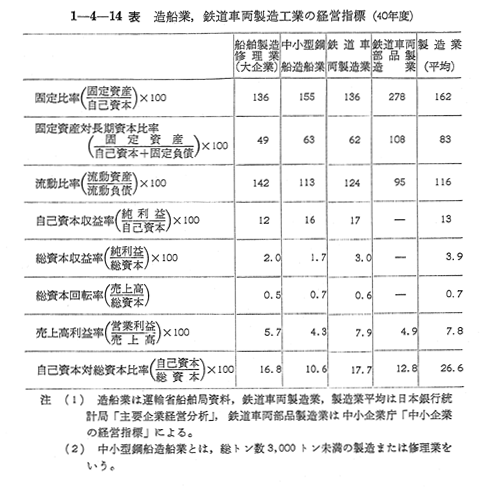
|