|
1 砂利・砂・石材砂利・砂・石材の需要はコンクリート構築物の建設需要の増大,道路整備の進展などに伴い,順調な伸びを示しており,昭和39年には35年と比べて61%の増加を示している。また,地区別消費量では東京都,大阪府および愛知県の比重が大きく,これらの3都府県で全体の1/4程度を占めている。 輸送量は 〔2−2−6図〕に示すように35年度対比で64%増となつているが,特に関東における伸びが大きい。 つぎに,輸送構造をみると,わが国は急流河川が多く砂利・砂生産には比較的恵まれ,消費地の近くで採取される場合が多かつたことなどからダンプカーに代表される自動車輸送への依存度がきわめて高く,35年度では,総輸送量の93.4%が自動車輸送となつている。 しかし,需要増大に比例して,近隣骨材資源は次第に枯渇化の様相を呈したため,輸送の遠距離化は避け難い傾向となり,近年域内流動率はやや下つている。それにもかかわらず自動車輸送への傾斜は,近年,一層その度を増していることが指摘される。 また,地域別の変化をみると南関東では北関東,静岡県などからの流入量が著増しており・平均輸送距離は伸びてきているとみられるものの,静岡県からの船舶輸送を除いては,依然として自動車輸送への依存度が高い。阪神では,和歌山県,徳島県からの供給がふえているが,その輸送は船舶によることが多いため,内航海運のシエアが漸増している。さらに,東海については,その地形上,砂利・砂の大量生産地に恵まれているため,現在でも,域内供給でほぼまかなわれている。
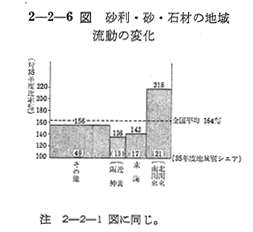
すでに述べたように,砂利・砂・石材は,資源枯渇化のため,近年急速に輸送の遠距離化傾向がみられるが,今後も需要増大が見込まれるので,いままでのように自動車に極端に依存した輸送構造には,安全性や合理性の点で解決すべき問題が含まれているので,船舶,鉄道など大量輸送機関への転換促進,大規模な砕石山の新規開発による安定的供給源の確保などを骨子とする改善策の樹立,実施が関係者間で進められている。
|