|
2 石炭
かつてわが国の基幹産業の一つと数えられた石炭産業も,昭和30年代のめざましいエネルギー革命の進行のうちに,きびしい合理化策の遂行を迫られ,生産は昭和36年度をピークに減少の一途をたどり,35年度対比で3.5%減となつている。
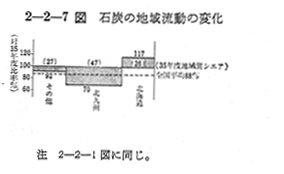
また輸送機関別輸送量についてみると,鉄道14%減,自動車16%減となつているが,内航海運は4%の減少にとどまつており,特に域間輸送の分野では80%以上のシエアを占めるに至つている。
|
|
2 石炭
かつてわが国の基幹産業の一つと数えられた石炭産業も,昭和30年代のめざましいエネルギー革命の進行のうちに,きびしい合理化策の遂行を迫られ,生産は昭和36年度をピークに減少の一途をたどり,35年度対比で3.5%減となつている。
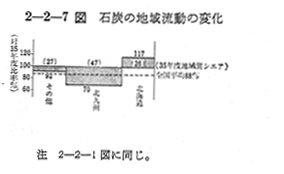
また輸送機関別輸送量についてみると,鉄道14%減,自動車16%減となつているが,内航海運は4%の減少にとどまつており,特に域間輸送の分野では80%以上のシエアを占めるに至つている。
|