|
3 内航海運の近代化
慢性的な船腹過剰と企業の脆弱性を克服し,内航海運の合理化,近代化を図るため,3年計画による近代的経済船の整備と過剰船腹の処理および内航海運企業の適正規模化を行なうことを骨子とする「内航海運対策要網」の実施について,以下まとめて概観したい。
-14.gif)
-15.gif)
この対策が決定したのは,41年5月であつたが,その後立法化を進め,第53回国会において特定船舶整備公団法の一部改正および内航海運業法の一部改正(同法案は第51回国会に提出され,継続審議となつていた。)が行なわれ,12月26日に公布された。
I 特定船舶整備公団法の一部改正
② つぎの業務を新設する。 (イ) 解撤建造者への融資および債務の保証 (ロ) 共同係船を行なう内航海運組合等への融資 ③ 政府は,公団または金融機関に対し,債務保証,利子補給および損失補償をすることができることとする。
II 内航海運業法の一部改正
② 内航運送業については一定の支配船腹量の保有を要すること等の許可基準を定める。 ③ 事業計画の変更,事業の譲渡し,譲受け,合併および相続を認可制とする。 ④ 許可または認可には条件を附し,およびこれを変更することができることとする。 ⑤ 改正法の施行は,42年4月1日とし,現に登録を受けている内航海運業者の許可制への切替えは,44年9月30日までに行ない,許可申請は,44年3月1日から同月31日までに行なわせる。 これらにより「内航海運対策」は実施に移されることになつたがすでに述べたように,内航海運市況の好転等その後の情勢の変化により,閣議決定当時の計画をそのままの形で達成することが不可能となり,つぎのように実施されることとなつた。
① 貨物船代替建造計画
-16.gif)
② 係船実施計画
これは,内航海運組合法第8条に基づく調整事業として行なわれるもので,昭和44年3月末までに法定耐用年数に達しない100総トン以上の鋼製貨物船を対象とし,係船を実施した組合員に対しては,組合から係船船舶1重量トン当り月額平均約1,800円を交付し,他方,借入金の返済にあてるため,稼働中の船舶については,1重量トン当り月額13円以内において一定の納付金を組合員から徴収するものである。 これに要する資金は,さきに述べたように船舶整備公団が総連合会に貸し付けることとなつているが,総連合会は,この債務履行を確保するため,組合員から連帯保証書を提出させ,また,納付金の保証として手形保証を行なわせる等文字通り全内航海運業者が一体となつて行なう事業であり,従来の内航海運業界のあり方からみると画期的なことである。前述のようにその規模は若干縮小されたとはいえ,今後の不況対策についての一つの体制がつくられたものとして,その意義はきめて大きいといえよう。
③ 許可制の実施
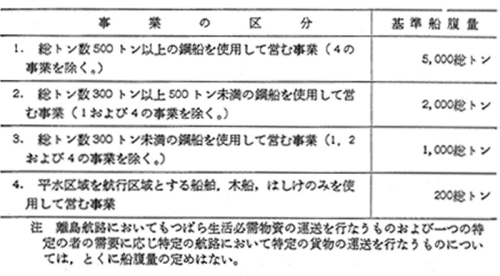
これらによつて,内航海運の適正規模化を進めていくことになるが現在登録を受けて内航海運業を営んでいる者については,2年半の猶予期間が設けられているので,この間に,事業の実態に即応して集約化,協業化を指導していくこととしている。 なお,以上の内航海運対策は,主として船舶整備公団を通じて実施しているものであり,同公団の内航海運における使命は一段と重要なものとなつており,それに伴ない名称が変更され,理事,職員の定員も増加している。 そのほか,資金量の増加とともに,42年度からは新たに88億円の船舶整備債券を発行する予定であり,また新たに海水油濁防止のための施策の一環として,船内のビルジ排出防止装置の設置について,所要資金の融資を行なうことになり,それぞれ所要の措置が進められている。
内航船の近代化は老朽船の解撤と経済船の建造を目的とし,過剰船腹の解消も含めて船舶整備公団を中心に進められてきた。公団との共有方式による代替建造により,36年度から38年度まで3年間は戦標船対策として113隻,16万2,000総トンの戦標船を解撤し,54隻12万1,000総トンの貨物船,油送船および石炭専用船が建造され,39年度からは老朽船対策として解撤1.5に対し建造1の割合で近代的経済船を建造することとし,39,40年の2年度で老朽船1,462隻22万5,997総トンを解撤し,99隻14万2,681総トンの内航専用船が建造された。40年度までに公団により建造された内航船は約27万総トンとなり,全内航船舶の10%弱に達している。さらに41年度からは,内航海運対策要綱に基づき,3年計画で代替建造を進めるとともに,建造船の範囲も近海船にまで拡げて,船舶の近代化を進めることとしている。
(イ) 船舶の自動化
(ロ) 船舶の専用船化
-17.gif)
(ハ) その他
また,陸上輸送において用いられているパレットあるいはコンテナによる方式が海上貨物にも徐々に現われ,一部内航船舶にも混載の形で利用されるようになつてきたが,埠頭および船内における荷役設備の問題やコンテナの回収の問題が未解決のため未だ十分にその効果を発揮していない。しかし,外航海運におけるコンテナ専用船の就航を43年秋にひかえ,内航においても支線輸送(フイダーサービス)としての内航のコンテナ尊用船の問題が緊急の話題となつている。内航独自のコンテナ専用船の技術的問題については,一応標準船の規格の成案も出来上り,埠頭の整備と内航コンテナ貨物の地域的分布の検討が今後の課題となつている。
|