|
1 収支状況
最初に,日本航空(株)の収支状況をみると,昭和41年度における国内線収益は,171億4,500万円で前年度比24%の増収となつた。
一方,支出は164億3,000万円で同比21%増(10年定額法の場合だと,156億3,500万円で同比15%増)となり,差引経常利益は7億1,700万円(旧ベースの場合15億1,000万円)で,前年度の2億4,200万円を大きく上回る業績を示した。
国内線がこのように好調だつたのは,41年2月,3月の一連の事故,11月の全日空松山沖事故により航空旅客の伸びは全体としては停滞気味だつたにもかかわらず,日本航空の場合,東京――利幌,東京――福岡の長距離旅客が増えて旅客収入が増大したことおよび損益分岐重量利用率が大幅に低下したことによるものである。
つぎに,幹線および主要ローカル線を運営する全日本空輸(株)についてみれば,まず,収入においては,前年度にみられた東海道新幹線への需要の転移,および41年2月のジェット機事故による旅客需要の減退に加え,41年11月のYS-11型機事故による影響は,路線収入に多大の衝撃をあたえ,41年度定期および不定期運送事業による旅客収入は137億5,367万円で,前年度149億9,070万円に比し8%減収となつた。一方貨物収入は前年度に比し39%,郵便収入は29%増と好調な推移を示した。
また,支出面においては支払利息(11億8,419万円)が経営の圧迫要因となつているほか,前記事故による特別損失(4,300万円)の支出増がある。
以上により本年度収支決算においては,経常損失17億7,623万円となり,特別損失において,前年度内部留保した航空機特別償却引当金(1億5千万円)を取崩し,当期損失16億7,952万円となつた。当期損失は前期繰越利益(1億447万円),任意積立金(1億2,100万円),利益準備金(1億円),資本準備金(376万円),を取崩し次期繰越損失として13億5千万円が42年度へ繰越されることとなつた。
つぎに,日本国内航空(株)であるが,同社は41年7月幹線の運営を日本航空に委託し,再建計画の基本方針として思い切つた路線,機材,人員等各般にわたる合理化を進めてきた。まず路線についてみると,新規路線は,大阪-宇部線,札幌-旭川線のみの開設にとどめ,不採算路線の整理を行ない,航空機については将来YS-11型機のみとする含みでYS-11型機とND-262型機の2機種に統一し,あわせて整備基地を統合することによつて採算の向上を図つた。
収入面においては,松山沖事故の影響を受け,旅客収入は前年度に比し,6%の減収となつたが,郵便,貨物需要の新規開拓,幹線委託による年度後半の増収等により路線収入は28億9,540万円と前年度に比し19%の増収となつた。これに対し支出面は,支払利息(9億1,728万円),営業権償却額(1億9,340万円),開発費償却額(1億6,982万円)等の支出があり,特別損失として固定資産処分損(3億2千万円),棚卸資産処分損(1億5,768万円)等の損失要因がある。
以上により本年度収支決算においては,経常損失21億7,798万円,当期損失26億6,790万円を計上するにいたり,前期繰越損失42億6,836万円とあわせ,次期繰越損失として69億3,626万円が42年度へ繰越されることとなつた。
その他のローカル路線運営会社,東亜航空(株)および長崎航空(株)については,東亜航空1億9,800万円,長崎航空1億700万円とそれぞれ当期損失の計上を余儀なくされたが,航空事故による旅客需要の減少等によるものといえよう。
以上,全日本空輸,日本国内航空,東亜航空および長崎航空のローカル路線各社はいずれも損失計上となつたが,その経営状況は会社により差異はあるものの,本年度は度重なる航空事故の影響も漸次解消しつつあり,今後の各社経営状況は次第に改善の方向へ推移するものと思われる。
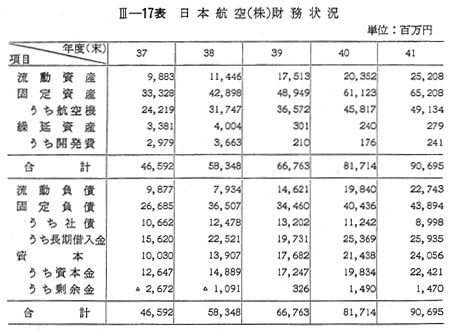
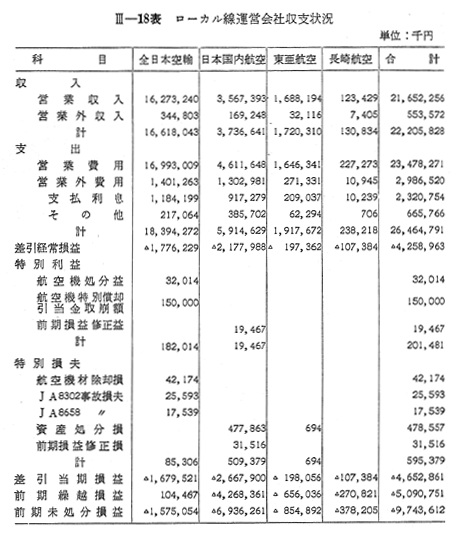
|