|
1 航空保安無線施設近年における航空交通の質的量的発達に対応して,航空保安無線施設の近代化を過去数年にわたり実施し,安全性と定期性の確保を図つて来た。 すなわち,戦後,レシプロ機を対象とし,NDB(無指向性中波無線標識)等により構成されていたわが国の航空路を,幹線から順次VOR(超短波全方向式無線標識-航空機からこの施設からの方位を知りうるような特性をもつたVHF電波を発射する地上装置)またはVORTAC(ボルタック-VORとタカンを組み合せた施設で,航空機はこの施設から発射する電波により,この施設からの方位と距離を知ることができる)化し,現在までに15ヵ所の整備を完了し,引き続き沼の端,仙台,名古屋,大津の各VORおよび出雲VORTACを整備中である。 これらの施設が完成すれば,国内航空路のうち最も基幹的な航空路についてVOR化が完了することとなる。 空港における援助施設としては,東京および名古屋空港にILS(計器着陸装置)を設置し,視界不良の際の着陸を可能としている。 また,東京,大阪,名古屋,宮崎の各空港にASR(空港監視レーダー),PAR(精測進入レーダー)を設置し,空港周辺約60海里の範囲にわたるターミナルレーダー管制業務および着陸誘導管制業務を行なつているほか,鹿児島,仙台および高松空港にASRを建設中である。 航空路管制施設としては,関東地区用として箱根辰沢山にARSR(航空路監視レーダー)の設置を完了し,引き続いて九州地区用として福岡県三郡山に同様の施設を建設中であるほか,電子計算機の導入による東京航空交通管制部の航空路管制自動化も整備中である。これらを含め現在航空局の管理する航空保安無線施設の現勢は 〔III−26表〕のとおりである。 将来については,今後の航空交通の急速な進展に対処して,高度の安全を確保するため,航空援助施設の整備を従来に比べ大幅に促進するとともに,施設の信頼性と性能向上を図らねばならない。 すなわち,航空路についてはVORおよびTACAN又ばDME(距離測定用装置)による国内航空路の整備,新東京国際空港の出現に伴う東京ターミナルエリヤの安城整備等を並行して推進し,国際空港においてはカテゴリーIIILSを始め,必要とするすべての航空援助施設,管制施設を整備して,高度の安全の確保を実現するほか,国内主要空路についても,滑走路を計器滑走路化し,ILS,ASR,VOR,TACANおよびDMEを可急的すみやかに整備する必要がある。 また航空路管制の能率化のために,近畿地区をはじめ仙台地区,札幌地区にもARSRを設置し,全国をレーダー網をもつて覆うよう航空路監視レーダを整備するとともに管制の自動化を推進して管制能率の向上を図る必要がある。 一方,昭和42年設立された電子航法研究所において,ILSカテゴリーIIおよびIII,精密VOR,衛星航法および管制自動化等に関する試験,開発ならびに評価試験を計画的に実施し,機材の信頼性と性能の向上を図り,航空安全の確保に寄与する計画である。
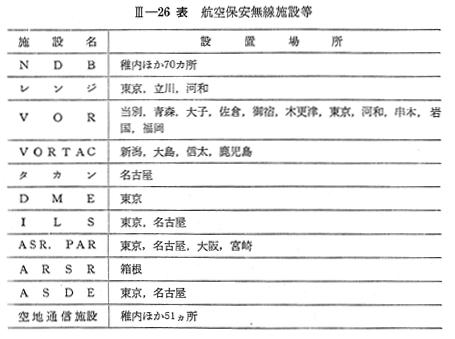
|