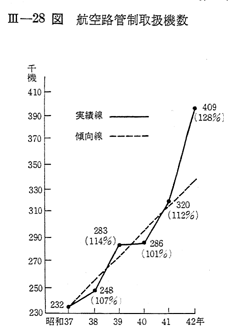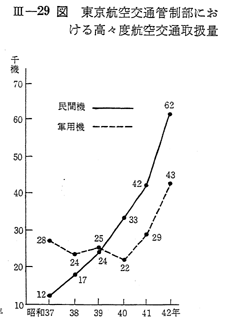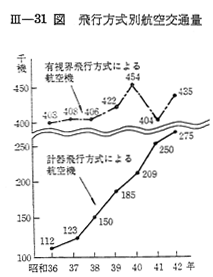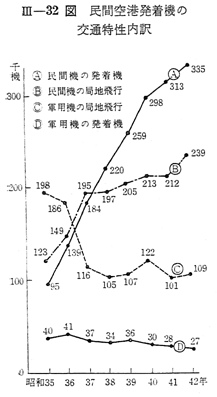|
1 航空交通管制の現況
航空交通管制を実施する機関は,大別して航空路管制機関とターミナル管制機関の2種に分けられるが,航空交通管制の現況をこれらの管制機関が取扱つた航空交通の量的推移と質的変化を中心に概説するとつぎのとおりである。
(1) 航空露管制機関の取扱つた航空交通
現在わが国における航空路管制業務は東京,札幌および福岡の三航空交通管制部で行なわれているが,これらの航空路管制機関が昭和皿年に取扱つた出発機,到着機,通過機の合計は409,071機で前年の機数合計319,991機と比較すると89,060機の増加であつた。
〔III−28図〕は37年からの航空交通実績を実線であらわし,42年までの平均的傾向線を点線であらわしたものである。その増加速度は毎年約2万機であつたが,42年の実績値は41年までの傾向値を大きく上回つた。これは極東情勢の緊迫という特殊事情によるものと考えられる。取扱機数は短距離飛行の航空機も長距離飛行の航空機も一様に1機として数えているのであるが,これらの航空機の飛行回数をルート上の位置通報点ごとの通過機数として算出した延飛行画数(Fix Posting)は非常に増大している。
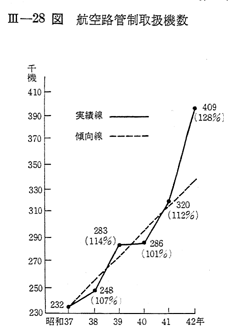
この航空交通の量的増加と相まつて近年航空交通の質的変化,すなわちジエット機の出現にともなう航空交通の高速化が問題とされに至つた。
たとえば,東京航空交通管制部における37年の高々度(7,300メートル以上の高度をいう。)航空交通取扱機数は4万機程度にすぎなかつたが 〔III−29図〕に示すとおり42年には10万6,089機と約6万機(2.6倍)の急増を示しており,その増加部分の主体は多数旅客を運送する民間ジェット機の増加によるものである。
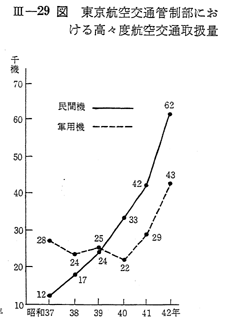
42年におけるわが国全体の高々度航空交通量は17万8,808機で,今や航空路管制機関の全取扱交通量(41万機)の43%を占めるに至つた。
(2) ターミナル管制機関の取扱つた航空交通
ターミナル管制機関とは,飛行場管制業務,進入管制業務,ターミナル・レーダー管制業務および着陸誘導管制業務を行なう機関の総称であり,いずれも空港内に設置されている。現在,運輸省管理のターミナル管制機は東京国際空港ほか20をかぞえるが昭和42年にこれらの管制機関が取扱つた航空交通量は71万364機で前年の65万4,022機と比較すると,5万6,342機(9%)の増加であつた。 〔III−31図〕
これを飛行方式別にみると,42年における計器飛行方式の交通量(27万5,234機)は前年の交通量(24万9,712機)より約2万5,000機(10%)の増加を示している。
〔III−31図〕は 〔III−30図〕の全航空交通量を飛行方式別に分けたものであるが,これによると計器飛行方式による航空機は年々増加の一途をたどつているが,有視界飛行方式による航空機はほぼ横ばいの推移を示している。
また,両者の割合をみると36年における全発着機に対する計器飛行方式による航空機の割合は22%であつたものが,42年において39%を占めるに至つている。このことは従来有視界飛行方式で飛行していた航空機も,天候に左右されることの少ない計器飛行方式に次第に切換えていく傾向にあることを物語つている。

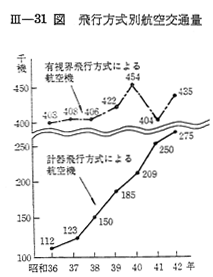
〔III−32図〕は同じ民間空港21カ所の総交通量について民間機,軍用機の別,および局地飛行とそれ以外の発着機の別で分析したものである。本図によれば民間機(局地飛行を除く。)の発着機がターミナル航空交通量増加の主要素をなしている。
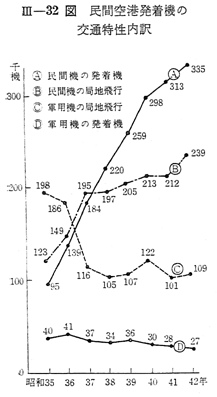
|