|
1 損益状況昭和43年度の企業経営の一般動向を日銀「主要企業経営分析」によつてみると, 〔1−4−3表〕のとおり,上期において売上高,純利益ともやや伸びが鈍化したものの,下期には再び大幅な伸長を記録した。 運輸事業の営業収支状況は 〔1−4−4表〕に示すように,外航海運,航空など一部の業種を除いては,前年に比べ一般に営業収入は,かなり増加しているものの,営業費用が収入を上回る増加率を示し,このため利益の減少,赤字幅の増大という傾向が認められる。 国鉄は,貨物収入の伸び悩み,人件費の急増,債務累積に伴う金利負担の増大などのため,純損失1,344億円と,39年度以降5年連続赤字決算となるという極めて憂慮すべき状態にある。このため政府は,日本国有鉄道財政再建特別措置法(44年5月)に基づき,44年度より,財政援助および国鉄の合理化を中心とした,国鉄財政再建施策を推進することとなつた。 大手私鉄は旅客輸送量の伸びが低かつたことに加えて人件費の増加を主因として営業費用が増大して,利益は減少している。中小私鉄は,旅客輸送量自体が一般に横ばいないし減少傾向にあり,人件費の増大とあいまつて年々経営は悪化している。 自動車運送業は,旅客輸送,貨物輸送ともに人件費が過半を占める営業費用の増加が営業収入の伸びを上回り,利益面での悪化を招いている。 外航海運は,集約による企業規模の拡大,再建計画施策の推進により,経営は著しく改善され,減価償却不足額と借入金約定償還延滞額のすべてを44年3月期までに解消した。 内航海運は一般経済の好況と,内航海運諸対策の効果を反映して改善の方向に向かつているが,43年度においては一社平均でみると前期繰越損失を解消するに至らなかつた。 航空運送事業は,前年に引き続き順調な推移を示した。国際線における旅客の増加,国内線における座席利用率の向上などにより増収増益となつた。
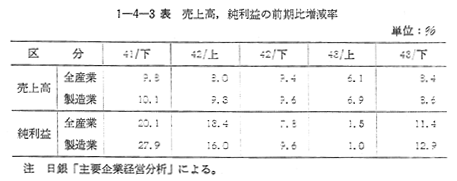
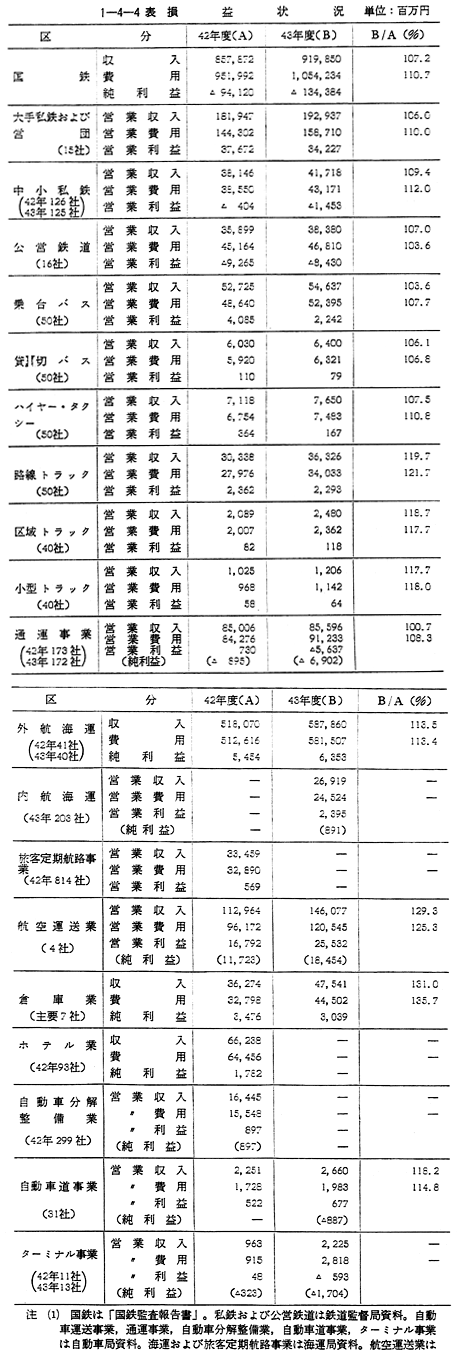
|