|
4 航空機工業
わが国の航空機工業の年間生産額は 〔1−4−17図〕に示すように39年には728億円に達したが,40年及び41年は防衛需要の空白期で急減した。しかし,42年には第3次防衛力整備計画の発足などにより789億円に増大し,更に43年には922億円と航空再開後の最高を記録した。昭和43年と42年の生産額を需要先別に対比すると,防衛需要がほぼ横ばいであつたのに対し,内需は13%増,輸出は17.8%増となり,従来,防衛需要に依存してきた航空機工業が内需,輸出の伸びで成長したことを示している。これは,40年,41年の防衛需要空白期に官民一体となつて民需を伸ばす努力をした成果である。航空機の輸出は,38年から40年まで毎年僅か数機に過ぎなかつたが,41年43機,42年27機,43年63機と増加した。その主体はYS-11,MU-2,KH-4,FA-200など純国産の民間機である。
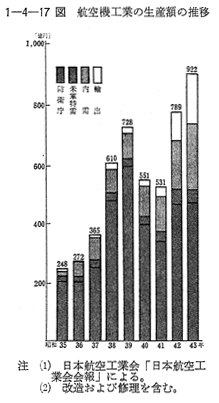
わが国の航空機工業は,一部の修理専門企業を除き,ほとんどが母体重工業企業の一事業部門として兼営されている。これは,依存度の高い防衛需要が通常不安定で,この増減によつて伸縮自在なことを要するからである。航空機工業25社の航空機部門が企業全体に占める割合は,僅か4〜5%(43年の純売上高において)に過ぎない。航空機部門の売上高純利益率は,42年下期で2%,43年上期で3.3%程度であり,おおむね企業全体の利益率よりも低い。
|