|
3 物的流通コスト
わが国経済が高度成長のなかで開放経済へ移行するにしたがつて,内外の企業間競争は激化し,企業はそれぞれ生産規模の拡大,国際競争力強化のため新設備の建設,新技術の導入など生産面の近代化,合理化を進め生産コストの低減に努めているが,これと並んで,近年流通コストに対する関心を高め,その低減を図るべく流通面での近代化を積極的に進めつつある。わが国における総流通コストを推計すると 〔2−2−23表〕に示すとおり,昭和40年において国全体で11兆6,605億円と国民総生産額の37%に当り,各輸送機関の貨物運賃,倉庫料金,荷造梱包費などの物資流通費の合計は総流通コストの約29%を占めている。個々の商品について流通コストの占める割合をみると 〔2−2−24図〕に示すとおりである。このように国民経済的にみても,また個々の商品についてみても,かなりのウエイトを占める流通部門を近代化し,そのコストを軽減することは,生産コストの低減と同じ意味において,単に企業の競争力の強化にとどまらず,物価の安定など国民生活につながる大きな政策課題であり,40年以降,物価問題懇談会,資源調査会,産業構造審議会,運輸経済懇談会など各種審議会において流通近代化に積極的に取組んでいる。
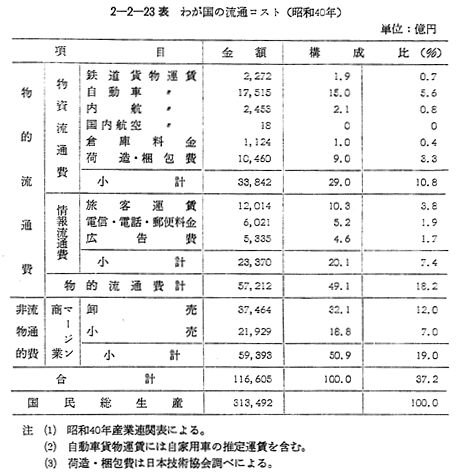
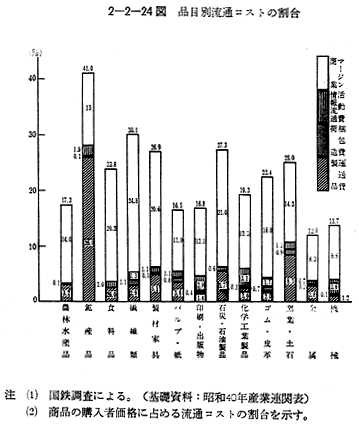
個々の企業においても,それぞれ生産物がもつ流通特性にふさわしい流通の近代化を進めているが,一般的傾向としては,輸送にあたつて輸送の効率化,輸送経費の低廉化を図るため,大量物資については専用輸送を行ない,小口貨物についてはコンテナ,パレットを利用して貨物をユニット化し,機械荷役との組合せによつて需要者側までの協同一貫輸送を進めている。貨物のユニット化は荷造,包装の規格化が前提となるが,これはユニット化による荷傷みの減少がもたらす荷造,包装の簡易化とともに,荷造,包装経費の低減となり,流通コストの低減に大きな効果をもたらしている。こうした物資流通の合理化に対応して需要動向の把握,取引情報網の整備,流通機構の再編成などによつて重複・中継輸送をできうる限り排除し,中間マージンの削減と合わせて流通コストの低減を図ろうとしている。さらに一部の業種では企業間の販売,出荷などの業務提携により交錯輸送を解消しようとする動きもみられる。
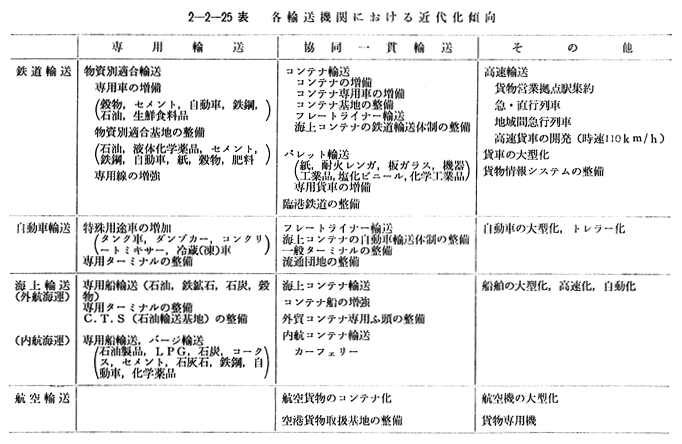
|