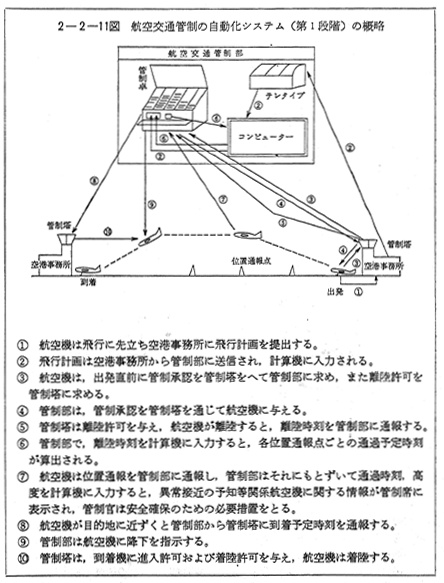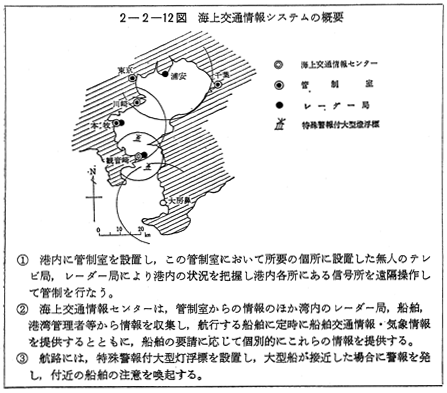|
3 航空交通管制システム
近年の旅客輸送需要の質的高度化は,航空輸送需要の急増に端的に示されているといえるであろう。航空輸送需要の増加と航空機の高速化,大型化にともない,空の航行の安全を守る航空交通管制業務の重要性は格段に高くなつてきた。
航空交通管制業務は,航空機の航行の安全と円滑を図るため,飛行経路・飛行高度の承認,航空機間の間隔の設定,離着陸の順序に関する許可等を行なっている。
航空交通量の増加と航空機の高速化により,管制官は従来より多くのデータを短時間に作成,計算し,あるいは記録,連絡を行ないながら本来の管制業務-安全間隔の設定,指示――を実施することになるので,管制において最も重要な,判断を的確に下すことが困難になってきた。そこで,附随的業務はコンピユーターに行なわせ,同時にその算出データーは管制官の本来の業務に使用して,航空交通の安全性,規則性,迅速性を確保することが必要となつてきた。
このため,運輸省では40年度から東京航空交通管制部における航空交通管制の自動化を三段階に分けて進めることとし,43年3月にその第1段階の整備が完了,45年度より本格的運用に入ることになつた。
第1段階では 〔2−2−11図〕に示すように,従来各管制席において,飛行情報カードの作成,位置通報点通過予定時刻の算出を手作業により行なつていたものを,コンピューターにより処理を行ない,また,航空機間に異常接近が予想されるときは,関係航空機の識別符号,高度,時刻等を管制席のテレビ式表示器に写し出し,適切な処置をとることを目的としている。以降第2,第3段階では,着陸順位の決定,レーダーによる自動識刷,自動高度表示等を行なうことになつている。
このシステムの導入により,航空交通管制業務の情報処理の近代化は大幅に進み,運行の安全が著しく高まるのみならず,空域利用の効率化,管制能力の増大など,多くのメリットが期待されている。
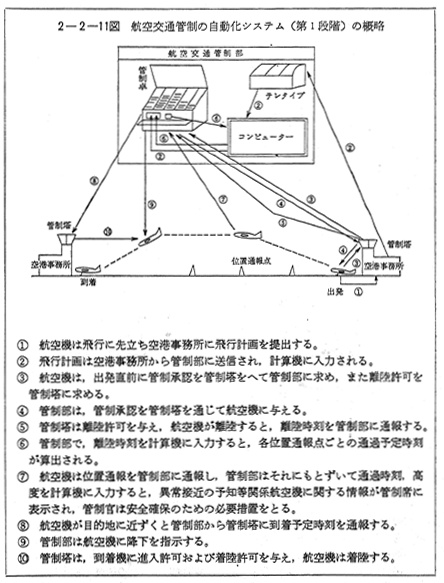
現在,京浜港等の主要港においては,信号所を設置し,船舶の行合いを避けるなどの航行管制を行なつているが,最近の海上交通の増大・複雑化,港湾の整備等に伴つて,新たに航行管制を行なう必要のある水域が増加する等,既設の信号所では航行安全上十分な管制を行なうことが困難となつてきた。一方,港域外においては,船舶は自船のレーダと見張りのみによつて前方の状況を把握している現状であり,浦賀水道のような船舶のふくそうする狭水道における航行の安全と運航能率の増進を図るためには,陸上からきめ細かな情報を与えて,航行船舶を援助することがとくに必要となつてきている。このため,従来の航行援助および航行管制の体制を抜本的に再検討し,航行援助業務と航行管制業務を体化し,狭水道・港内を通じて一貫したサービスを提供する海上交通情報システムを確立することとし,さしあたり,必要性の高い東京湾について45年度から具体的計画を検討することとしている。
その概要は, 〔2−2−12図〕のとおりである。
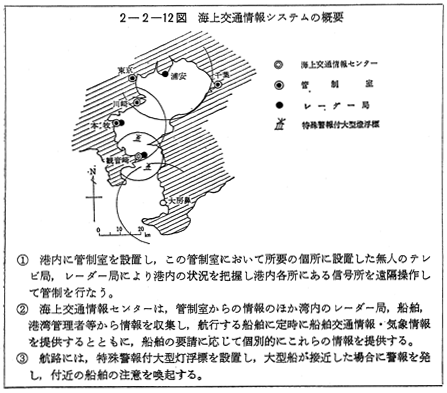
|