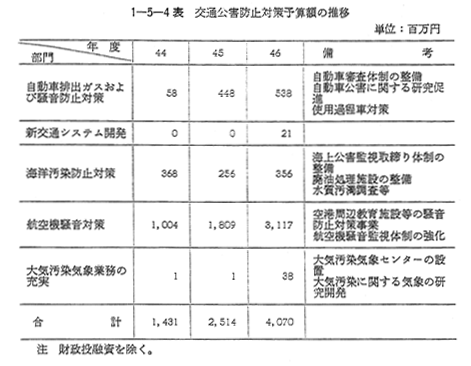|
2 交通公害低減への努力
交通公害防止対策のための予算額は 〔1−5−4表〕に示したとおりで,45年度,46年度を通じて大幅に増大している。
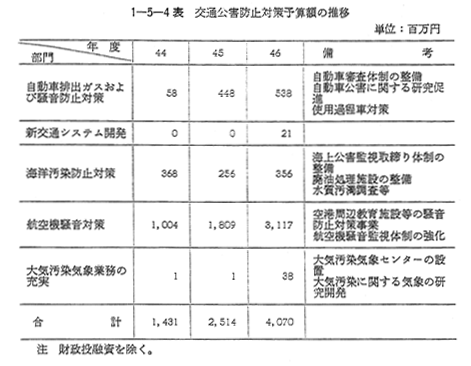
(1) 大気汚染
自動車の排出ガスによる大気汚染については,45年7月道路運送車両の保安基準を改正し,一酸化炭素の排出については,従来は対象外であつた液化石油ガスを燃料とする車および軽自動車についても規制をはじめ,さらに使用過程車に対してアイドリング時の規制を開始した。これとともに,光化学スモツグの起因物質のひとつである炭化水素については,ブローバイ・ガス環元装置の備付け義務を課すことにより,その排出の低減をはかつている。
45年7月,運輸技術審議会は「自動車排出ガス対策基本計画」において,48年,50年の二段階に分けた自動車排出ガスの低減目標を示した。これは,最も汚染のすすんでいるといわれる東京都における自動車排出ガス総量を,50年,55年においてそれぞれ38年,36年相当量にまで低減するという目標に沿つて算出されたもので,単位走行距離あたりの排出ガスを重量で規制する,いわゆる重量規制により段階的に規制を強化しようとするものである。
また,自動車排出ガスによる大気汚染実態の科学的究明,内燃機関の改良促進,排出ガス清浄装置の開発,無公害自動車の開発等今後の排出ガス対策の方向についても示されており,今後はこの計画に沿つた対策が推進される。
このほか,地方自治体が行なつているスモツグ警報等,大気汚染に関する緊急の措置に協力するため,46年6月,東京,大阪に大気汚染気象センターを設置し,必要な気象情報のしゆう集と提供を開始した。
(2) 海洋汚染
45年12月には,船舶および海津施設から海洋に油および廃棄物を排出することを規制し,廃液の適正な処理を確保するとともに海洋の汚染の防除のための措置を講ずることにより,海洋の汚染を防止し,海洋環境の保全に資することを目的として,「海洋汚染防止法」が公布された。この法律は47年6月までには全面的に施行されることとなつており,「水質汚濁防止法」,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」,「下水道法」等とともに,海洋の汚染防止に強い効力を発揮することが期待される。
しかし,゛きれいな海"は,ひとり法律の制定のみによつて取り戻せるものではない。海洋汚染防止に対する関係者の認識を深めるとともに,公害防止施設の増強,汚染調査,監視取締り体制の整備を図る必要がある。45年度においても廃油処理施設の整備等,これらの施策を引続き実施し,さらに46年度からは海上保安庁に海上公害課を新設し,海洋汚染の著しい東京湾,伊勢湾,瀬戸内海等を管轄する管区海上保安本部に海上公害監視センターを新設した。また,46年6月21日〜7月20日には広く国民の海洋汚染防止に関する意識を昂揚させるため,「海をきれいにする月間」を設定し,海上公害追放の啓発運動を全国的に展開した。
(3) 交通騒音
航空機の騒音については,とくに問題の生じている東京,大阪両空港において,騒音の実態を把握するため,周辺地域の騒音測定を従来より行なつており,これに加えて飛行経路の改善,深夜におけるジエツト機の離着陸の制限などの軽減措置を講じているほか,空港周辺の学校および公共施設等の騒音防止工事に対する助成をすすめている。
自動車の騒音については,従来から道路運送車両の保安基準により,定常走行騒音および排気騒音について規制していたが,45年11月,保安基準の改正を行ない,車種別に規制を強化するとともに,加速時の騒音についても新たに規制を加え,新型車については,46年4月,在来型式の新車については47年1月からこれを適用することとなつた。なお,従来現制対象外であつた原付自転車についても規制を行なうこととし,これを含めて全車についてその定常走行騒音を85ホン以下に規制することとなつた。
このように,45年度においても交通公害の低減のために規制の強化,測定・検査・監視体制の整備,これらをバツクアツプするための研究開発の促進と各方面にわたつて積極的に対策が講じられたが,交通公害のない国土を実現するためには,現存する輸送機関の発生する公害を減少させ,公害によつて生じる被害を最小限にとどめるためにあらゆる努力をはらうことはもちろんであるが,今後はさらにすすんで,新たに大気汚染も騒音もない輸送機関の開発をすすめることが肝要であろう。
|