|
2 運輸事業の経営状況
運輸事業の46年度の事業別損益状況は 〔1−4−2表〕のとおりで,大手私鉄および営団,路線トラツク,倉庫業を除いては,収入の伸びに対して,営業費用の伸びが上回り,人件費等諸経費が経営の圧迫要因となつていることがわかる。
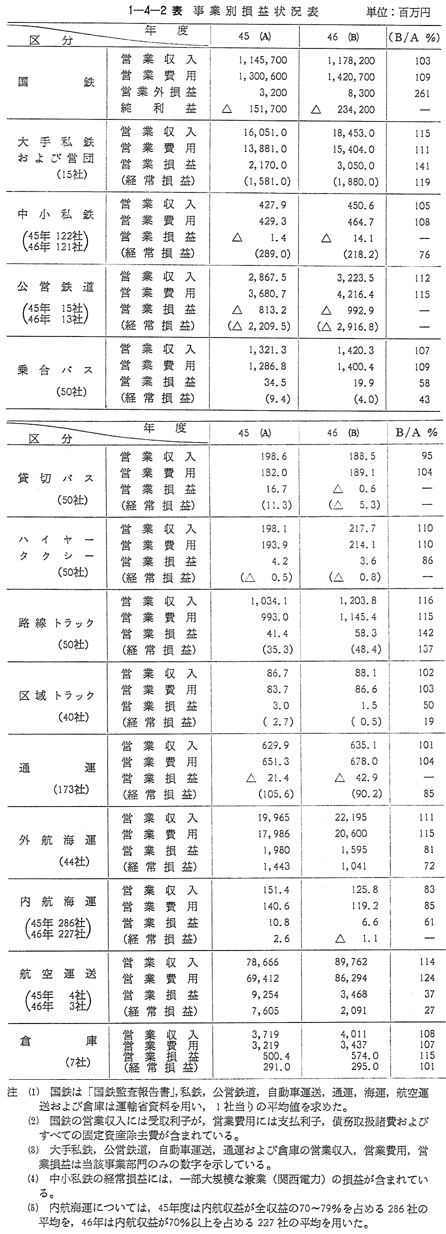
営業損益についてみると,大手私鉄および営団,路線トラック,倉庫業の利益が増加したほかは利益は減少しており,中小私鉄,公営鉄道については,赤字幅が拡大し,貸切バスは赤字決算に転落した。
運輸事業の46年度の事業別財務状況は 〔1−4−3表〕のとおりで,運輸事業の一般的な特徴として固定比率が高く,公営鉄道および倉庫業を除いて,全産業平均を上回つており,とくに国鉄,大手私鉄および営団,乗合バス,貸切バス,外航および内航海運業は高い比率を示している。固定長期適合率は,貸切バス,ハイヤー・タクシー,区域トラックを除いておおむね100%前後で財務の安定性は一応保たれているといえる。
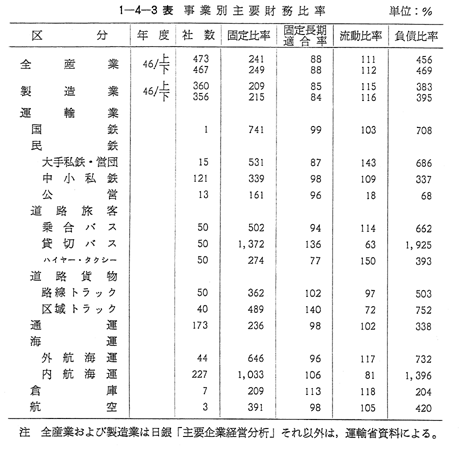
企業財務の流動性,すなわち,企業の支払能力を示す流動比率についてみると,大手私鉄および営団およびハイヤー・タクシーを除いては,全産業にほぼ等しいかそれを下回つている。
運輸事業の有形固定資産に対する付加価値額の割合を示す設備投資効率は 〔1−4−4表〕のとおり,全産業に比べ,道路運送業が大きな値を示し,従業員1人当りの有形固定資産額である労働装備率も低く,労働集約的業種であることを示している。
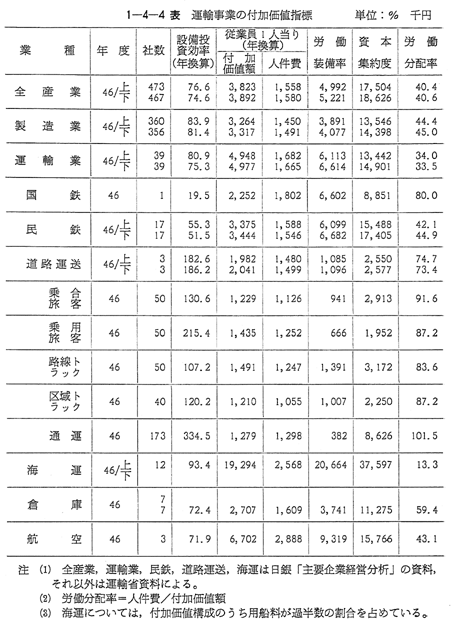
従業員1人当りの付加価値額は,全産業平均に比べ,船舶の大型化,専用化および自動化が進んでいる海運業は非常に大きな値を示しているほか,航空も上回つている。しかし,国鉄および道路運送業においては,全産業平均値をかなり下回つている。
|