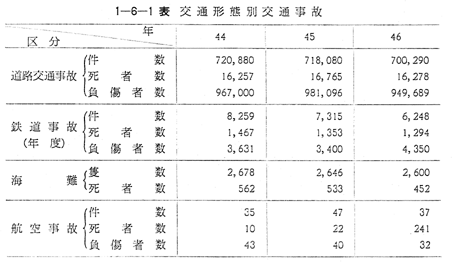|
1 交通事故の現状
交通形態別にみた最近3カ年間の交通事故の推移は 〔1−6−1表〕のとおりである。
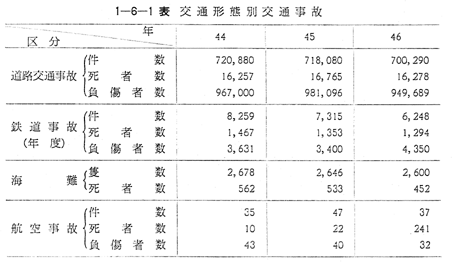
(1) 道路交通事故
最近3カ年における道路交通事故の被害をみると,死者数は1万6,000人台を,負傷者数は90万人台をそれぞれこえており,高い水準にある。道路交通事故は死者数において全交通事故の約90%を占め,国民に大きな負担を与えている。道路交通事故による国民的な損失を保険統計などから推計すると,昭和45年頃で約8,000億円に達している。これは45年度の道路総投資額の約50%にあたるものである。
しかし最近では若干明るいきざしがあらわれている。自動車走行1億台キロあたりの死者数はアメリカの約3人などと比べるといぜんとして高い水準にあるが,昭和36年38.2人,40年15.8人,45年7.7人と次第に減少してきており,安全対策の効果があがりつつあることを示している。また,46年には,戦後はじめて件数,死者数,負傷者数ともに減少した。この傾向は47年になつても続いており,47年1〜6月までの累計では前年同期比で件数においては4.5%減,死者数においては3.5%減,負傷者数においては6.8%減となつている。
46年の特徴としては, 〔1−6−2図〕のように大都市付近では交通事故が減少しているのに対し,地方の県ではモータリゼーシヨンの進行によつて増加を続けているところが多い。大都市付近において事故が減少したのは,信号,標識,歩道橋などの交通環境が整備されてきており,裏通り通行規制など交通規制が強化され,また道路混雑によつて交通量そのものも伸び悩んでいることなどによるものと思われる。死亡事故のうち,自動車対歩行者・自転車などのいわゆる「走る凶器」型の事故は47.7%と50%を割つたものの依然として高水準にある。

(2) 鉄道事故
昭和46年度の鉄道事故の件数は6,248件であり,前年度より14%減となつたが,列車衝突による負傷者数が激増(1,261名増)したため,負傷者数では前年度をかなり上回ることになつた。鉄道事故では踏切事故の比率が高く,運転事故による死者数の半分以上を占めている。踏切事故はダンプカーの無謀運転などによつて45年度まで多発していたが,踏切事故防止対策が強化された結果,46年度においては減少した。反面46年10月の近鉄の総谷トンネル内での列車衝突(25名死亡,重軽傷218名),47年3月の国鉄総武線船橋駅構内での列車衝突(重軽傷758人)など,列車運行側の責任である大事故が新たな問題となつてきている。
(3) 海難
昭和46年中に海上保安庁の取り扱つた救助を必要とする海難船舶は2,600隻で,死亡,行方不明となつた者は452人,物的損害は約207億円であつた。
とくに東京湾,伊勢湾,瀬戸内海の三海域においては,タンカーなどの船舶の大型化に加えて,カーフェリー,レジャーボートなど性能の著しく異なる船舶が狭い海域を往来し,このようなふくそう状態を反映して海難が多発しているが,これらの海域で大型タンカーなどの事故がおこつた場合には沿岸部にも相当の被害を生じさせることが予想される。47年11月に新潟港でおこつたジユリアナ号の遭難は,このような危険性が非常に大きいことを示した。
このほか,最近5年間についてみると,総トン数1万トン以上の大型タンカーの海難が漸増していること,また,カーフェリーの海難が就航隻数の増加に伴つて著しく増加していることが注目される。
(4) 航空事故
昭和46年の民間航空機による事故発生件数は,ヘリコプターの事故が大幅に減少したため前年度を大幅に下まわつたが,46年7月に「ばんだい号事故」および「全日空・自衛隊機衝突事故」が発生したため,民間人の死亡者数は241人と戦後最大となつた。そして,これら2大事故の発生は,わが国の航空保安体制への一大警鐘となり,これを契機に航空保安施設の緊急整備,空域編成の適正化など航空安全対策の強化が図られた。
また47年6月には日本の民間航空機が海外ではじめて死亡事故をおこし,86名が死亡した。
|