|
(1) 自動車排出ガス対策
自動車のめざましい普及は,'自動車排出ガスによる大気汚染問題を生ぜしめた。とくに45年5月〜6月にかけての鉛汚染問題,それにひき続いての光化学スモツグ問題の発生により,自動車排出ガス対策の強化の必要性が高まり,運輸技術審議会は,45年7月「自動車排出ガス対策基本計画」を中間答申として取りまとめた。これによると,48年および50年を目標に段階的に規制を強化し,自動車排出ガス総量を50年においては38年相当量,55年においては36年相当量とすることを目標としており,自動車排出ガス対策の柱となつている。しかし,最近の光化学スモツグのひん発化等により,これにさらに検討を加える必要がでてきている。
規制範囲の拡大については,41年から道路運送車両法により一酸化炭素の規制が行なわれてきたが,鉛汚染問題と光化学スモツグ問題の生起から46年度には,新たに炭化水素,窒素酸化物,鉛化合物および粒子状物質(デイーゼル黒煙)も有害物質として規制の対象となつた。
さらに,45年8月には,LPガスを燃料とする新車の最高濃度も1.5%以下にすることとした。また,新車に対する規制のみならず45年8月には使用過程車についてもアイドリング時の一酸化炭素濃度規制が開始されたほか,46年1月からは,軽自動車に対して最高濃度3.0%以下とするなど,大幅に規制を強化してきている。
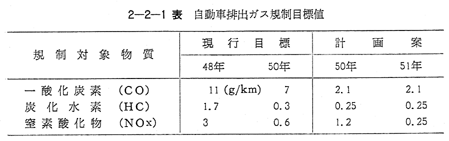
排出ガス公害は,自動車交通量の増大による集積公害であるために,その対策としては,自動車交通量の増加を極力抑制することが望ましい。交通量を規制するための方策として,一酸化炭素やオキシダント濃度が一定基準を越えた場合,運転手や使用者に対して,不用不急の運転の自粛を求めたり,交通規制を行なうことができるよう46年6月に道路交通海の一部改正が行なわれた。また,間接的な規制としては,路上駐車禁止区域の拡大等が行なわれている。
〔2−2−2図〕にみられるように定期点検整備を行なつた車は行なわない軍と比較して大幅に一酸化炭素の排出量が少ない。このような整備の効果を重視し,整備不良による多量の排出ガス発生を防止するために点検項目の充実,実施体制の強化を図つてきた。他方自動車の使用者に対して排出ガス減少に効果ある18項目について,半年ごとの定期点検整備を義務づけている。
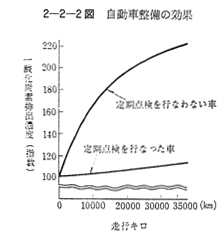
現在の自動車は,ガソリンや液化石油ガスを多量に消費し,環境保全上問題が多い。このため都市環境と調和する交通機関として,低無公害車の開発が世界各国で急がれており,わが国でもハイブリツド車(エンジンと電池等との併用),ガスタービン車,電気自動車等の実用化が促進されている。とくにハイブリツド車について,運輸省では,マイクロバスタイプの研究開発を推進することにしており,ハイブリツドエンジンの小型化が課題となつている。現在までの具体例としては東京におけるハイブリツド方式によるバスの試作,大阪での電気バスの路線運行があげられる。
|