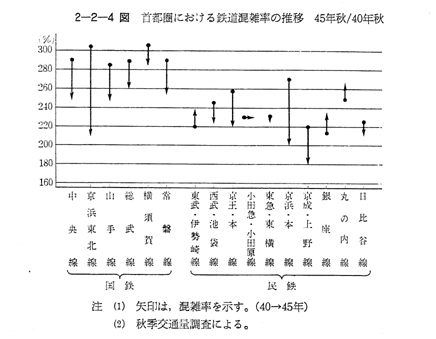|
(1) 通勤,通学輸送の改善
都市化により都市部での通勤,通学輸送需要は急激に拡大してきた。45年の国勢調査によると,15歳以上の就業者,就学者のうち交通機関を使つて通勤,通学しているものは67.2%を占めており,今日の国民の生活意識と通勤事情との関連は,ますます密接になってきているといえよう。
一例として,経済企画庁が行なつた「国民選好度調査」をみると国に対する要望として「道路,交通の是非力を入れて欲しい」と答えたものが52.5%%を占めている。
労働科学研究所の行なつた調査研究によると往復2時間満員電車で通勤すると,409カロリーのエネルギーが消費される一例として。これは通常8時間労働分のエネルギー750〜850カロリーの半分に相当するものである。
このような通勤による負担を軽減するために各交通機関では,輸送力を増強し,通勤混雑の緩和に努めてきている。輸送力増強を首都交通圏の鉄道についてみると,30年に比べ45年には,営業キロで約200㎞,車両数で約7,000両増大している。とくに,都市交通の主役として強力な整備が進められてきた地下鉄については,45年には30年に比べて,営業キロで6倍,車両数で10倍と大幅に拡充されてきている。
また,都市周辺部から都心部への輸送を受けもつ郊外鉄道についても,営業キロで約10%増,車両数で約180%増とそれぞれ伸びてきている。施設面の整備とならんで,郊外鉄道と地下鉄の相互乗入れなど制度面での整備も行なわれてきた。これらの鉄道輸送力増強策により,主要混雑区間の最混雑1時間あたりの輸送力の伸びを見ると35年に比べて45年には,国鉄で約1.5倍,民鉄で約2倍に増強されており 〔2−2−4図〕に示されるようにほとんどの路線で混雑率は低下してきている。
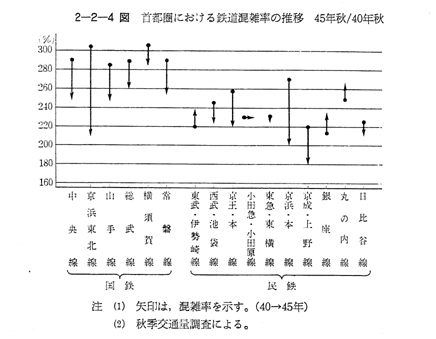
しかし,現状はいまだとうてい満足できるものではない。改善されてきているとはいえ,最混雑1時間あたりの混雑率は,おおむね200%を超えており,車内で満足に週刊誌も読めない状態である。今後は,昭和60年を目標に150%(新聞が楽に読める状態)実現をめざして輸送力を増強してゆく必要があろう。
また,都市交通の混雑は,路面交通の渋滞の激化となつてあらわれている。
路面交通混雑を渋滞発生状況でみると,東京では 〔2−2−5図〕に示すように40年以降渋滞時間は増加の一途をたどり,渋滞度3以上の渋滞発生状況についてみると,40年には1日平均254時間であつたものが,46年には約2.5倍の662時間になつている。このため,バス,路面電車の運行速度が低下し,通勤通学輸送に不可欠の定時性が確保できなくなり,サービスの低下を招いてきた。このため,バスに対しては定時性の回復を目的として45年度から大都市各地でバス優先レーンが設定され,さらにより一層の効果をねらつて46年12月からは東京で7路線,大阪で2路線のバス専用レーンが案施された。東京の例では平均33.6%のスピードアツプが実現され,この結果,バスの定時性もかなり回復されてきている。しかしこれとても現状のままでは,一時的,局部的な改善の効果しかあげえないと思われる。

総じて,これら通勤問題を交通施設の後追い的改善によつて根本的に解決することはできず,事務所の地方・都市周辺部への分散,都心部の高層住宅化による職住接近など都市計画的観点からの抜本的対策が必要とされる。
|